退職代行は、会社との直接交渉を避け、円満に退職できる便利なサービスとして注目を集めています。
しかし、代行業者を使って辞めようとすることで、場合によっては余計なトラブルを生む原因になることもあるため、注意が必要です。
本記事では、退職代行で起こりうる9つのトラブル事例を紹介し、退職を成功させるための具体的な準備や対策を解説します。


退職代行で起こる主なトラブル事例9選
退職代行サービスは、スムーズな退職をサポートする便利なサービスとして注目を集めています。しかし、適切な知識や準備がないまま利用すると、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
ここでは、実際に起こり得る主なトラブル事例とその対処法について詳しく解説していきます。
上記について詳しく解説していきます。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)退職代行の利用はリスクもあるため、気軽に利用すべきではありません。
トラブルに巻き込まれる可能性と、退職代行を利用するメリットを天秤にかけ、利用を検討する必要があります。
会社が退職を認めずに出社を強要される
退職代行を利用しても、会社側が退職を認めず、出社を強要されるケースが稀に発生することがあります。
雇用期間に定めのない正社員の場合、法律上はいつでも退職の申し入れが可能で、退職届提出から2週間経過すれば法律上退職が成立します。
参照:e-GOV法令検索「民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
ですが、このようなトラブルに巻き込まれないようにするためには、退職を認められない場合に交渉が出来るように、弁護士や労働組合の退職代行に依頼することがオススメです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社が退職を認めなかくても退職は成立するものの、その後の離職票や社会保険の手続きのことを考えると、スムーズに退職を認めてもらう方法を考えた方がいいでしょう。
民間の退職代行業者は、退職に関する「交渉」をすることができません。
そのため、退職代行を使ったことで揉める可能性が予想できる場合は、最初から弁護士や団体交渉権を持つ労働組合の退職代行に依頼をするといいでしょう。




退職前の有給休暇取得が認められない
退職時に有給休暇の取得を拒否されるトラブルも少なくありません。
しかし、有給休暇の取得は労働基準法第39条で保障された労働者の権利であり、正当な理由なく取得を拒否することは出来ません。そのため、退職代行を利用したことを理由に有給休暇を認めないのは労働基準法違反となります。
参照:e-GOV法令検索「労働基準法第39条(年次有給休暇)」
このような場合、弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスであれば、法的根拠に基づいて会社側と交渉することが可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
雇用形態にかかわらず、自企業に雇用される労働者は働き始めて6か月以上が経過し、8割以上を出勤していれば有給休暇が付与されます。
ですが、職場によっては、以下のように有給休暇の利用を制限する場合があります。
・有給休暇はない
・うちは使えない
上記の有給休暇の要件を満たしていれば、法律上、有給は付与されているため、退職時にはしっかり消化するようにしましょう。




未払いの賃金が支払われない
退職代行の利用を理由に、退職金や未払いの賃金(時間外手当を含む)の支払いを拒否されるケースがあります。
当然ですが、そんなことは認められず、労働基準法第24条において、既に働いた分の賃金は必ず支払わなければならないと定められています。
参照:e-GOV法令検索「労働基準法第24条(賃金の支払)」
このような場合も、弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスを利用することで、適切な交渉が可能となるため、安心して会社を辞めることが可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
民間の退職代行サービスの場合は交渉ができないため、「給与を払わない」と会社に言われた際に、そのメッセージをそのまま自分に伝えてくるケースがあります。
せっかく退職代行を利用しても、労働基準法違反の主張をする会社に対して自分が主体的に対応する必要があります。
退職によるやり取りで疲弊することを避けるためには、弁護士や労働組合が運営する退職代行に依頼し、交渉をしてもらうことがおすすめです。


損害賠償を迫られる
ごくまれに、退職代行の利用を理由に、会社から損害賠償を請求されるケースがあります。
しかし、適切な引き継ぎを行い、退職届の提出など正当な手続きを踏んでいれば、損害賠償請求には法的根拠がありません。そのため、実際に訴訟にまで発展するケースは極めて稀といえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
上述の通り、実際に損害賠償請求をされるケースは少ないですが、退職代行を使われたことに激高した社長や上司が「損害賠償だ!」と声を上げることは意外に少なくありません。
もしもこのような状況を、退職代行を使おうとしている会社内で目にしたことがある人は、弁護士の退職代行に依頼して法的に適切な対応をしてもらうことがオススメです。


代行業者とのやりとりを拒否され手続きが進まない
会社側が退職代行業者とのやりとりを拒否し、手続きが停滞するケースがあります。
特に民間企業が運営する退職代行の場合、法的な交渉権限がないため、このような事態に直面しやすくなります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
やり取りを拒否された場合であっても、内容証明郵便によって退職届の送付を行い、退職手続きを進めることは可能です。
ただし、退職はゴールではなく転職へのスタートラインだと考えると、揉めている時間が勿体ないと感じるでしょう。
退職代行とのやり取りを拒否されるリスクが予想される場合は、弁護士が運営する退職代行への依頼を検討するといいでしょう。


会社から直接連絡が来て精神的ストレスがかかる
退職代行を利用しているにもかかわらず、会社から直接連絡が来てしまうケースがあります。
退職代行を活用することで、基本的に会社とのやり取りを全て代行してもらえるものの、会社から電話やメールが直接くることを必ず止められるわけではありません。
もしも会社から直接連絡が入った場合は、留守電やメールの内容を確認し、折り返しや返信はせずに、退職代行業者に共有した上で対応方法を検討することがオススメです。
その際、退職に関する事務的な手続きにおいて必要な連絡が入る可能性もあるため、着信やメールの受信拒否などは控えた方がいいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
全ての連絡は退職代行業者を通すよう伝えることで、ある程度は避けられるものの、会社からの直接連絡が来る可能性はゼロではありません。
心理的につらいと感じる場合もありますが、まずは冷静に内容を確認し、代行業者に伝えるようにしましょう。


成功報酬として想定外の追加料金を請求される
退職代行の中には、基本料金に加えて追加料金が必要なサービスもあります。そのため、退職代行の完了時に、想定していたより高額な請求に驚いてしまう人もいるようです。
退職代行に必要な料金を正確に把握するためには、以下のポイントを必ずチェックしておきましょう。
- 追加費用が発生する条件を確認する
- 成功報酬の有無と料金を確認する
退職代行の料金は3~7万円程度が相場となっており、決して高くはありません。
ですが、退職後の転職活動やキャリアアップのための学びなどに使える費用を確保するためにも、利用料金は正確に把握しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
追加費用の一例として、残業代や退職金の支払いを会社が拒否した場合に、弁護士などの専門家の交渉によって支払い請求に成功した場合に、別途報酬が必要なケースがあります。
(例:回収額の20~30%)
非弁行為を行う違法な退職代行に依頼してしまった
民間企業が運営する退職代行では、会社との交渉や法的な助言を行うことはできません。これらは弁護士法で禁止された「非弁行為」に該当するためです。ですが、中には弁護士でもないのに法的な問題に対する交渉をしてしまう違法業者が存在します。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行は許認可などは必要なく、だれでも始められる事業です。
そのため、適法に代行業務を行う会社だけではなく、中には違法な非弁行為を行う業者も存在するため、注意しておきましょう。


懲戒解雇すると脅される
退職代行の利用を理由に懲戒解雇を示唆されるケースがあります。
しかし、退職手続きの一環として退職代行を利用することは、懲戒解雇の正当な理由とはなりません。
懲戒解雇は労使間における最も重いペナルティです。社内の秩序を著しく乱した労働者に課せられるもので、仕事の上の地位を利用した犯罪や、会社の地位を害する犯罪等を犯した場合に該当します。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行を使ったことを理由に懲戒解雇を仄めかすような会社に勤めている場合は、事態を早期に収束させるためにも、法的対応が可能な弁護士が運営する退職代行業者に相談して辞めることをおすすめします。


退職代行でトラブルが発生する主な原因
退職代行サービスを利用する際のトラブルには、いくつかの典型的な原因があります。
退職代行を利用におけるトラブルを未然に防ぐために、ここでは、トラブルの原因になりやすい以下の点について詳しく解説していきます。
それぞれ詳しく解説していきます。
退職代行サービスの選び方を誤っている
適切な退職代行サービスを選べなかったことが、トラブル発生の原因の一つといえます。トラブルにつながる退職代行サービスの見落としがちなポイントは以下の通りです。
- 運営主体の確認不足
- サービス内容と法的権限の把握不足
- 料金体系の理解不足
特に「運営主体の確認」は非常に重要で、退職に伴って代行業者に「交渉」を依頼したい場合は、弁護士もしくは団体交渉権を持つ労働組合に依頼する必要があります。また、損害賠償などの訴訟に法的対応をするためには、弁護士の退職代行に依頼することが重要になります。
退職、および代行業者の利用に伴って発生しそうなトラブルと、その対応に必要な依頼先についてはしっかり把握しておいた方がいいでしょう。
>退職代行でトラブルを起こさないためのサービスの選び方は本記事のこちらで解説
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行サービスは
・民間事業者
・労働組合
・弁護士
の3種類があり、それぞれ対応可能な範囲が異なるため、注意が必要です。
退職に伴って揉めそうな会社に勤めている場合は、あらゆる法的対応が可能な弁護士への依頼を検討するといいでしょう。




事前確認や準備が不十分である
退職代行サービスを利用する際、多くのトラブルは、利用者側の準備不足から発生します。
退職代行サービスを利用する前に、就業規則の確認や必要書類の準備、会社備品の確認や引継ぎの準備などを怠ると、円滑な退職手続きの妨げとなります。
そのため、退職代行を使ってスムーズに会社を辞めるためには、最低限の準備をしたうえで臨むことがおすすめです。
>退職代行でトラブルを起こさないための準備は本記事のこちらで詳細解説
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
もちろん、「もう会社に行きたくない!」という気持ちから衝動的に退職代行に依頼したい気持ちになることもあります。
ですが、ほんの少しの準備で割けられるトラブルもあるため、余裕があれば、退職に必要な確認・準備をしたうえで代行業者に依頼することがオススメです。
退職代行に依頼して、結果的にさらに疲弊しないためにも、しっかり準備をしておきましょう。
会社側の対応に問題がある
時として、会社側の不適切な対応がトラブルを引き起こす原因となります。
このような場合、法律に基づく適切な対応が必要となりますが、利用している退職代行サービスに法的対応の権限がないと、スムーズな問題解決が困難になり、最終的に別途弁護士に相談しなければならない可能性があります。
そのため、会社側が使用者としての権力を乱用する恐れがある場合は、最初から弁護士が運営する退職代行に依頼を検討するといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行経由で辞職を通達後、引継ぎを要求されたり、仕事に関する大量の質問メールが届く場合もあります。
ですが、業務内容によっては引き継ぎに関しては直接の対応が不要なケースも多いため、まずは代行業者に相談し、粛々と進めるといいでしょう。




退職代行のトラブルを防ぐ4つの対策
退職代行サービスを利用する際のトラブルは、適切な対策を講じることで大幅に減らすことができます。ここでは、トラブルを防ぎための以下の対策について、具体的に解説していきます。
信頼できる代行業者を見極めるポイントを押さえる
退職代行業者の信頼性を見極めることは、トラブル防止の第一歩です。退職代行を選ぶ際は、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。
- 運営会社の実績と評判(過去の成功事例や口コミ評価など)
- 料金体系の透明性(追加料金の有無や支払い条件など)
- アフターフォローの充実度(相談対応や返金保証制度の有無など)
特に、口コミなどのチェックは公式HP以外の外部サービス等に掲載されるものも参考にしたうえで、依頼する代行業者を検討するようにしましょう。
交渉が必要な場合は弁護士法人が運営する退職代行へ依頼する
会社との法的交渉が必要になる可能性が高い場合、弁護士法人が運営する退職代行サービスの利用を強く推奨します。
法的な知識と交渉権限を持つ弁護士が対応することで、以下のようなメリットがあります。
- 法的根拠に基づいた適切な交渉が可能
- 会社側の不当な要求を効果的に排除できる
- 必要に応じて法的手続きへの移行がスムーズ
労働組合の退職代行でも、有給休暇の取得や退職日調整などの交渉を行うことは可能ですが、損害賠償請求や懲戒解雇をすると言われた際に、適切な対応ができません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
弁護士の退職代行なら非弁行為にならないので安心して利用可能です。
未払いの残業代の請求をしたい場合や、損害賠償の仄めかしがある場合は、まずは弁護士の退職代行サービスへ相談してみるといいでしょう。






退職に必要な準備を事前に整える
退職をスムーズに進めるためには、事前の準備が不可欠です。具体的には、有給休暇の残日数の確認、退職金規定の確認、会社備品の整理など、必要な情報や書類を整理しておくことが重要です。
特に重要な準備事項は以下の通りです。
- 就業規則や労働契約書の内容を確認
- 会社貸与品のリストアップと返却準備
- 私物の整理
上記の事前準備をすることで、退職代行業者が会社に連絡した際の情報の食い違いを防ぎ、スムーズな退職を実現可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
突発的に代行業者に相談することも悪いことではありません。ですが、退職手続きを進めるうえで、上記を確認する必要がでる場合があることを事前に認識しておきましょう。
>退職代行でトラブルを起こさないための準備は本記事のこちらで詳細解説
法的な権利を正しく理解しておく
代行業者を使って退職する際には、労働者としての法的権利を正しく理解しておくことで、不当な要求や圧力から自身を守ることができます。
また、有給休暇の取得や未払い賃金の請求なども、法律で保護された権利であり、労働者はこれを行使することが可能です。
これらの知識を持っておくことで、会社側の不当な要求に対して適切に対応することができるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
有期雇用を結んでいる契約社員やパートの場合であっても、やむを得ない理由がある場合等はいつでも退職することが可能です。
>契約社員の退職代行利用についてはこちらで解説


退職代行でトラブルを起こさないための準備
退職代行サービスを利用する前に、必要な準備を整えることでトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、以下の具体的な準備事項について詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社を退職するのは、他でもない自分自身です。
退職代行に依頼して全てお任せではなく、トラブルを避けるためにも、必要な準備をして臨むといいでしょう。
残りの有給休暇日数を正確に把握する
退職代行を利用し、即日退職をするためには有給休暇の日数を正確に把握する必要があります。
なぜなら、退職の申し出以降に出勤をしない場合は、正式な退職日までの期間に有休を充てる必要があるためです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
勤めている会社によっては、「うちは有給休暇はない」と言われ、在職中に一度も有給を使ったことがない人もいます。
ですが、これは誤りで、6か月以上の勤務期間(出勤率8割以上)がある人は、雇用形態を問わず全員に有給休暇が付与されています。
参照:e-GOV法令検索「労働基準法第39条(年次有給休暇)」
有給休暇はその名の通り、給与をもらいつつとれるお休みです。
転職活動や休職期間を有意義にするために、退職時には必ず取得するようにしましょう。




退職金の支給条件を就業規則で確認する
退職代行を利用する際は、事前に就業規則の記載された退職金の支給条件を確認することがおすすめです。
働いている間はあまり気にしたことが無いかもしれませんが、退職金の制度がある企業は全体の74.9%となっており、自身の働いている会社でも支給を受けられる可能性があります。
参照:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査結果の概況(退職給付(一時金・年金)制度)」
そのため、就業規則の退職に関する規定について、以下の点を事前に確認しておきましょう。
- 退職金の支給対象者の条件
- 退職金の算定方法
- 支給時期や支払方法
- 不支給となる条件
ただし、退職金(退職一時金)を受け取るためには一定以上の勤続年数を条件としている企業が多く、中央労働委員会の調査では、自己都合退職の場合は49.3%の企業が「3年以上」の勤続が必要としています。
| 退職一時金の受け取りに必要な 勤続年数 | 自己都合の場合 | 会社都合の場合 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 4.3% | 55.1% |
| 1年以上2年未満 | 28.3% | 29.7% |
| 2年以上3年未満 | 15.2% | 5.1% |
| 3年以上 | 49.3% | 8.7% |
n数=138
退職後の生活のためにも、退職金を受け取れるかどうかは重要なポイントになるので、事前に確認しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職金制度は主に「退職一時金」「退職年金制度」の2種類があります。
退職年金制度の場合は、退職後に手続きが必要なので、必ず確認しておきましょう。
会社の備品と私物を整理して準備する
会社の備品と私物の整理は、退職時のトラブルを防ぐ重要なポイントです。会社から貸与されているものは全て返却する必要があり、紛失や破損があった場合はトラブルの原因となります。
特に以下のポイントについては事前に確認と準備を行いましょう。
- 社員証
- セキュリティカード
- 制服や作業着
- パソコンやスマートフォンなどの電子機器
これらの備品は、退職日までに会社に返却できるよう、事前に準備しておくことが重要です。特に、セキュリティカードの返却が漏れると、後で大きなトラブルに発展しかねないため、必ず確認しておきましょう。
また、デスクやロッカーに置いてある私物については、できるだけ早めに持ち帰るようにし、退職日直前に慌てることのないよう計画的に整理を進めましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
貸与物ではないですが、退職に伴って健康保険証も返却が必要なので、手元に用意しておきましょう。
退職代行でトラブルを起こさないためのサービスの選び方
退職代行を利用する際は、適切なサービスを選ぶことで、多くのトラブルを回避することができます。
ここでは、サービス選びの重要なポイントについて解説していきます。
サービスの選び方
上記について、それぞれ詳しく解説していきます。


法的に対応可能な範囲を確認する
退職代行を選ぶ際には、法的に対応可能な範囲を確認することが非常に重要です。
退職代行に当たって依頼したい内容によっては、法律上、民間業者が対応できないものもあるため、自身が会社を辞めるにあたって必要な手続きやリスクを予想し、依頼するサービスを選ぶ必要があります。
運営主体による対応可能範囲は以下の通りです。
- 弁護士による退職代行
-
退職に伴う各種交渉に加え、法的対応、交渉、訴訟対応まで可能。
- 労働組合による退職代行
-
団体交渉権による退職条件の交渉が可能。
- 民間企業による退職代行
-
基本的にメッセンジャーとして退職意思の伝達のみ可能。
※事業者によっては、法的対応が必要になった場合に、各外部団体と連携するサービスも有り
上記を見ると分かるように、弁護士の退職代行であれば非弁行為に該当する恐れがなく、安心・確実に退職交渉を代行することが可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職の意思を伝達するのみであれば、民間の退職代行会社でも問題ありません。
ですが、法的根拠に基づく交渉が必要になりそうな場合は、料金が高くても弁護士の退職代行に依頼する方が無難といえます。


料金体系を細かくチェックする
退職代行の利用時に、「想定外の料金を請求された!」とならないように、事前に料金体系を細かくチェックすることが重要になります。依頼時には、以下の点について、特に注意深く確認する必要があります。
- 基本料金に含まれるサービスの範囲
- 追加オプションの有無と料金
- キャンセル時の取り扱い
- 退職できなかった場合の返金制度の有無
事前に料金体系を詳しく確認し、不明な点があれば必ず事前に問い合わせるようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行の料金は3~7万円が相場で、民間事業者の方が安く、弁護士へ依頼する場合は高くなる傾向があります。
そもそも、退職は自分で無料で出来ることを考えると、人によっては高く感じるかもしれません。
ですが、退職代行を検討している人の多くは、自分で退職することが困難に感じており、代行を依頼することで精神的苦痛や時間のロスを軽減したいと感じているハズです。
そのため退職代行の料金を考える際は、「困難の代行にどこまで払えるか?」を基準に、依頼する退職代行業者を選定するといいでしょう。




実績と口コミを詳しく確認する
退職代行サービスの信頼性を判断する上で、これまでの実績と口コミは重要な判断材料となります。
特に、否定的な口コミについては、その内容と会社の対応を確認することで、サービスの質をより正確に判断することができます。


退職代行のトラブルに関するまとめ
退職代行サービスは、適切に利用することで円滑な退職を実現できる有効な手段です。
しかし、利用の際には、様々なトラブルのリスクも存在することを理解しておく必要があります。
本記事で解説してきたトラブル事例や対応策を踏まえて、退職代行を活用することで、多くのトラブルを回避することができます。
退職代行サービスは、あくまでも退職をサポートするためのツールのひとつです。自身の権利と義務を正しく理解し、適切なサービスを選択することで、より円滑な退職を実現することができるでしょう。




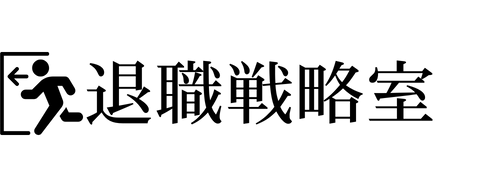
.png)





