退職したい時の言い方8つのコツ!辞める理由の伝え方や避けるべき表現も解説
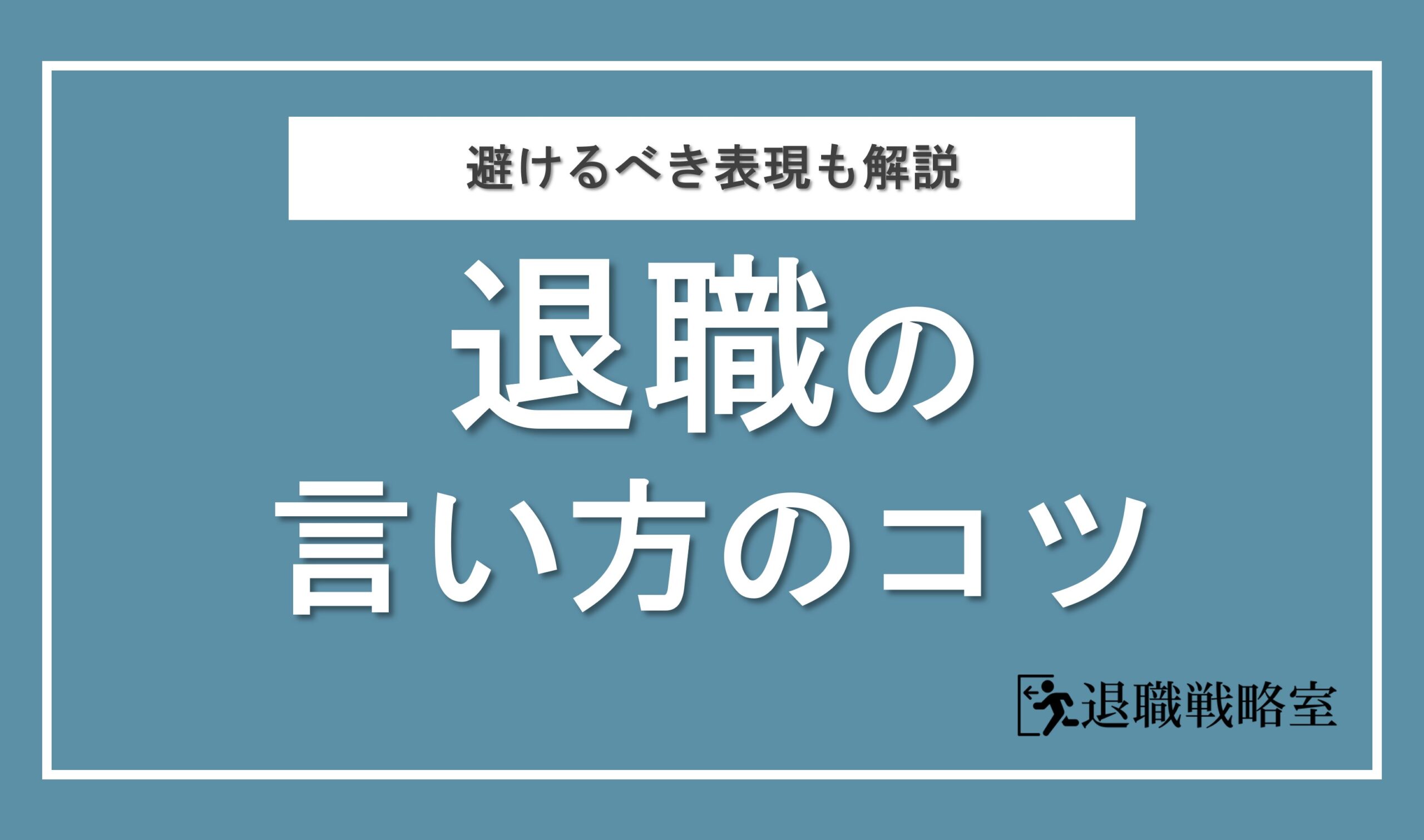
退職を考えていても、「どのように切り出せばいいのか」「引き留められたらどうしよう」と悩んでしまい、なかなか言い出せない人が多いようです。特に、仕事でお世話になった上司に対しては、伝え方に悩む場合もあるでしょう。
この記事では、退職をスムーズにする言い方のポイントやコツ、シチュエーションに応じた具体的な退職理由の伝え方まで解説します。
現職の引き留めを避けて、円満退職を実現するための方法を徹底解説するので、是非ご確認ください。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


退職の言い方の3つのポイント
退職を伝える際は、会社との良好な関係を維持しながら、自身の意思を明確に伝えることが重要です。突然の申し出となる場合でも、適切な伝え方を心がけることで、円満な退職につながります。
具体的な退職の伝え方のポイントは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
お詫びの言葉から切り出して退職意思を伝える
退職を上司に伝える際は、「突然のご報告で恐縮ですが」など、まずはお詫びの言葉から始めることで、相手への配慮を示すことができます。これまでお世話になった感謝の気持ちを込めながら、退職の意思を明確に伝えましょう。
単に退職を通告するのではなく、丁寧な姿勢で臨むことで、その後の手続きもスムーズに進めやすくなるでしょう。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)これまでの感謝やお詫びとともに退職を伝えることで、角を立てずに退職をすることが可能です。
逆に、退職の際に礼儀を尽くせなかった場合、上司による感情的な引き止め等のトラブルを招く可能性があるため、注意しておきましょう。
一方的な通告ではなく丁寧な説明を心がける
退職の意思を伝える際は、一方的な通告ではなく、相手の立場に立った丁寧な説明を心がけましょう。
具体的には、以下のポイントを意識することで、より円滑なコミュニケーションが可能となります。
- 具体的な退職希望時期
- 退職を決意した理由を簡潔に説明
- 引き継ぎに関する具体案
- 会社への感謝の意
この時点で退職日を記載した退職届を出すことも法律上は可能ですが、退職日について会社側と調整して円満退職を目指す場合は、まずは上記の内容を直属の上司に伝えるようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
できるだけ早く退職したい場合や、職場環境に問題がある場合を除けば、まずは退職の意思を伝え、退職日を合意した時点で退職届を出すようにしましょう。
ただし、転職先が既に決まっている場合や、有給休暇が残っている場合は早めに退職日を決める必要があるため、注意しておきましょう。
引き留めを避けるために退職の意志が固いことを伝える
退職を上司に伝える際は、「退職についてご相談したい」といった曖昧な言い方は避け、「退職を決意いたしました」など、意思が固いことを示す表現を使いましょう。
ただし、円満退職を目指すなら、強引な印象を与えないように「退職時期については相談させていただければ」と柔軟な姿勢も示すことが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職意思が固いことを伝えることで、不要な引き止めを最小限に止め、退職日の調整や引き継ぎ方法などの建設的な相談を早期に進めることが可能です。


退職をスムーズにする言い方8つのコツ
退職を円満かつスムーズに進めるためには、適切なタイミングと伝え方が重要です。
退職をスムーズにする具体的な言い方は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
退職の1~3か月前を目安に伝える
法律上、正社員の場合は2週間前の申し出による退職が可能ですが、円満な退職を目指すなら退職日の1~3ヶ月前には伝えることがおすすめします。
これにより、会社側の引き継ぎ準備や後任者の手配にも余裕が生まれ、あなたの退職後も業務が滞りなく進められます。
また、可能な範囲で繁忙期や重要プロジェクトの最中は避けるなど、タイミングにも配慮できると、さらに望ましいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社によっては1か月を超える退職申し出期間を就業規則に記載している場合がありますが、正社員(無期雇用社員)の場合、法律で定められた2週間を大幅に超える期間については無効になります。
そのため、就業規則に縛られ過ぎず、転職先に悪影響が出ないように退職スケジュールを調整することが望ましいでしょう。
また、退職日は、次の職場の出勤日と、残っている有給休暇を全て消化することを前提に調整するようにしましょう。




上司の予定を確認して面談時間を取る
退職をスムーズにする言い方のコツのひとつに、退職を伝えるタイミングと場所が挙げられます。
社内に不確実な噂が広まって混乱することを防ぐためにも、退職の意思を伝える際は、必ず上司と1対1で話せる時間と場所を確保しましょう。
具体的には、以下のポイントを押さえて上司に退職を伝えるようにしましょう。
- メールで「ご相談したいことがございます」と伝えて時間を取る
- 人目につかない会議室などを予約しておく
- 30分程度の時間枠を確保する
- 忙しい時間帯は避ける
上記に従って上司の時間を確保することで、周囲に配慮した退職の言い方が可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職に関する話は、周囲に「退職理由が気になる」「引き継ぎや後任者はどうなるのか?」等の疑問を生むため、職場全体に伝えるタイミングはコントロールする必要があります。
そのため、様々な人がいるオフィスや職場で、いきなり「退職したいです」と伝えるのではなく、会議室や個室で伝えるようにしましょう。


退職理由を簡潔に説明する
退職理由は、会社や上司への不満を口にせず、前向きな表現で簡潔に説明することがおすすめです。
もしも本当の退職理由が職場環境や人間関係、仕事内容のせいだったとしても、それをストレートに伝えると「改善するから残ってほしい」という引き止めを受ける可能性が高くなります。
そのため、転職先が既に決まっている場合や、退職の意思が固い場合は、不要な引き止めを避けるためにも「前向きな退職理由」のみを伝えるようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職の言い方を誤ると、不要な引き止め交渉が発生し、自分も会社側(上司)も疲弊してしまいます。
結果的に退職日が遅くなってしまえば、転職先にも悪影響が発生する可能性があります。
退職日や引き継ぎに関する建設的な話し合いを進めるためにも、退職理由は簡潔かつ前向きな理由を伝えることがおすすめです。


引き継ぎ計画を具体的に提示する
円満な退職のカギとなるのが、具体的な引き継ぎ計画の提示です。
退職を伝える時点で詳細な引き継ぎ計画が完成している必要はありませんが、すぐに用意できる範囲で情報をまとめ、退職と共に伝えるといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
この時点で、会社側から「後任者がいないから退職は待って欲しい」と要請される可能性があります。
ですが、採用および異動による後任者の確保は会社側で行う役割のため、後任者が見つからないという理由で退職予定日を引き延ばさないように注意しておきましょう。


最終出社日の希望を伝える
希望する最終出社日は、会社規定や業務の状況を考慮した上で提案しましょう。
また、有給休暇が残っている場合は、全て消化することを前提に最終出社日を調整するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
法律上、正社員(無期雇用社員)は2週間前に申し出をすれば退職することが可能です。
参照:e-Gov法令検索「民法第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
退職日や最終出社日の交渉に当たっては、就業規則に記載された退職申し出期間を理由に引き延ばされる可能性がありますが、法律を大きく超える規定については効力を持ちません。
上記を前提に、建設的に最終出社日および退職日の調整を進めるようにしましょう。


上司からの質問に誠実に回答する
退職の意思を伝えた後、上司から様々な質問を受けることがあります。
ただし、必要以上の情報は開示せず、適度な距離感を保つことも大切です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
特に、転職先が競合他社や取引先に該当する場合は、伝える情報は慎重に選ぶ必要があります。
感謝の気持ちを表現する
退職の際には、その会社で得られた経験やスキル、これまでの指導やサポートに対する感謝の気持ちを必ず伝えましょう。
具体的なエピソードを交えながら、言葉で感謝を示すことで、最後まで良好な関係を維持することができます。
また、今後のキャリアにおいても、良好な人間関係を築けていたことは大きな財産となります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
打算的ではありますが、退職時に良い印象を残すことで、今後のキャリアを応援してもらう下地を作ることが可能です。
具体的には、将来の取引先の確保や、リファレンスチェックが必要な転職をする際に役立つ人脈を得ることができます。
キャリアの不確実性が高い時代だからこそ、同じ職場で働いてきた縁をないがしろにしないように注意しておきましょう。
書面で退職届を提出する
退職の意思を口頭で伝え、退職日の合意ができた後は、正式な手続きとして「退職届」の提出が必要です。
会社指定の様式がある場合はそれに従い、なければ一般的な形式で退職届を作成します。提出時期や提出先については上司や人事部に確認し、遅滞なく進めていきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
もしも、在職を強要され、退職届を受け取ってもらえない状況に陥った場合は、退職届を内容証明郵便(※)で送るようにしましょう。
※郵送物の内容と送付日、送付先を証明してもらえるサービス。




退職承認後の具体的な流れ
退職が承認され、最終出社日や退職日が決まれば、引き継ぎや有給休暇の取得をしなければなりません。
円滑な退職および引き継ぎのために、承認後から退職日までの具体的な流れと注意点について、以下の通り解説していきます。
退職日と最終出社日の決定
退職日は会社側と相談の上で正式に決定します。
この際、業務の引き継ぎ期間や有給休暇の消化、会社の繁忙期などを考慮に入れる必要があります。決定した退職日は人事部門にも共有され、この日程を基準に各種手続きが進められていきます。
引き継ぎのスケジュールと資料を作成
退職に伴う、具体的な引き継ぎ計画を立案します。
以下のポイントを含めた詳細な引き継ぎスケジュールを作成しましょう。
- 各担当業務の完了予定時期の設定
- 後任者への引き継ぎ日程の調整
- 必要な資料やマニュアル作成
- 取引先への挨拶回りのスケジュール
業務と顧客の引き継ぎを実施
作成したスケジュールに沿って、実際の引き継ぎを進めます。
円滑な引き継ぎのためには、日常業務の手順や注意点、取引先との関係性など、細かな情報まで漏れなく伝えることが重要です。
特に重要な案件や継続的なプロジェクトについては、後任者が混乱しないよう丁寧な説明を心がけましょう。
最終出社日に同僚や上司へ挨拶
最終出社日には、これまでお世話になった方々へ順序立てて挨拶をします。
まずは上司、そして他部署の関係者、同じ部署の同僚に感謝の言葉を伝え、今後も良好な関係を維持できるよう心がけましょう。
会社貸与物や備品を返却
退職時には会社から貸与されていた物品をすべて返却する必要があります。
社員証や入館証、パソコンやスマホなどの電子機器、各種アクセス権限の解除なども忘れずに対応しましょう。
個人のデータと会社のデータをしっかりと切り分け、機密情報の取り扱いには特に注意が必要です。
残っている有給休暇を取得
有給休暇が残っている場合は、会社の規定に従って取得または買い取りの手続きを行います。
有給休暇の取得については、業務の引き継ぎに支障が出ないよう、計画的に調整することが重要です。
退職日以降に年金や健康保険の切り替え
退職後の社会保険の手続きは速やかに行う必要があります。
退職後、すぐに次の職場で働く場合は新しい会社で手続きを行い、空白期間が生まれる場合は国民健康保険に切り替えましょう。
また、次の就職先が決まっていない場合は国民年金への切り替え手続きを行いましょう。
退職を切り出す際の事前準備
退職の意思を伝える前に、必要な情報の確認と準備を万全に整えておくことで、その後の手続きをスムーズに進めることができます。また、会社側との交渉に備えて、自分の希望や条件を整理しておくことも重要です。
ここでは、退職を切り出す際に事前に準備しておくべき以下の事項について詳しく解説していきます。
退職予告期間を確認する
退職を切り出す際は、事前に就業規則に定められている退職予告期間を確認しておきましょう。
この期間を把握することで、退職の申し出のタイミングを適切に計画することができます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
前述したように、法律で定められた2週間を超える退職予告期間は法律上効力がありません(正社員の場合)。
そのため、法律上の制限と自社の就業規則を把握したうえで、適切な退職日を調整することが可能になるでしょう。
希望の退職日と延長可能な日時を決めておく
退職を切り出す際には、以下の要素を考慮しながら、事前に具体的な退職時期を検討しましょう。
- 会社の繁忙期を避けた日程
- 引き継ぎに必要な期間の見積もり
- 転職先がある場合は入社日との調整
- 延長を求められた場合の対応可能期間
転職先が決まっている場合は、入社予定日を変更不可のデッドラインとしたうえで、引き継ぎと有給休暇の消化が可能なスケジュールを立てるようにするといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
法律上、正社員は申し出から最短2週間で退職することが可能ですが、円満退社を目指すなら、最短の退職日が必ずしも最善の選択肢とは限りません。
また、会社側の要求を全て鵜呑みにする必要もなく、転職先で活躍する為の準備に時間が必要であれば、必要な休暇を確保する必要があります。
会社側と自分の生活、転職先の入社までにやるべき準備を考慮し、最適な退職日を会社側とすり合わせるようにしましょう。
有給休暇の消化予定を決める
退職を切り出す際は、残存している有給休暇の日数を確認し、どのように消化するか事前に計画を立ておきましょう。
有休休暇の残日数が多い場合、引き継ぎや退職日のスケジュールに大きな影響を与える可能性があるため、事前に計画を立てる必要があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
稀に「退職する社員に有給休暇は取得させない」と主張するブラック企業も存在しますが、有給休暇の取得は法律で定められた権利であり、退職時に会社側がこれを拒否することは出来ません。
また、時季変更権を行使して有給休暇を取得させないようにする場合もありますが、退職日以降に休暇を取ることは出来ないため、注意しておきましょう。




退職金の取得条件を確認しておく
退職金制度がある場合、その受給条件や金額の計算方法を事前に確認します。
また、確定拠出年金などの企業年金がある場合は、その取り扱いについても確認しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社によっては退職理由が「会社都合退職」か「自己都合退職」かで退職金の金額が異なる場合もあります。
退職する際の理由によっては、自分から退職を申し出ても「会社都合退職」にできる場合があるため、必ず確認しておきましょう。
引き継ぎ資料や方法を事前に整理する
退職を申し出る際は、事前に現在担当している業務の棚卸しを行い、引き継ぎに必要な情報を整理しておくことがおすすめです。
日常的な業務の手順書や、進行中のプロジェクトの状況、取引先との関係性など、後任者が必要とする情報を漏れなくリストアップすることで、円滑な引き継ぎの計画を立てることが可能になります。
具体的には、以下のような資料を事前に準備しておくと効果的です。
- 定型業務の実施手順書
- 業務上の重要な連絡先リスト
- 進行中案件の状況整理表
- システムやツールの利用マニュアル
これらの準備を整えることで、実際に退職を申し出た後の手続きや引き継ぎをスムーズに進めることができます。
また、会社側からの質問や確認事項にも適切に対応できる状態を整えておくことで、より円満な退職につなげられるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ただし、引き継ぎの準備のせいで、退職の申し出が遅くなるのは避けるべきです。
会社側としては、退職の意向有無は何よりも早く把握したい人事情報のため、退職を切り出すのが遅くなるくらいなら、引き継ぎ資料の準備は後回しにしましょう。
状況別の具体的な退職理由の伝え方
退職理由は状況によって適切な伝え方が異なります。会社や上司への配慮を忘れず、かつ自分の意思をしっかりと伝えられる表現を選ぶことが重要になります。
ここでは、よくある退職理由別の効果的な伝え方を紹介していきます。
転職のために退職する場合の前向きな伝え方
転職をすることを退職理由とする場合は、現在の職場での経験に感謝しつつ、キャリアアップへの意欲を示す形で伝えることが効果的です。
具体的な転職先については、以下のような方針で説明することをおすすめします。
- 業界について聞かれた場合は大まかに答える
- 具体的な企業名は必要以上に明かさない
- 現職場での学びを活かせる点を強調する
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
上司との距離感や信頼関係によって伝えるべき情報を事前に検討するようにしましょう。
家庭の事情で退職する場合の説明方法
結婚、出産、介護など家庭の事情による退職の場合は、状況を簡潔に説明することが重要です。
会社によっては両立支援制度の提案を受ける可能性もあるため、退職を決意する前に制度の確認と自身の意向を整理しておくことが大切です。


責任ある立場から退職する場合の伝え方
管理職や重要なプロジェクトリーダーなど、責任ある立場からの退職は、より慎重な対応が必要です。
特に留意すべき点は下記の通りです。
- 現在の職責を全うする意思を示す
- 具体的な引き継ぎ計画を提示する
- チームへの影響を最小限に抑える方策を説明する
退職理由の説明では、前向きな表現を使いつつ、会社への感謝の意も忘れずに伝えることで、より良好な関係を維持することができます。
また、引き継ぎや今後の対応について具体的な提案を示すことで、会社側の不安を軽減することにもつながるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
マネジメント職やプロジェクトのリーダーなどを担っている場合は、退職する際の言い方に、より配慮が必要です。
状況に応じて適切な表現を選び、誠意を持って説明することを心がけましょう。
退職の言い方で絶対に避けるべき表現
退職の意思を伝える際、適切でない表現を使用してしまうと、その後の手続きや人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。円満な退職を実現するためには、注意すべき表現や態度があるため、注意が必要です。
ここでは、退職時に使用を避けるべき以下の表現とその理由について詳しく説明していきます。
会社や上司の批判を含む発言を避ける
たとえ退職の背景に仕事に対する不満があったとしても、会社や上司への批判的な発言は避けるべきです。
「待遇が悪い」「評価が不当」といった否定的な表現は、その場の雰囲気を悪化させるだけでなく、将来的な人脈形成にも悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、以下のような表現は特に注意が必要です。
- 給与や待遇への不満
- 人事評価への批判
- 職場の人間関係に関する愚痴
- 会社の経営方針への否定的意見
退職時には、自分の将来のキャリアのことを第一に考えて、慎重に行動するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
よかれと思って会社への不満や批判をした場合であっても、余計な悪感情を招きかねないため注意が必要です。
退職後の関係性に影響するため、極力会社への不満を退職時に伝えるのは避けた方が無難といえるでしょう。
曖昧な表現で誤解を招かない
退職を伝える際に、「退職を考えています」「できれば辞めたいのですが」といった曖昧な表現は、退職の意思が固まっていないと誤解を招き、不必要な引き留めの原因となります。
そのため、退職の意思を伝える際は、明確で具体的な表現を使用することが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
まだ引き留められる、と判断されると引き止め交渉が長引く可能性があります。
結果的に、退職希望者は精神的に疲弊し、会社側も人員の確保(採用・異動)が進められず、どちらも損な状況に陥るため、注意しておきましょう。
感情的な言葉を使用しない
退職の意思を伝える際は、冷静さを保ち、感情的な表現を避けることが重要です。
たとえ職場での経験に不満があったとしても、「もう限界です」「耐えられません」といった感情的な言葉は使用すべきではありません。代わりに、「新たなキャリアにチャレンジしたい」「自己成長のため」など、前向きな表現を選択することで、建設的な対話が可能となります。
これらの表現を避けることで、退職後も良好な関係を維持することができ、将来的なキャリアにおいてもプラスとなります。退職時の会話は、その後の人生に大きな影響を与える可能性があることを常に意識し、慎重に言葉を選ぶよう心がけましょう。
特に感情が高ぶっている場合は、一呼吸置いて冷静になってから話をすることをお勧めします。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
長く働いた職場や辛い思いをした職場の場合、退職時に感情的になるのは極めて自然なことです。
ですが、社会人として建設的な対話をするためには、出来る限り前向きな表現を使うことが望ましいでしょう。


退職を伝えた上司の反応別の対応方法
退職の意思を伝えた後、上司からは様々な反応が予想されます。突然の退職の申し出に動揺したり、引き留めを試みたりするケースも少なくありません。
そこで、ここからは想定される上司の反応と、それぞれの状況における適切な対応方法について以下の通り解説していきます。
引き留めを受けた場合の返答例を準備する
退職を伝えた際、多くの場合において上司は最初に引き留めを試みるはずです。
具体的には、退職理由を確認しつつ、「待遇改善を検討する」「異動も考えられる」といった提案を受けることがあります。
このような退職引き止めを受けた場合、以下のポイントを意識した対応を準備しておくことが重要です。
- 退職を決意した背景にある理由を簡潔に説明する
- 丁寧な言葉で感謝しつつ、断る
- 具体的な対案に関する即答を避ける
引き止められた場合の対応をあらかじめ考えておくことで、よりスムーズに退職を実現することができるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を伝えた際に、パワハラとも受け取れる高圧的な引き止めを受けたり、退職願・退職届の受け取りを拒否される場合は、退職代行サービスや労働局の総合労働相談コーナーに相談するようにしましょう。
参照:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」




再考を促された際の対応を決めておく
「もう少し考え直してほしい」「急な話で判断できない」といった形で、時間を置くことを提案されるケースもあります。この場合、安易に同意せず、「十分に考えた上での決断です」と、意思の固さを伝えることが重要です。
ただし、その際の言い方としては、上司の立場や心情にも配慮しながら、建設的な対話を心がけるようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
特に、転職先が既に決まっている場合は、再考しても双方にメリットが無い構成が高いといえるでしょう。
ただし、転職先がまだ決まっておらず、現職に残るか悩んでいる場合等は、キャリアバディなどの有料キャリア相談サービスを利用して、専門家のアドバイスをもらうことがおすすめです。


昇進や待遇改善の提案への返し方を考える
退職の意思を伝えた際、退職を引き止める材料として昇進や給与アップなどの条件を提示されることがあります。
このような提案に対しては、感謝の意を示しつつも、金銭的な条件だけでなく、キャリアの方向性や自己実現といった観点から決断したことを説明します。
慎重に検討した末の決断であることを示しつつ、会社や上司への敬意を失わない対応を心がけることで、その後の退職手続きもスムーズに進めることができます。
また、将来的な人脈形成の観点からも、最後まで誠実な態度を保つことが重要です。上司との対話は、退職後の関係性にも大きく影響する重要な機会であることを忘れずに対応しましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を申し出た際に打診される昇進や待遇改善の提案は、実現する保証がありません。
そのため、この提案に乗って転職先の内定を蹴るのは、非常にリスクが高い選択肢といえるでしょう。
上司としては、期間中に退職されると直属の上司である自分の評価が下がる可能性があるため、一時的な引き止めのために待遇改善を申し出る場合があります。
そのため、もしも昇進や待遇改善されれば現職に残ることを検討する場合は、その実現可能性や時期についても必ず確認するようにしましょう。


退職を周囲に伝える際の適切なタイミング
退職の意思を周囲に伝える際は、適切なタイミングと順序を守ることが重要です。早すぎると職場の雰囲気を損ねる可能性があり、遅すぎると周囲への配慮を欠くことになるため、注意が必要です。
ここでは、家族や同僚、取引先それぞれに対する効果的な退職報告のタイミングと方法について説明していきます。
家族には転職活動開始時点で相談する
家族、特に配偶者には、退職を決意する前の転職活動開始時点で相談することをお勧めします。退職は生活設計に大きく関わる決断であるため、以下のような点について十分な話し合いが必要です。
- 収入の変化と家計への影響
- 勤務地や勤務時間の変更可能性
- 転職後のキャリアビジョン
転職活動を行う際に家族の理解と協力を得られることで、より明確なライフキャリアプランの設計が可能になります。
いきなり転職・退職を伝えるのではなく、事前に考えやキャリア設計を共有するようにしておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
転職を考える際は、仕事だけではなく家庭や日常生活を含めたライフキャリアプランを考えることが重要です。
ライフキャリア設計に悩んだら、キャリアのプロであるキャリアコンサルタントに相談を検討するといいでしょう。
>キャリアコンサルタントへの相談はキャリアバディへ!
同僚への報告は社内の最終承認後に行う
同僚への報告は、上司および会社側の最終承認を得てから行うのが適切です。
万が一、退職の噂が先行してしまうと職場の雰囲気が悪化したり、上司との信頼関係に傷がついたりする可能性があるため、注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
同僚へ退職報告をするタイミングは、社内でコントロールすべき事項になります。
自身の一存で、大勢に触れ回ることが無いようにしましょう。
取引先への報告は後任の紹介と同時に行う
取引先への報告は、社内での手続きが整ってから、後任者の紹介とともに行うことが望ましいでしょう。
特に重要な取引先に対しては、できるだけ直接訪問して報告することが望ましいでしょう。取引先へ退職報告する際は、以下の点に留意して進めていきます。
- 後任者と同行して紹介を行う
- 継続案件の引き継ぎ状況を説明する
- 取引先との関係維持に配慮する
- 必要に応じて引き継ぎ期間中の連絡体制を説明する
取引先への報告は必ず会社の方針に従い、個人的な判断で情報を開示することは避けましょう。
また、取引先との良好な関係を維持するため、後任者への引き継ぎが確実に行われることを強調し、取引先に安心感を与えることが重要です。これまでの信頼関係を損なわないよう、最後まで誠実な対応を心がけましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
万が一にも、自身の退職が取引停止につながることが無いように、丁寧な報告と引き継ぎを心がけるようにしましょう。




円満退職を実現するための最終チェックリスト
円満な退職を実現し、今後のキャリアにも良い影響を残すためには、計画的かつ丁寧な対応が必要です。
ここでは、退職前に必ず確認すべき事項と、その具体的な進め方は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
最後まで責任を持って仕事に取り組む
退職が決まったからといって、現在の業務をおろそかにするのは避けるべきです。
むしろ、退職するからこそ、以下の点に特に注意を払いながら、最後まで真摯に仕事に取り組む姿勢を見せることが重要です。
- 進行中のプロジェクトの完了または適切な引き継ぎ
- 日常業務の質の維持
- 締切の厳守と報告の徹底
- 後任者への丁寧な引き継ぎ
退職が決まると、気が緩んで仕事でミスが多くなる場合もありますが、最後だからこそ気を引き締めて臨むようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
稀に「引き継ぎが完了したと認めるまで辞めさせない」と在職を強要するブラック企業もあるため、注意が必要です。
もしも退職に伴う引き継ぎを巡って揉めている、もしくはトラブルが発生しそうな場合は、弁護士の退職代行や労働局の総合労働相談コーナーに相談するようにしましょう。
参照:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」


同僚への挨拶と感謝を忘れない
長年働いてきた職場での人間関係は、退職後も貴重な財産となります。
最終出社日が近づいたら、直接の同僚だけでなく、関係部署の方々にも順番に挨拶回りをしましょう。この際、これまでの感謝を伝えるとともに、今後の連絡方法についても適切に共有することが大切です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
長く一緒に働いてきた人脈は、退職してもなくならない貴重な財産のひとつです。
退職後も連絡が取れるように、連絡先の交換をしておきましょう。
将来の紹介や推薦状をお願いする
転職活動を行う中で、以前の職場からの推薦状や紹介等のリファレンスチェックが必要になることがあります。
このようなリファレンスチェックが必要になった場合に備え、退職時に上司や人事部門に対して、将来の推薦状作成や紹介についての可能性を確認しておくことは有益です。
ただし、お互いの信頼関係が構築できていることを確認した上で、依頼をするようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
志望者が多い企業や信頼性が求められる業界では、リファレンスチェックを導入している企業も少なくありません。
いざという時に紹介・推薦を受けられる体制を整えておきましょう。
具体的な引き継ぎ書を作成する
業務の引き継ぎは、退職時の最も重要な業務の一つです。後任者が混乱なく業務を継続できるよう、以下のような項目を含む詳細な引き継ぎ書を作成しましょう。
- 日常業務の具体的な手順とポイント
- 取引先との重要な約束事や慣習
- システムやツールの利用方法
- 各種IDとパスワード
- トラブル発生時の対処方法
- 定期的な業務の実施時期と注意点
最終的な退職時には、これらすべての項目が適切に対応されているかを確認し、もし漏れがある場合は速やかに対処することが重要です。
円満な退職は、将来的なキャリアにとっても大きな意味を持つことを忘れずに、最後まで誠実な対応を心がけましょう。


退職したい時の言い方のまとめ
退職を伝える際には、適切なタイミングと丁寧な言い方を心がけることが、円満な退職への重要な鍵となります。
基本的な流れとしては、まず退職の1〜3か月前を目安に直属の上司にアポイントを取り、個室などの適切な場所で退職の意思を伝えることから始めます。その際、「突然のご報告で申し訳ございません」といったお詫びの言葉から切り出し、退職意思が固いことを明確に示しながらも、一方的な通告とならないよう配慮することが重要です。
退職理由については、会社や上司への批判を避け、建設的な理由を簡潔に説明することで、スムーズな退職手続きにつながります。また、引き継ぎ計画や最終出社日の希望など、具体的な提案を準備しておくことで、会社側との調整もスムーズに進めやすくなるでしょう。
このように、退職の意思表示から実際の退職日までの一連のプロセスを、計画的かつ丁寧に進めることで、お互いにとって納得のいく形で退職することが可能となります。
転職先で気持ちよく働くためにも、現職における適切な退職の言い方・進め方を心がけるようにしましょう。






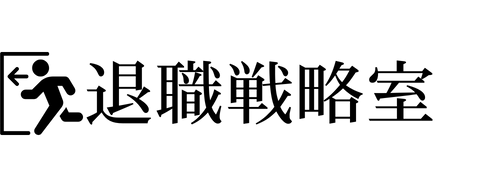
.png)

