最強の退職理由おすすめ7選!嘘を伝えるメリット・デメリットと円満退職のコツを解説

「本当の退職理由を言い出しづらい」
「退職したいけどスムーズに辞められるか不安」
会社に退職を伝える際に、このように悩む人は少なくありません。退職理由は必ずしも正直に話す必要はありませんが、伝え方を誤ると引き止めにあい、スムーズに辞められないことがあります。
そこで本記事では、引き止めを受けづらい最強の退職理由や、円満退職したい人におすすめの辞め方を解説していきます。
嘘の退職理由を伝える場合のメリット・デメリットも解説しているので、ぜひご確認ください。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


引き止められない最強のおすすめ退職理由7選!
退職を考えていても、「どう伝えれば引き止められずにスムーズに辞められるか」と悩む人は少なくありません。
特に、自分が悪者に見られたり、後味の悪さを残したりするのは避けつつ、スムーズな退職を実現するためには、ポジティブな印象を与える退職理由を伝えることがおすすめです。
会社側も納得しやすい、本記事が紹介する「最強のおすすめ退職理由」は以下の通りです。
- 別の業界へチャレンジするため
- 体調不良で仕事を続けられないから
- 家族の介護が必要になったから
- 資格取得に集中するため
- 新しい環境で働きたいから
- キャリアアップのため
- 会社の経営方針と自身の目標のミスマッチのため
それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)会社に伝える退職理由に「正解」はありません。
とはいえ、伝えた後の引き止めを避けたり、信頼関係を保ったまま退職したりするためには、上記のような「使いやすい退職理由」を選ぶことがおすすめです。
ただし注意すべき点として、現職に伝える退職理由と、転職先の面接で伝える退職理由は同じではありません。
状況に応じて「本音」と「建前」を使い分けることで、不要な誤解やトラブルを防ぐようにしましょう。
体調不良で仕事を続けられないから
体調不良は、引き止められにくい代表的な退職理由です。健康を損なってまで働き続けるべきではなく、会社としても無理に引き止めれば労務上のリスクを抱えることになります。
医療機関を受診している場合は、「医師から退職を勧められている」「治療に専念する必要がある」と事実に基づいて簡潔に伝えることで説得力が増すでしょう。
体調を理由にすれば、悪者扱いされる可能性はほぼ無く、自分も「やむを得ない決断」と納得しやすいため、罪悪感も感じることなく退職することができるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「体調不良で仕事を続けられない」という理由は、会社からの引き止めをほとんど受けない、いわば『無敵の退職理由』といえます。
ただし、実際に大きく体調を損なってしまうと、新しい職場での仕事に悪影響が出るだけでなく、転職活動においても不利になる可能性があります。
そのため、もし体調を崩しかねないような環境で働いている場合は、「働き続けられないほどの体調不良」になる前に退職を決断し、新しい環境へ転職することが望ましいでしょう。
家族の介護が必要になったから
家族の介護や看護を理由とした退職は、会社側が強く引き止められない退職理由のひとつです。
親や配偶者の介護は社会的にも理解されやすく、周囲から「仕方がない」と受け止められやすいでしょう。
家族の介護はプライベートな領域でもあるため、上司も深く踏み込めず、スムーズに退職が認められる可能性が高い退職理由といえます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「家族の介護が必要になった」と退職理由を伝えれば、引き止められる可能性は低く、かつ深く詮索されづらい点もメリットの一つです。
ただし、転職して仕事を続けながら家族の介護を行う予定がある場合には、現職で契約社員やパートといった形態に切り替えることで、無理なく働ける可能性もあります。
もし今の会社自体に大きな不満がないのであれば、一度相談してみるのも良いでしょう。
別の業界や職種へチャレンジするため
「新しい業界や職種に挑戦したい」という理由は、前向きでポジティブに受け取られやすい退職理由です。
単に「今の仕事辞めたい」のではなく「将来を見据えて新しい挑戦をしたい」という姿勢を示せるため、上司や同僚へ悪印象を与えにくい退職理由といえるでしょう。
ただし注意点として、新しく挑戦したい職種や業界が、自社の別部署やグループ会社でも実現可能な内容である場合、退職交渉の場で部署異動を提案されることがあります。
その結果、退職に関する話し合いが長引く可能性があるため、事前に想定しておくことが大切です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職の意思が固い場合は、あらかじめ転職先の内定を獲得してから退職を申し出るようにしましょう。
すでに新しい挑戦の場として転職先が決まっている場合、会社側も無理に引き止めることは難しくなるため、退職交渉をスムーズに進めやすくなります。
新しい環境で働きたいから
「新しい環境で働きたい」という理由は、やや抽象的ではあるものの、柔らかく伝えられる退職理由です。
実際には人間関係や職場の雰囲気に不満がある場合でも、この言い方を選べば角が立ちにくく、円滑に退職できる可能性が高まります。
ただし、「希望の環境で働ける部署に異動させるから辞めないでほしい」といった引き止めを受けるケースもあるため、あらかじめ返答を準備しておくと安心です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
また、「新しい環境で働きたい」とだけ伝えるとやや漠然とした印象になるため、「よりスキルを活かせる環境」「裁量権のある職場」など、より具体性を加えて伝える方が説得力が増すでしょう。
キャリアアップのため
キャリアアップを理由に退職を伝える場合は、「今の会社では得られない経験を積みたい」「将来的により広い役割を担いたい」と表現すると、上司にも納得してもらいやすくなります。
この理由は会社や上司を否定するものではなく、「自己成長を目指す前向きな姿勢」として受け止められるため、悪印象を与えにくいのが大きな特徴です。
また、キャリアアップを理由にすれば引き止められる可能性も低く、職場によってはむしろ応援してもらえるケースもあります。そのため、罪悪感を抱かずに円満退職を目指したい人にとって、非常に使いやすい退職理由といえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
キャリアアップを理由に退職を伝えると、「昇進させるから辞めないでほしい」といったカウンターオファーで引き止められる場合があります。
もっとも、こうした提案は実現しなかったり先延ばしになることも少なくありません。
そのため、転職を取りやめて現職に残るか検討する際は、役職・待遇・実施時期などの条件を具体化し、可能であれば書面で確認するなど、慎重に判断しましょう。
資格取得に集中するため
「資格取得に専念したい」という理由も、会社が引き止めづらい退職理由のひとつです。
難易度の高い国家資格の場合、学習にまとまった時間を割く必要があるため、「今の働き方では勉強時間を確保できない」「合格に向けて集中する必要がある」と説明すると納得されやすいです。
ただし、資格の難易度や有用性次第では「仕事しながらでも取得できる」「残業をなくすので辞めないで欲しい」と引き止めを受ける可能性があるため、注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
また、資格を取得できても、その間に職歴にブランクが生じると再就職が難しくなる可能性があります。
そのため、資格取得そのものにこだわるのではなく、5〜10年後を見据えたキャリアプランの中で資格取得や転職の計画を立てることが大切です。
キャリアプランの設計に悩んでいる場合は、キャリアバディでプロのキャリアコンサルタントに相談するといいでしょう。
会社の経営方針と自身の目標のミスマッチのため
「会社の経営方針と自分のキャリア目標が合わない」という理由は、やむを得ない退職理由のひとつです。
企業の方向性と個人の将来像や目標が一致しない場合、双方にとって無理に続けることは不利益になるため、退職することを理解されやすいのが特徴です。


そもそもなぜ会社は退職希望者を引き止めるのか?
ここまで「引き止めに合わない最強の退職理由」について解説してきましたが、実際に退職の意思を伝えると、多くの場合「もう少し考えてみないか」「条件を改善するから残ってほしい」といった引き止めに遭います。
では、なぜ会社はそこまでして退職者を止めようとするのでしょうか。上司や会社側が退職希望者を引き止める主な理由は、以下の通りです。
- 人手不足だから
- 売上が下がるから
- 上司の評価が下がるリスクがあるから
- 退職者のことを心配しているから
このように、引き止めるのは理由は必ずしも「退職者のため」だけではなく、組織や上司の事情によるものが大半であることが分かります。
それぞれ詳しく解説していきます。
人手不足だから
多くの企業が退職者を引き止める一番の理由は「人手不足」です。
特に人材不足が深刻な業界(医療・福祉業界や飲食業)では、一人辞めるだけで業務が大きく滞ることも珍しくありません。仮に新たな人材を採用できても教育に時間がかかり、戦力として働けるまでに長い期間を要します。
つまり、引き止めの根本はあくまで「会社都合」であり、退職時に強く引き止められたとしても、過度な罪悪感を抱く必要はありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
少子高齢化による労働力不足が深刻化している日本では、退職者が出ても簡単に穴埋めすることができません。
結果として、現場の負担が増すだけでなく、上司自身がさらに上層部から叱責を受けることも珍しくありません。
そのため、上司が必死になって退職希望者を引き止めるケースが多く見られるのです。
売上が下がるから
退職によって会社の売上や利益に直接影響が出るケースも、引き止めの大きな理由です。
例えば、営業職やSES企業でエンジニアとして働いている人が辞めれば、取引先との関係が不安定になり、契約を失うリスクも生じます。
また、専門的なスキルと知識を持った社員がいなくなることでサービスや商品の質が下がり、業績悪化に直結する恐れもあります。そのため、会社としては「売上減を防ぐために辞めてほしくない」という考えが強く働くのです。
これは会社の経営的な事情であり、個人が責任を感じる必要はありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職が売上の低下に直結する業務では、上司の評価や部署全体の成績にも直接影響が及びます。
そのため、上司が自らの立場や数字を守ろうとして、手段を選ばずに退職希望者を引き止めるケースも少なくありません。


上司の評価が下がるリスクがあるから
退職者が出ると、その上司のマネジメントスキルに疑問が持たれることがあります。
特に複数人が立て続けに辞めると「上司の管理が不十分ではないか」と評価に影響する可能性があります。そのため、上司自身が「自分の責任になるのは避けたい」と考え、必死に引き止めようとするケースが少なくありません。
つまり、退職者の将来やキャリアを本気で心配しているのではなく、上司自身の立場や評価を守るための引き止めを行っているケースも少なくありません。
このような背景を理解しておくと「引き止めは上司の事情」と割り切れるため、過度な罪悪感を抱かずに退職を進められるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
企業によっては、退職者の有無や人数そのものが管理職の重要なKPIとして設定されている場合もあります。
そのため、退職を申し出た際、上司から強い引き止めを受けるケースは少なくありません。
退職者のことを心配しているから
もちろんすべてが会社や上司の都合ではなく、純粋に退職者を心配して引き止める場合もあります。
「辞めて後悔しないか」「次の職場で本当に大丈夫か」といった想いから、本人のためを考えて声をかけてくれるケースです。特に長年一緒に働いた上司であれば、情として止めたいと感じるのも自然でしょう。
ただし、その心配が必ずしも正しいとは限りません。最終的に自分の人生を選択するのは自分自身です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
サービス残業や法律違反が横行するブラック企業からの転職でない限り、「絶対的な正解の退職」は存在しません。
大切なのは、周囲の意見を踏まえたうえで、自分が納得できる選択をすることです。


円満退職をしたい人におすすめの流れ
「退職」は人生の大きな転機ですが、伝え方や流れを誤ると職場に迷惑をかけたり、人間関係を悪化させたりするリスクがあります。
ここでは、円満退職を実現するために意識すべき流れは以下の通りです。
まずは転職先を確保する
円満退職を目指すなら、まず転職先を確保してから退職の意思を伝えるのが鉄則です。
転職先が決まっていれば、金銭的な不安がなく精神的にも安定して話し合いができることに加え、転職先が決まっていない状況であれば、ズルズルと引き止めを受ける心配もありません。
逆に転職先が未定のまま退職を申し出ると「なぜ急ぐのか」と不信感を持たれたり、説得されて辞めづらくなったりすることも少なくありません。
余計な引き止めを避け、スムーズに辞めたい人こそ、転職活動を先に進めておくことが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
中には「退職を伝える前に転職活動をするのは現職に失礼ではないか」と考える人もいます。
しかし、転職活動にはどのくらいの期間がかかるか予測できないため、自身のキャリアを考えると、できる限り在職中に次の職場を確保しておく方が無難といえるでしょう。
また、転職活動を進める中で「やはり今の職場でもう少し続けたい」と気持ちが変わり、退職の決意を見直すケースも少なくありません。
そのため、基本的には「まずは転職先を確保する」ことを優先するのがおすすめです。
退職の1カ月前までに申し出る
円満退職のためには、退職日の1カ月前までに申し出るようにしましょう。
法律上は、正社員(無期雇用)の場合「退職の2週間前」に伝えれば問題ありません。
しかし、実際には引き継ぎや後任の確保などに時間がかかるため、1カ月前までに伝えておく方が、会社側としては安心といえるでしょう。
特に、引き継ぎに時間を要する業務を担当している場合や、繁忙期を避けたい場合は、早めの相談が望ましいでしょう。
退職日まで余裕を持って伝えることで、会社も後任の採用や業務調整を行いやすくなり、不要な不満やトラブルを防げます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社によっては「退職は3カ月前までに申し出ること」といったように、就業規則で1カ月を超える長い期間を定めている場合があります。
ですが、法律上は2週間前の申し出で退職が可能であり、社会通念上も、1カ月前までに申し出れば問題ありません。
一方で、契約社員などの有期雇用契約の場合は注意が必要です。やむを得ない事情がない限り、契約期間満了前に退職するには会社の同意が必要になるため、注意しておきましょう。
>1カ月前に退職を伝えても辞めさせてくれない理由と対処法を解説


ネガティブな退職理由はポジティブに言い換える
退職理由の本音が「給料が低い」「人間関係が合わない」などの場合であっても、ネガティブな理由をそのまま伝えると、会社や上司を批判しているように受け取られかねません。
そのため、円満退職を目指すなら「スキルをさらに高めたい」「新しい環境で挑戦したい」といったポジティブな表現に言い換えるのがコツです。
上司へ過度に不快感を与えず、前向きな姿勢を示すことで、退職に理解を示してもらいやすくなるでしょう。
適切な引継ぎを行う
円満退職のためには、丁寧な引き継ぎが欠かせません。
自分が担当していた業務を後任者やチームにスムーズに渡せるように、マニュアルを作成したり、進行中の案件を整理したりすることが大切です。
引継ぎが不十分だと「無責任に辞めた」という悪印象を残し、後々の人間関係にも影響を与えかねません。
逆に丁寧に引継ぎを行えば「最後まで責任感を持ってくれた」と評価され、退職後も良好な関係を維持できます。次の職場で前向きにスタートを切るためにも、最後まで誠実な対応を心がけましょう。
嘘の退職理由を伝えても問題ないのか?
退職理由を正直に伝えるべきか、それとも嘘を交えてやんわり伝えるべきか悩む人は少なくありません。
結論としては、基本的に嘘の退職理由を伝えても問題ありません。嘘の退職理由を伝えても問題ない理由は以下の2つです。
- 正直に退職理由を伝えると引き止められる可能性があるから
- 正社員は退職理由を伝える義務はないから
退職時に、「人間関係がつらい」「給料が低い」などネガティブな本音をそのまま話すと、相手(上司・人事担当者等)を不快にさせたり、引き止めや説得を受けやすくなる可能性があります。
そのため、円満退職を目指すなら「本音をオブラートに包む」「事実と異なる理由を使う」ことも一つの選択肢になります。もちろん、完全な虚偽は避けるべきですが、「資格取得に専念したい」「家庭の事情でやむを得ない」など前向きに受け止められる口実を使うのは一般的です。
また、正社員(無期雇用)の退職は民法で以下のように規定されており、退職においてはそもそも理由を伝える必要が無く、申し出から2週間で辞めることが可能です。
民法627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
そのため、嘘の退職理由を伝えること自体が法律違反になるわけではないため、むしろ戦略的に活用してスムーズな退職を目指すのが賢明といえます。
ただし、民法628条の規定に基づき、契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合、雇用期間中に退職するためには、原則として「会社の合意」もしくは「やむを得ない理由」が必要となります(以下参照)。
民法628条 やむを得ない事由による雇用の解除
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
そのため、退職理由のウソがばれる可能性は低いものの、有期雇用契約の期間中に退職する場合は注意が必要です。万が一発覚すれば、損害賠償を請求されるなどのトラブルに発展する恐れがあります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
実際には、退職理由に多少の脚色をしても問題なく辞められるケースは多いですが、契約社員や派遣社員といった有期雇用の場合は契約途中の退職には一定のリスクがあります。
そのため、事実と矛盾しない「退職理由の言い換え」を工夫し、嘘にならない形で伝えることが重要です。




嘘の退職理由を伝えるメリット
会社を辞める際に、嘘の退職理由伝えるメリットは以下の通りです。
- スムーズに退職が可能
- 信頼関係を保ったまま辞めることができる
それぞれ詳しく解説していきます。
スムーズに退職が可能
嘘の退職理由を使う最大のメリットは、退職をスムーズに進められることです。
本音で「人間関係が合わない」「給料が低い」等の退職理由を伝えると、上司から改善策を提示され「改善するから残ってほしい」と引き止めに遭ったり、会社や上司を批判していると受け取られて気まずい雰囲気になる可能性があります。
ただし、可能性は低いものの、あとからバレて悪い評判が広まるくらいケースもあるため、事実と乖離しすぎる退職理由は避けや方がいいでしょう。
信頼関係を保ったまま辞めることができる
嘘の退職理由には「会社や上司との関係を悪化させずに辞められる」というメリットもあります。
正直に「給与が不満」「職場の雰囲気が悪い」と言えば、どうしても会社批判になり、会社側と溝を作ったまま退職することになってしまいます。
特に、仕事やプライベートで、退職後に元上司や同僚と再び関わる可能性が高い人は、信頼を損なわず円滑に退職を目指した方がいいでしょう。
嘘の退職理由を伝える際の注意点
退職理由で嘘を伝えることは、スムーズに辞めるための有効な手段のひとつですが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。
会社を辞める際に、嘘の退職理由伝える際の注意点は以下の通りです。
- 同僚にも本当の退職理由は伝えるべきではない
- 嘘がバレた時に信用を失う
- トラブルの元になる嘘は避けるべし
それぞれ詳しく解説していきます。
同僚にも本当の退職理由は伝えるべきではない
退職理由において、上司には嘘を伝えつつ、同僚には「実は人間関係が嫌で…」と本音を漏らしてしまう人は少なくありません。
しかし、噂はどこから漏れるか分かりません。一部の人にだけ本当の理由を話したつもりでも、いつの間にか職場全体に広がり、最終的に上司の耳に入ってしまう可能性があります。
そのため、仲の良い同僚であっても気を許さず、退職までの限られた期間は口を固くしておきましょう。退職理由は、最後まで一貫して表向きの説明を使うことが大切です。
嘘がバレた時に信用を失う
退職理由の嘘は、基本的に「ばれにくいもの」を選ぶことが大切です。
例えば「資格取得に専念したい」と伝えたのに、周囲に勉強している様子がまったくなければ不自然に思われる可能性があります。
もし知職理由の嘘が発覚すれば「最後に裏切られた」という印象を与え、これまで築いた信頼関係を一気に失うリスクがあります。
特に、同じ業界内で転職して働き続ける場合、噂が広がると転職先に悪影響を与えることもあるため注意が必要です。
トラブルの元になる嘘は避けるべし
「転職先が決まっている」と嘘をついたのに、後から無職であることが知られるようなケースは、不要なトラブルの元になります。
また「家族の介護がある」と伝えたのに、SNSで家族との旅行を楽しんでいる姿を投稿してしまえば、すぐに矛盾が露見します。
退職理由を偽る場合は、「会社が深掘りしにくい事情」「後から確認されないもの」を選ぶのが鉄則です。
転職先に退職理由を伝える際のポイント
転職活動では、面接官から高確率で「前職を辞めた理由」を質問されます。このときの答え方次第で、面接官に与える印象は大きく変わります。
正直に前職への不満を述べすぎると「同じ理由ですぐ辞めるのでは?」と不安を与えかねません。そのため、退職理由はできるだけ前向きに整理し、志望動機とつながる形にして伝えることが重要です。
ここでは、転職先で安心感を持ってもらえる退職理由の伝え方を3つのポイントに分けて解説します。
- 前職の悪口は言わない
- 退職理由と志望動機を結びつける
- 面接官が安心できる退職理由を選ぶ
前職の悪口は言わない
面接の場で「人間関係が悪かった」「給与が低すぎた」といったネガティブな退職理由をそのまま話すのは、絶対に避けましょう。
その退職理由がどれだけ事実でも、面接官からは「不満が多い人」「環境が合わないとすぐ辞める人」と見られる可能性があります。
面接の場では、「より幅広い経験を積みたい」「専門性を深めたい」といったポジティブな表現に言い換えることが大切です。悪口ではなく、自分の成長意欲やキャリア形成の観点で理由を語ることで、面接官も納得しやすくなるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
面接で退職理由を聞かれたときは、「今の仕事を辞めたい理由」ではなく、「新しい仕事で挑戦したいこと・実現したいこと」を軸に伝えるようにしましょう。
転職活動の面接に不安がある人は、キャリア相談プラットフォーム「キャリアアディ」で、キャリアコンサルタント等の専門家に相談するのがおすすめです。
退職理由と志望動機を結びつける
面接で退職理由を確認された際には、転職先の仕事でやりたいことや、5年後~10年後を見据えたキャリアの目標を軸に伝えるようにしましょう。
単なる前職不満や環境改善だけを退職理由にしてしまうと印象が悪くなりますが、自身の目標や挑戦したいことと結びつけることで「前向きな転職」と理解されやすくなります。
退職理由と志望動機を一貫性のあるストーリーにまとめることが、面接突破のポイントです。
面接官が安心できる退職理由を選ぶ
面接において採用担当が知りたいのは「この人は同じ理由ですぐ辞めないかどうか」です。そのため、面接で退職理由を聞かれた際には、安心感を与える理由を選ぶことが大切です。
例えば「専門的なスキルをさらに高めたい」「長期的なキャリア形成のため」といった理由は前向きで、かつ再現性のあるものであるため、安心して受け入れてもらいやすい退職理由といえるでしょう。
面接官の視点に立ち、納得感と安心感を与える多食理由の説明を意識しましょう。
退職理由に関するよくある質問
最後に、退職理由に関するよくある質問について、Q&A形式で解説していきます。
引き止められない退職理由はどんなものがありますか?
「体調不良」や「家族の介護」といった理由は、会社側も強く引き止めにくいため、比較的スムーズに退職しやすい理由といえます。
どんな退職理由でも辞められますか?
正社員(無期雇用契約)の場合、どんな退職理由であっても伝えて最短2週間で辞めることが可能です。
契約社員等の有期雇用契約の場合、契約期間中の退職には原則として会社の合意が必要ですが、「やむを得ない退職理由」があればすぐに退職することが可能です。
退職届の退職理由にはなんて書けばいいですか?
基本的に「一身上の都合」と記載して問題ありません。
ただし、ハラスメントなどが退職理由の場合は「会社都合退職」として辞めることになるため、退職理由に明記するようにしましょう。
退職理由は嘘でも問題ないですか?
正社員の場合、法律上そもそも退職理由を伝える義務はなく、基本的には表向きの理由や多少の嘘を交えても問題なく退職できます。
一方で、契約社員などの有期雇用契約では事情が異なります。
契約期間中に辞める場合は、原則として「会社の合意」または「やむを得ない退職理由」が必要です。そのため、退職理由の嘘が発覚すると、損害賠償などのトラブルに発展するリスクがあるため注意が必要です。
面接で退職理由を聞かれた際はどう答えたらいいですか?
面接で前職の退職理由を聞かれた際は、ネガティブな表現は避け、できるだけ前向きな理由に言い換えることが大切です。
具体的には、前職への不満や悪口は控え、「転職を通じて何を実現したいのか」という転職理由と結びつけて説明すると、説得力と前向きさを兼ね備えた退職理由の伝え方ができます。
最強の退職理由まとめ
引き止められづらく、スムーズに辞められる最強の退職理由は以下の通りです。
- 別の業界へチャレンジするため
- 体調不良で仕事を続けられないから
- 家族の介護が必要になったから
- 資格取得に集中するため
- 新しい環境で働きたいから
- キャリアアップのため
- 会社の経営方針と自身の目標のミスマッチのため
これらの理由は上司や会社が否定しにくく、合理的な引き止めを行うことが難しいといえます。
もちろん、退職理由については多少の脚色や嘘を交えても大きな問題にはなりません。ゆくゆくのトラブルや転職先への悪影響を避けるためには、「矛盾がなく」「万が一ばれても大きな支障にならない」程度にとどめることが重要です。
スムーズに退職するためにも、本記事で紹介した退職理由を参考にしつつ、最後まで誠意を持って対応し、円満退職を実現しましょう!
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/






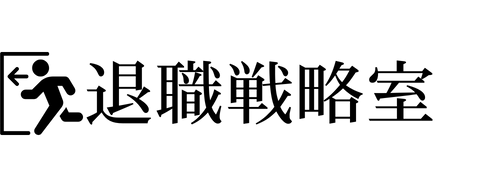
.png)





