【弁護士監修】退職代行は契約社員でも使える!5つの利用条件とデメリットを徹底解説

「契約期間の途中だから退職できない」「正社員と違って退職代行は使えないのでは」と悩んでいる契約社員の方も多いようです。
雇用期間の定めがある契約社員やパート社員でも、実は一定の条件を満たせば退職代行サービスを利用できます。
本記事では、退職代行を契約社員が利用できる条件や具体的な流れ、注意点まで徹底解説します。これから退職代行の利用を検討している契約社員の方は、ぜひ最後までご覧ください。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


法律に定められた契約社員の退職ルールを解説
- 契約社員は退職できない
- 契約満了まで働かないといけない
契約社員として働いている人のなかには、このような話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
確かに、雇用の定めがない正社員とは違い、契約社員やパートなどの有期雇用契約を結んでいる場合は、雇用契約期間中に退職することは比較的難しいといえます。
ではなぜ、「契約期間中は辞められない」という誤解が広まっているのでしょうか。ここからは、会社の正社員と契約社員の退職に関するルールについて、以下の2つの視点で解説していきます。
正社員の場合は退職の2週間前に申し出が必要
民法627条に定められている通り、期間の定めがない雇用契約の会社員(正社員)の場合、申し出から最短2週間で退職を成立させることが可能です。
一方で、会社側が「退職を認めない」と主張しても、労働者の退職の自由は法的に保障されており、2週間経過後には退職が成立します。
トラブルを避けて必ず退職を実現するためには、退職届を書面またはメールで記録を残す形で提出し、交渉の余地を残さないことが重要になります。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)正社員の場合は「2週間前の申し出で労働契約の解除が可能」と法律に明記されています。
そのため、有給休暇が残っていれば、退職代行を使って退職日まで就労しないという対応も可能です。
ただし、担当業務や退職時の状況によっては損害賠償のリスクはゼロではないため、引き継ぎ範囲や方法については状況に応じて検討する必要があるでしょう。




契約社員の場合はやむをえない事由があれば退職可能
雇用期間に定めのある契約社員の場合、原則として契約期間満了まで退職できません。
「退職のやむを得ない事情」は状況によって様々ですが、具体例としては「職場におけるハラスメント」「仕事を続けられない家庭の事情」等が挙げられます。
さらに、会社側と合意の上での退職(合意解約)であれば、契約期間に関係なく辞めることができます。
そのため、「契約社員だから退職できない」と悩んでいる場合は、上記を踏まえて退職するための方法を検討するといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ブラック企業によっては、退職の申し出をしても「契約期間中は辞められない」と退職を拒否するケースがあります。
ですが、実際は条件を満たせば退職することが可能です。
もしも雇用期間中に退職したいと悩んでいる場合は、プロの退職代行サービスに辞めるための方法を相談してみるといいでしょう。
退職代行を契約社員でも利用できる条件は?
「契約社員は退職代行サービスは使えない」という話を聞いたことはないでしょうか?
前述したように、契約社員やパート社員のように有期雇用契約で働いている場合であっても、条件を満たせば雇用期間中に退職をすることは可能です。同様に、いくつかの条件を満たせば退職代行サービスを通じて退職することも可能な場合があります。
契約社員が退職代行を利用して辞めるための条件は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。



ただ、これがあるから「退職代行サービスを必ず利用できる」というわけでもないことは注意しましょう。
退職のやむをえない理由がある場合
民法第628条に基づき、やむを得ない事由がある場合は、契約期間中であっても退職が認められます。具体的には、以下のような退職理由が該当します。
- パワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている
- 健康上の理由で業務継続が困難
- 労働条件に重大な問題がある場合
- 家庭の事情で仕事を続けられない
上記について、それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
上記はあくまで一例です。
もしこれらの退職理由に当てはまらない場合でも、やむを得ない理由として認められるケースは多々あります。


職場でハラスメントを受けている場合
職場でハラスメント(パワハラ・セクハラ)を受けている場合は、雇用形態を問わず、明確な退職理由として認められます。
特に上司からの暴言や嫌がらせ、不当な扱いなどが継続的に行われている場合は、職場環境の悪化で就労困難として正当な退職理由となり得ます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
パワハラやセクハラがひどい場合は、退職時に慰謝料の請求を行うことも可能です。
ただし、民間事業者の退職代行では訴訟などの法的対応ができないため、慰謝料請求の際は弁護士の退職代行に相談するようにしましょう。


健康上の理由がある場合
メンタルヘルスの悪化や身体的な疾患により、業務の継続が困難になった場合も、契約社員のやむを得ない退職理由として認められます。特に、医師の診断書がある場合は、さらに説得力のある退職理由となるでしょう。
「契約社員だから雇用期間中は働かなければ」と考えて無理をせずに、適切なタイミングで退職をするといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
職場の精神的なストレスが原因により体調不良の場合、退職を直接申し出るハードルが高く、言い出せないことも少なくありません。
その場合は、退職代行を使って迅速に辞めることも検討しましょう。
労働条件に重大な問題がある場合
契約書に記載された労働条件と実際の労働環境が著しく異なる場合や、残業代や給与が適切に支払われていないなどの法令違反がある場合は、正当な退職理由として認められやすいと考えられます。
その場合、退職代行サービスを通じて適切なサポートを請けつつ、迅速かつ確実に退職実現を目指すことがおすすめです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
未払いの給与や残業代がある場合、退職代行を使って適切に請求することが重要です。
未払い賃金の請求を行う場合は、退職に関する諸条件において「交渉」を行う権利をもつ「労働組合」や「弁護士」の退職代行サービスに相談するといいでしょう。
※民間の退職代行では退職に関する交渉はできないため注意


家庭の事情で仕事を続けられない場合
家族の介護や育児など、やむを得ない家庭の事情により仕事を継続することが困難になった場合も、契約社員の正当な退職理由として認められます。
そのため、家庭環境の変化によって退職を考えている要因になる場合、退職理由として伝えても問題ありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
家庭の事情でどうしても就労が困難という場合もやむを得ない理由と認められる可能性はあります。
ただし、単に家族が反対しているなどの理由では不十分であり、育児・介護など就労に具体的に支障のある事情である必要があることに注意しましょう。
会社が合意している場合
会社側と退職について合意が得られる場合は、契約期間に関係なく退職が可能です。これを俗に「合意退職」と呼び、両者の話し合いによって退職時期や条件を決定します。
退職代行サービスは、この合意形成のプロセスをスムーズに進めるための交渉の代行をしてもらうことが可能です。




雇用契約から1年以上経過している場合
労働基準法第137条により、雇用契約の開始から1年以上が経過している契約社員(有期雇用契約社員)は、いつでも自由に退職することができます。これは、もともとの契約期間が1年を超える契約を結んでいる場合に適用される規定です。
この場合、会社に申し出ることで、いつでも退職が可能となります。たとえば、2年契約で働いている契約社員であれば、1年経過後はいつでも退職できます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
契約社員の雇用期間は「1年毎に更新」の場合が多いですが、この場合は対象になりません。
いつでも退職できるので、1年を超える雇用契約において1年以上働いた契約社員の場合に限られるため、注意しておきましょう。



以上のような理由があれば、契約期間の途中でも退職することは可能と考えられます。
もっとも、退職理由の有無や程度で会社と労働者との間で認識の相違が生じる可能性があり、弁護士資格のない民間の退職代行サービスでは対応困難としてサービス利用ができない可能性が高いです。
したがって、退職理由について会社と具体的な協議や交渉が必要な場合は、自らこれを行うか、それが難しければ弁護士や労働組合に対応を依頼するべきでしょう。
退職代行を契約社員が利用する際の選び方
退職代行サービスを選ぶ際は、契約社員特有の事情を考慮して選ぶことで、安全かつ確実な退職が可能になります。契約社員が退職代行サービスを選ぶ際の重要なポイントは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。


契約社員の退職代行に対応したサービスを選ぶ
退職代行サービスの中には、正社員のみを対象としているものもあるため、契約社員のひとは、まず自分の雇用形態に対応しているかどうかを確認することが重要です。
対応の有無は、サービスのホームページで確認できるほか、無料相談の際に直接確認することもできます。
契約社員の場合、退職代行サービスを選ぶ際は以下の点を確認しておきましょう。
- 契約社員の退職実績が明確に記載されている
- 契約社員向けの料金体系が明示されている
- 雇用形態別の成功事例が掲載されている
上記のポイントを確認した上で、気になる退職代行サービスの相談してみるといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行の業務内容としては、契約社員も正社員も大きな違いがないため、契約社員だけ対応していないサービスは非常に稀です。
ただし、実績がなければ契約社員特有の事情に詳しくない可能性があるため、注意しておきましょう。


退職代行実績が豊富なサービスを選ぶ
契約社員の退職は正社員と比べて手続きがやや複雑になる可能性が高いため、豊富な実績を持つサービスを選ぶことが重要です。
実績のあるサービスは、様々なケースに対応した経験があり、予期せぬ事態にも適切に対応できます。また、実績数だけでなく、具体的な成功事例や利用者の声なども参考にしましょう。
労働組合または弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶ
契約社員の退職においては、会社との間で具体的な協議や交渉が必要となる場合もあります。
そのため、契約社員の仕事を辞めたい際には、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶことをお勧めします。労働組合および弁護士の退職代行を選ぶべき理由は以下の通りです。
- 法的な観点からの適切なアドバイスが受けられる
- 会社との交渉が可能
- トラブル発生時のサポートが充実
契約社員の退職は、多くの場合契約期間中に辞めることになるため、法的な観点からのサポートが不可欠です。
ですが、弁護士資格のない民間の退職代行サービスは弁護士法の関係で会社と退職理由について協議・交渉をすることが許されません。
これに対し、労働組合や弁護士が運営するサービスであれば、この弁護士法の縛りを受けずに退職に関する具体的な協議・交渉を行うことができるため、契約社員の退職におすすめといえます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職に伴う交渉は民間業者にはできないため、退職に伴う交渉の代行をしてもらいたい場合は、労働組合か弁護士の退職代行を選ぶべきといえます。
ただし、労働組合では損害賠償請求や懲戒解雇などの法的トラブルに対応することは出来ないため、退職にあたってこれらのリスクがある場合は弁護士の退職代行に依頼をする必要があります。




退職代行を契約社員が利用する場合の6つのステップ
ここでは、契約社員が退職代行サービスを利用する際の具体的な流れを、6つのステップに分けて解説します。
無料相談で退職条件を確認する
まず最初に、退職代行サービスの無料相談を利用して、自分のケースが退職代行の対象となるかや、希望の退職条件や退職に伴うリスクを確認します。
無料相談では、主に以下の点を伝えるようにしましょう。
- 雇用契約期間と勤続年数
- 退職を希望する理由
- 現在の労働環境での問題点
- 退職希望時期の目安
退職代行の無料相談では、これらの情報を基に退職の実現可能性や具体的な進め方について、専門家からアドバイスを受けることができます。
サービス内容と料金を比較検討する
可能であれば、複数の退職代行サービスの内容と料金を比較し、自分に最適なサービスを選ぶことがおすすめです。
この際、契約社員の退職に特化したサービスを提供しているかどうかを重視しましょう。また、基本料金以外に追加料金(※)が発生する可能性についても確認しておきましょう。
退職代行を依頼する
依頼するサービスを決めたら、正式に退職代行を依頼します。
多くの代行サービスは前払いとなっており、入金確認後に退職に向けた対応が始まります。
必要書類を準備して退職手続きを開始する
退職代行サービスの利用を決めたら、必要な書類を準備します。
退職に伴って一般的に必要となる書類には、雇用契約書のコピー、源泉徴収票、直近の給与明細などがあります。
また、退職者が損害賠償を請求する場合は、パワハラなどの証拠となる資料も合わせて準備します。
退職日程と給与受け取りを調整する
退職代行業者を通して、会社側と退職日程の調整を行います。
この段階では、最終出社日や給与の精算方法、有給休暇の消化などについて具体的な調整が行われます。特に契約社員の場合は、契約期間との兼ね合いで退職時期の調整が重要になるでしょう。
また、未払い残業代がある場合は、その請求についても検討します。
退職完了
最終的な退職手続きが完了したら、会社から必要な書類(退職証明書、離職票など)を受け取ります。
この段階で退職代行業者は、これらの書類が適切に発行されているかを確認し、必要に応じて会社側との調整を行います。また、代行サービスによっては退職後に必要となる各種手続き(健康保険の切り替えなど)についてもアドバイスを受けることができます。
退職完了後も、退職代行サービスによってはアフターフォローを提供しているところもあります。万が一、退職後に会社とのトラブルが発生した場合などに備えて、サポート体制を確認しておくことがおすすめします。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職後のキャリアに関して悩んでいる人は、キャリアバディのような有料キャリア相談サービスで専門家に相談してみるといいでしょう。
>おすすめの有料キャリア相談サービスはこちら
退職代行を契約社員が利用する際のデメリット
契約社員が退職代行サービスを使って辞めることは多くのメリットがある一方で、以下のデメリットも存在します。
それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
これらのデメリットが発生することは現実的にはあまりないものの、ゼロではありません。
退職代行を使って契約社員を辞めるリスクを理解したうえで、代行サービスを使うかどうかを検討するといいでしょう。
退職を拒否されるリスクがある
契約社員の場合、契約期間中の退職であることや、代行サービスを経由して退職の連絡をしたことを理由に、会社側から退職を拒否されるリスクがあります。特に退職理由が明確でない場合や、やむを得ない理由に該当しない場合は、退職を拒否される可能性が高くなるでしょう。
退職を拒否されるリスクに対しては、以下の準備が有効となります。
- 退職理由を具体的な事実に基づいて整理しておく
- パワハラやセクハラの客観的な証拠を準備する
- 労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶ
退職代行を使っても、会社を辞めるにあたってのやり取りをすべて拒否されてしまっては、手続きを進めることができません。
退職代行を使うことで、会社から退職や手続きの拒否をされそうな場合は、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスを選んでしっかり交渉してもらうことや、労働基準監督署に相談に行くことがおすすめです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
雇用期間の定めがある契約社員は、「やむを得ない理由」があれば、法律上はいつでも退職をすることができます。
参照:e-Gov法令検索「労働基準法第137条」
ですが、現実には法律の定めを無視した対応を行うブラック企業もあるため、円滑に退職を進めるためには適切な準備が重要になります。


転職活動に悪影響が出る可能性がある
退職代行サービスを利用することで、転職活動に悪影響が発生する可能性があります。
本記事でもお伝えしている通り、有期雇用の契約社員は「やむを得ない理由」がある場合や、会社が退職に合意している場合は問題なく退職代行を使って辞めることが可能です。
そのため、退職代行サービスを利用する際は、可能な限り円満な形での退職を目指します。これには、適切な引き継ぎ期間の確保や、必要書類の適切な処理が含まれます。また、退職理由については事実に基づいた説明ができるよう、整理しておくことが重要です。
また、次の就職先での面接では、退職の経緯について淡々と事実を説明し、将来に向けての前向きな姿勢を示すことが効果的です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
そもそも、本来は「退職代行を使われた会社」だと思われたくないため、代行業者を使って辞めたという個人情報が外部に出ることは多くはありません。
ですが、可能性は低いもののゼロではないため、注意が必要です。
また、前職のリファレンスチェックが必要な会社へ転職する場合は、転職においてやや不利になるといえるでしょう。
契約社員が退職代行で辞めた後の注意点
退職代行サービスを利用して無事に退職が完了したあとも、いくつかの重要な手続きが必要です。これらの手続きを適切に行うことで、その後の生活や再就職をスムーズに進めることができます。
退職後に必要な以下の手続きと注意点について、具体的に解説していきます。
必要な社会保険の手続きを確認する
退職後は、健康保険や年金の切り替え手続きが必要になります。特に契約社員の場合、以下の点に注意して手続きを進める必要があります
- 国民健康保険への切り替え
- 国民年金への切り替え
- 雇用保険の失業給付に関する手続き
(ハローワークで手続きが必要)
これらの手続きは期限が設けられているものが多いため、退職が決まったら、早めに準備を始めるといいでしょう。
特に失業給付は手続き、および認定が遅れればその分受け取れるタイミングが後ろ倒しになってしまうため、注意が必要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
失業給付を受け取るにあたり、「会社都合退職」であれば自己都合退職よりも早く失業給付を受けることが可能です。
退職代行を使って辞める場合であっても、いじめやパワハラ等が退職原因の場合は交渉して「会社都合退職」にすることも可能です。
ただし、上記の交渉は弁護士、もしくは団体交渉権を持つ労働組合しかできないため、注意しておきましょう。




会社貸与品の返却について相談する
会社から貸与されていた物品の返却は、退職時の重要な手続きの一つです。パソコンや携帯電話、制服などの返却について、退職代行サービスを通じて具体的な方法と時期を確認しましょう。
特に以下の点について、明確に取り決めておくことが重要です。
- 返却方法(郵送か直接持参か)
- 返却期限
退職完了後に余計なトラブルに巻き込まれないようにするためにも、会社備品や貸与品の返却は確実に行うようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
返却が必要な物品の具体的なリストを作成し、事前に共有することで会社側との認識を統一しておくことも重要になります。


給与や諸手当の清算方法を確認する
契約社員が退職代行を使って給与や諸手当の清算には特に注意が必要です。最終給与の支払い時期や方法、未消化の有給休暇の取り扱い、残業代の精算などについて、具体的に確認しましょう。
また、契約期間途中での退職となる場合、以下のような点についても確認が必要です。
- 契約期間満了による退職金の扱い
- 賞与や各種手当の按分計算の方法
- 社会保険料の精算方法
上記は基本的に就業規則に記載されているため、事前に確認しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
未払いの残業代・給与がある場合、ここでしっかり請求するようにしましょう。
未払い賃金の請求を行う場合、退職に関する交渉が可能な労働組合、もしくは弁護士に依頼することがおすすめです。
契約社員が退職代行使う条件と流れまとめ
契約社員が退職を考える際、「契約期間があるから退職できない」と悩む方は少なくありません。
しかし、本記事で解説してきたように、一定の条件を満たせば契約社員でも契約期間中に退職できますし、その退職について退職代行サービスを利用することもできる場合があります。
退職代行サービスを選ぶ際は、必ず契約社員対応が可能なサービスを選び、できれば労働組合や弁護士が運営するサービスを選択することをおすすめします。これにより、法的な観点からのサポートを受けながら、適切な退職手続きを進めることができます。
また、退職後の手続きや清算についても、専門家のアドバイスを得ながら進めることで、スムーズな退職が実現できるでしょう。
退職は誰にとっても人生の大きな転機となります。特に契約社員の方は、雇用形態特有の制約や課題に直面することもありますが、それは決して乗り越えられない壁ではありません。適切なサポートを受けながら、自分らしい働き方を実現するための一歩を踏み出しましょう!



一般的に無期雇用で働く労働者を正社員、有期雇用で働く労働者を契約社員と呼んでおり、正社員の方が契約社員よりも職責が重いことが多いと言えます。
そのため、正社員は退職しづらく、契約社員は比較的かんたんに辞められると思っている方も多いでしょうが、法律的には実は逆です。
もっとも、この点は雇用している側もよくわかっていないことが大半であり、実際には契約社員が退職したいと言った場合にこれを強く遺留するケースはほとんどなく、労使間の合意でスムーズに退職できる場合が大半と思われます。
ですが、契約期間中の退職でトラブルとなるケースもゼロではないことから、運悪くそのようなトラブルとなってしまった場合には退職代行サービスの利用等を検討しても良いかもしれません。


プラム綜合法律事務所
【保有資格】
- 弁護士
【経歴】
第二東京弁護士会所属。
東京大学法学部卒業後、日本四大法律事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。6年間の実務経験を経て、2014年に独立し、プラム綜合法律事務所を設立。
企業法務全般から労務トラブル、訴訟対応、交通事故、相続、刑事事件まで幅広い分野に対応。
著書・執筆実績も多数あり、労務管理やハラスメント対応の専門家として多方面で活躍中。
【主な著書】
『ハラスメントの正しい知識と対応 職場で取り組む予防・対策』(ビジネス教育出版社)
『それ、パワハラですよ』(ダイヤモンド社)
2025年5月4日監修






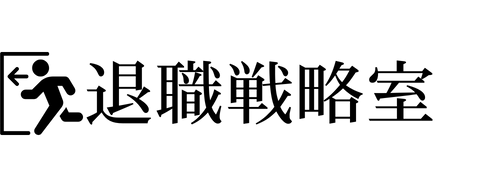
.png)







