退職代行を使ったら引き継ぎ不要で辞められる?4つのリスクと安全な対処法を解説

退職代行を利用する際に、「引き継ぎはどうすればよいのか」という不安を多くの方が抱えているようです。
代行業者を使って引き継ぎなしに退職することは可能ですが、場合によっては損害賠償を請求されるリスクがあるため、注意が必要です。
本記事では、退職代行利用時の引き継ぎについて、法的な観点から解説するとともに、想定されるリスクや安全に退職するためのポイントを紹介します。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


退職代行で引き継ぎせずに辞めることは可能なのか
退職代行サービスを利用して引き継ぎなしで退職することは可能です。ただし、自身が携わる仕事の内容や、引き継ぎをしないことで発生する問題によっては、損害賠償請求をされる等のリスクがあります。
ここからは、退職代行を使って引き継ぎをせずに会社を辞めることについて、以下の3つの観点から解説していきます。
理解しておくべき3つの考え方
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)引き継ぎをせずに退職代行を使って辞められるかという問いの結論としては、「場合によって異なる」という回答になります。
退職時の引き継ぎに対する考え方について、上記3つの考え方から解説していきます。
法律上は引き継ぎに関する定めはない
民法上、無期雇用契約の労働者(正社員)には退職の自由が保障されています。
参照:e-GOV法令検索「民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
これに対し、業務引き継ぎについて法律の明確な定めはないため、退職時に引き継ぎをする法律上の義務はありません。
そのため、退職代行サービスを利用する場合であっても、会社からの求め次第で必要な引き継ぎを行わなければならない可能性があるため、注意が必要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
特に、引き継ぎなく退職することで会社が重大な損害を被る場合は損害賠償を請求される場合もあるため、状況に応じて引継ぎの準備をする必要があります。
民法で保障された退職の自由
法律上、期間の定めのない労働者(正社員)はいつでも退職の申し入れが可能で、申し入れから2週間で退職可能と定められています。
また、契約社員やパートなどの有期雇用社員の場合でも、やむをえない事情がある時は、雇用期間中であっても退職することができます。
参照:e-GOV法令検索「民法第第627(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
参照:e-GOV法令検索「民法第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)」
また、退職が決まっている人の有給休暇の取得を退職日以降にすることは出来ないため、退職日まで有給を使うことで、引き継ぎをせずに退職日を迎えることは実現可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職の自由と有給休暇を駆使することで、引き継ぎをせずに退職することは可能ですが、担当業務次第ではリスクがあることを認識しておきましょう。




ただし引き継ぎ放棄にはリスクもある
退職代行を使って全く引き継ぎをせずに退職をした場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 会社から損害賠償請求される可能性
- 退職金がもらえなくなるリスク
- 同僚との人間関係の悪化
- 今後の転職活動への悪影響
引き継ぎをせず、要請があっても拒否することで、会社が重大な問題・損失を被る場合は、損害賠償請求をされる可能性があります。
退職代行サービスを利用する場合でも、これらのリスクを考慮した上で、どの程度の引き継ぎが必要かを判断することが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
引き継ぎをした方がいい場合であっても、全てを完ぺきに引き継ぐことを求められるケースは稀で、退職日までに誠実に対応可能な範囲で実施するべきといえます。
マニュアルや引き継ぎ書を用意することが可能であれば、事前に準備を進めておくといいでしょう。


退職代行で辞める際の引き継ぎに関する重要ポイント
退職代行サービスを利用する際の引き継ぎについて、知っておくべき以下の重要なルールと注意点を解説します。引き継ぎをめぐって想定外のトラブルに巻き込まれないようにするために、必ずチェックしておきましょう。
引き継ぎに関する重要ポイント
それぞれ、詳しく解説していきます。
就業規則の引き継ぎに関する規定は要確認
会社を辞める際の引き継ぎは法律上に明確な定めはなく(※)、退職代行サービスを利用する場合でもそれは変わりません。
しかし、企業の就業規則や雇用契約書に引き継ぎに関する規定がある場合は、その内容に従う必要性を検討する必要があります。会社の就業規則に引き継ぎについての規定がある場合、特に以下の点を確認することが重要です。
- 退職時の引き継ぎ義務の有無と範囲
- 引き継ぎを怠った場合の罰則規定
- 退職金支給条件との関連性
特に、企業によっては適切な引き継ぎを退職金の支給を紐づけている場合もあるため、注意が必要です。退職金を確実に受け取りたい場合は、まずは就業規則を確認し、必要に応じて引継ぎの準備を検討するといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
就業規則に引き継ぎをしないことへの重い罰則が規定されている場合がありますが、短期間で退職する際に完璧に引き継ぎを行うことは現実的ではありません。
退職代行を使って辞める際、引き継ぎ方法や範囲について悩んでいる場合は、会社との交渉が可能な弁護士の退職代行サービスに相談するのがよいでしょう。
弁護士の退職代行は引き継ぎ交渉もサポート可能
弁護士が運営する退職代行サービスでは、会社との引き継ぎ範囲の交渉も可能です。
法律上、民間の退職代行業者では退職に伴う交渉はできません。これに対し、弁護士の退職代行は適切な引き継ぎ範囲の設定や方法の交渉、会社からの過度な要求への対応もサポートしてもらえるため、安心して退職を進めることができます。
ですが、退職代行を使って辞めようとした際に、出社による引き継ぎの強要などの無理な要求に対し、法的根拠に基づく交渉をしてもらえるという点で弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
弁護士の退職代行であれば、自身の業務範囲や退職に伴って発生する影響を考慮し、損害賠償を請求されるリスクや対策などを事前に相談できるため、非常に心強いです。


民法で定められた退職2週間ルール
民法第627条に記載の通り、正社員(無期雇用)の場合は、退職の申し出から2週間で退職が可能です。
参照:e-GOV法令検索「民法第第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)」
ただし、仕事の内容によっては2週間で全て行うことは困難です。その場合は、事前に引き継ぎに関する書類を用意しておくことが望ましいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
雇用期間に定めがある契約社員やパート社員の場合は上記の2週間ルールは適用されませんが、「やむを得ない理由」があれば、すぐに退職することが可能です。
ただし、退職の「やむを得ない理由」が自身の過失によって生じるものの場合、法律上は「損害賠償の責任を負う」とされているので、注意が必要です。
参照:e-GOV法令検索「民法第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)」


有給休暇を使って引き継ぎを回避できる可能性がある
代行業者経由で退職の申し出を行った際に、残っている有給休暇を利用することで、出社をせずに即日退職のプロセスを進める選択肢もあります。
ただし、この場合でも重要な業務や機密情報の取り扱いについては、適切な対応を検討する必要があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行サービスによっては、引継ぎ書類を作成する際に役立つテンプレートを用意している業者もあるので、必要に応じて確認しておくといいでしょう。




退職代行を使って引き継ぎをせずに辞める4つのリスク
退職代行サービスを利用して引き継ぎなしで退職する場合、以下のリスクが存在します。
引き継ぎせずに辞める4つのリスク
これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることで、円滑な退職を実現可能です。それぞれ、詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行サービスによっては、「引継ぎ無しで辞めれる!」と謳うものもありますが、実際は退職希望者の受け持つ仕事や状況によって異なります。
退職代行を利用する際は、上記のリスクを理解したうえで、気持ちよく辞められるように必要な準備をすることがおすすめです。
会社から損害賠償を請求されるリスク
引き継ぎをせずに退職することで、会社に具体的な損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、現実的には退職代行を使って辞めたことに対する損害額を算出することは困難で、主観的な引き継ぎ不足だけでは、直ちに賠償責任が発生するわけではありません。
そのため、最低限伝えなければならない情報の伝達によって、退職に伴う引き継ぎを完了させられるケースも多くあります。
不安な人は、引き継ぎ範囲の交渉が可能な弁護士の退職代行に相談してみるといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
勤める会社によっては、「人手不足なので辞められたら迷惑」という理由で損害賠償を仄めかし、退職日の引き延ばしを図る場合もあります。
ですが、事前に退職の申し出を行い、適切な退職日の設定(正社員の場合は申し出から最短2週間後)をしたうえで退職する場合、現実的に損害賠償が必要になるケースは少ないでしょう。
会社としては当該期間中に人材募集および採用を行う義務があります。
自分一人の責任と抱え込まずに、退職のためにまずは代行業者に相談してみるといいでしょう。


懲戒解雇される可能性がある
就業規則に引き継ぎ義務が明記されている場合、引き継ぎを全く行わないことは就業規則違反として扱われる可能性があります。
最悪の場合、通常の退職ではなく懲戒解雇される危険性があり、これは今後の転職活動においても大きな不利益となりかねません。
ですが、退職代行を使って辞めることや、引継ぎをしないことに対し会社側が感情的になり、会社側が職権を濫用して懲戒解雇の処分を行うことも否定できません。
この場合は不当解雇にあたり認められない可能性が高いものの、裁判を行う時間と費用が必要になるため、出来る限り避けるべき事態といえます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職希望者は次のキャリアのために時間を使うべきであり、裁判対応に疲弊してしまうのは、あまりに勿体ない時間の使い方と言わざるを得ません。
そのため、不当な懲戒解雇を避けるためにも、最低限必要な引き継ぎを事前に用意しておくことや、引き継ぐ範囲を弁護士の退職代行を通して交渉することが重要になります。
万が一、懲戒解雇を仄めかされても、弁護士なら法的根拠を元に対処が可能なため、安心して退職を進められます。
退職後の執拗な連絡や出社要請
引き継ぎなしに突然退職すると、会社や元同僚から業務に関する問い合わせが直接入り、場合によっては出社を要請がされる可能性があります。具体的には、以下のような連絡が予想されます。
- 業務内容や進捗状況の確認
- 資料の保管場所や取引先の連絡先の問い合わせ
- 顧客情報の確認
- 緊急の案件対応への協力要請
- 引き継ぎのための出社依頼
- システムへログインするためのパスワード確認
退職代行サービスを利用する場合、基本的に「退職者への直接連絡を控えてほしい」という要望を伝えてもらえるものの、民間事業者・労働組合の退職代行(※)には法的な拘束力はなく、結果的に直接連絡が来てしまうケースもあります。
直接の問い合わせが多い場合、それぞれに対応しているとかなりの時間を使うことになり、精神的にも疲弊してしまうため、転職活動にも影響が出る可能性があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
引き継ぎに関する「交渉」を代行してもらう場合は、弁護士や団体交渉権を持つ労働組合の退職代行に依頼する必要があります。
民間の退職代行では交渉を行うことは法律上できませんので、注意しておきましょう。




同僚からの信頼を失う
退職代行を使い、引き継ぎも無しに突然職場を去った場合、残された同僚の業務負担が急増する可能性があります。その結果、残された元同僚との人間関係を著しく損なう原因となります。
一緒に働いていた同僚の信頼を失うことで、以下のようなデメリットが考えられます。
- 元同僚からの評価の低下
- 業界内での評判が悪化
- 将来的な人的ネットワークへの悪影響
- 転職時の推薦状取得が困難になる可能性
- リファレンスチェックが必要な転職先へ入社が困難
これらのリスクは、退職後の中長期的なキャリアにも影響を及ぼす可能性があるため、慎重な判断が必要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行を依頼することを検討する場合、そもそも職場環境が悪いことも考えられるため、上記のデメリットを考えたくない人もいるでしょう。
まったく違う業界へ転職する場合はキャリアへの影響も小さくなりますが、最低限必要な引き継ぎは準備しておいた方が無難といえるでしょう。


退職代行を利用して安全に引き継ぎを進めるポイント
退職代行サービスを利用する場合でも、可能な範囲で適切な引き継ぎを行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。以下では、安全に引き継ぎを進めるための具体的なポイントを解説します。
安全に引き継ぎを進めるポイント
それぞれ詳しく解説していきます。
事前に引き継ぎ書類を用意する
引き継ぎ書類を事前に準備することで、対面による引き継ぎを避けながらも、必要な情報を確実に伝えることができます。
引き継ぎ書類には主に以下の項目を含めることがオススメです。
- 担当業務の概要と進捗状況
- 重要な取引先の情報
- 定期的な業務の実施手順
- 必要な資料の保管場所
- システムやツールのアクセス情報
※担当業務によって必要な引き継ぎは異なります。
引継ぎ書類に関して「何を準備すればいいか分からない」という人もいますが、退職代行業者によっては、引き継ぎ書のテンプレートをもらえるサービスもあるため、代行業者選定時の参考にするといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
適切な引き継ぎ書類を用意しておくことで、スムーズに退職できる可能性が高まります。
不要なトラブルを避け、退職後のキャリアに集中するためにも、事前に準備を進めておくといいでしょう。


重要業務の完了を最優先する
退職前に可能な限り、担当している重要な業務を完了させておくことが望ましいです。
これにより、引き継ぎの負担が軽減されるだけでなく、会社との関係悪化も防ぐことができます。
退職代行会社を通じて引き継ぎ範囲を交渉する
退職代行サービスを通じて、会社側と適切な引き継ぎ範囲について交渉することができます。
ただし、交渉可能な範囲は退職代行会社の種類によって異なり、民間の事業者は「交渉」は出来ない点に注意しておきましょう。
退職に伴う交渉が可能な退職代行の種類は以下の通りです。
- 労働組合の退職代行
- 弁護士の退職代行
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
全ての業務において、後任者に対する完璧な引き継ぎを望まれる場合もありますが、退職時にそこまで対応することは現実的ではありません。
そのため、必要な引継ぎの範囲については、「交渉」が可能な弁護士の退職代行を通して調整する方が無難です。


労働組合型の退職代行サービスの対応可能範囲
団体交渉権が認められている労働組合が運営する退職代行サービスは、退職に伴う条件を企業と交渉することが可能です。
そのため、引き継ぎの範囲や方法について具体的な協議が可能となり、退職条件や引き継ぎ方法について、より柔軟な対応を引き出せる可能性があります。




弁護士運営の退職代行サービスの対応可能範囲
弁護士が運営する退職代行サービスでは、引き継ぎ範囲の調整を含め、様々な退職条件の交渉が可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行を使って辞めることや、引き継ぎの範囲や方法を巡り、大きなトラブルに発展しそうな場合は、弁護士へ依頼することを前向きに検討するべきといえるでしょう。


退職代行を利用時に引き継ぎが必要なケースと対応方法
退職代行サービスを利用する場合でも、状況によっては適切な引き継ぎが必要不可欠です。ここでは、特に引き継ぎの必要性が高いケースとその具体的な対応方法について解説します。
引き継ぎが必要なケースと対応方法
それぞれ、詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行には「引き継ぎが不要になる」という法的効果はありません。
退職日まで有給休暇を取得することで、引き継ぎをせずに強引に退職してしまうことも可能ではありますが、前述の通り損害賠償を含む様々なリスクが発生します。
>退職代行を使って引き継ぎをせずに辞めるリスクはこちら
そのため、基本的には退職時の状況に応じた引き継ぎを行うことがおすすめです。
就業規則で引継ぎが義務付けられている
多くの企業では、就業規則において退職時の引き継ぎについて具体的な規定を設けています。
引継ぎ完了が退職金支給の条件になっている場合、退職代行サービスを通じて、就業規則に準拠した必要最低限の引き継ぎを行うことを検討しましょう。
引き継ぎ内容は書面で整理し、退職代行業者を通じて提出することで、直接的な接触を避けながら要件を満たすことが可能になります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
たとえ就業規則に、「引継ぎの完了が退職金の満額支給条件」と定めている場合であっても、退職に伴ってよほどの不利益を生んだ場合でないと、法律上の効力はない可能性があります。
ですが、就業規則に定めている以上引継ぎが十分ではないと判断されれば、退職金の不支給、もしくは減額の方向で動くでしょう。
この際、法的な手続きを行う場合には弁護士に相談することが必要になるため、最初から弁護士の退職代行に依頼することを検討するといいでしょう。
>退職金不支給を含む代行サービス利用時のトラブルはこちらで解説




重要な取引先を担当している
会社において重要な取引先やプロジェクトを担当している場合、突然の担当者変更は取引先との関係悪化および契約解消を招く可能性があります。
このような場合、以下の情報を整理した引き継ぎ資料を用意することがおすすめです。
- 取引先の基本情報と連絡窓口
- 進行中の案件の状況と今後の予定
- 過去の取引経緯や注意点
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
顧客の信頼を損なわないためには、可能であれば対面で引き継ぎを行うことが望ましいといえます。ですが、それができるのであれば、そもそも退職代行への依頼は検討しない人も多いでしょう。
そのため、対面引き継ぎが出来ない場合は、顧客の引き継ぎがスムーズになるように、上記の情報をまとめた書類を用意しておきましょう。
会社機密情報を大量に保持している
機密情報や重要データを扱う立場にある場合、適切な情報の引き継ぎと返却が必須です。
情報漏洩のリスクを避けるため、システムアクセス権限の整理や保有書類の確実な返却が必要です。一方で、個人的なメモや資料は事前に整理し、私物と会社の物を明確に区別しておくことが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
機密情報を取り扱う仕事の場合、引継ぎが不十分であることの不利益が発生しやすく、結果的に損害賠償のリスクが高まってしまいます。
トラブルを避けるためにも、適切な引継ぎ準備をするといいでしょう。
プロジェクトの責任者を務めている
大規模なプロジェクトや重要な業務の責任者を務めている場合、引き継ぎは特に慎重に行う必要があります。
完全な引き継ぎが難しい場合でも、以下のポイントを押さえて最低限必要な対応を心がけしましょう。
- プロジェクトの現状と課題の文書化
- 重要な意思決定事項の記録
- 主要なステークホルダーの連絡先リスト
- 今後のマイルストーンと必要なアクション
このような場合、弁護士が運営する退職代行サービスを利用することで、法的リスクを最小限に抑えながら、必要な引き継ぎを進めることができます。
書面での引き継ぎを基本とし、必要に応じてリモートでの説明機会を設けるなど、柔軟な対応を検討することが望ましいでしょう。


退職代行利用時の引継ぎに関する疑問まとめ
退職代行サービスを利用する場合の引き継ぎについて、法的な観点とリスク管理の両面から解説してきました。
退職代行を利用する場合、引継ぎを行わずに強引に退職することは可能です。ですが、その場合は損害賠償を請求されるリスクがあるため、状況に応じて必要な対応を検討する必要があります。
特に重要な業務や取引先を担当している場合は、引き継ぎを完全に放棄するのではなく、書面での引き継ぎや最低限の情報提供を検討することが賢明です。これにより、退職に伴うリスクを軽減し、将来のキャリアへの悪影響を防ぐことが可能です。
退職代行サービスの選択では、引継ぎを含めた退職条件の交渉や法的対応ができる弁護士が運営するサービスを選ぶことで、より安心・安全に会社を辞めることができるでしょう。
最終的には、自身の状況と退職の理由を冷静に判断し、必要最低限の引き継ぎを行うことで、円滑な退職を目指すことが重要です。退職代行は、あくまでも退職プロセスをサポートするツールとして活用し、可能な範囲で適切な引き継ぎを行うように心がけましょう。






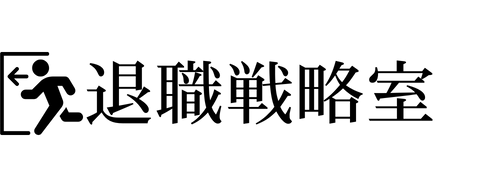
.png)







