退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれないのはなぜ?理由と対処法を徹底解説!

「1ヶ月前に退職を伝えたのに、会社が認めてくれない」
「就業規則には3か月前に退職の申し出が必要と書いてある」
このように、今の仕事を退職したくても辞められない状況に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
会社によっては、就業規則に退職に必要な期間を独自に定めているケースが多々あります。ですが、法律上、正社員は申し出から2週間、契約社員やアルバイトなどの有期雇用契約の場合は、やむを得ない理由があればいつでも退職可能です。
ではなぜ、会社側は退職を1カ月に伝えても辞めさせてくれないのでしょうか?本記事では、会社側が1カ月後の退職を認めない理由や、会社に退職を認めさせる具体的な対処方法を解説します。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれない理由
退職の意思を1ヶ月前に伝えたにもかかわらず、会社側が認めてくれないケースは珍しくありません。まずは、なぜ会社が退職を認めないのか、その背景にある理由を理解することが重要です。
上記について、それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)会社によっては、「1カ月前の退職は認めない」と主張しつつ、ズルズルと退職日を引き延ばされるケースもあるので、注意しておきましょう。


就業規則に1カ月を超える退職期間が定められている
多くの企業では、就業規則に「退職希望日の○ヶ月前までに申し出ること」という規定が設けられています。
一般的には1ヶ月前と定めている場合が多いものの、中には3ヶ月前や6ヶ月前と定めている企業も存在するため、この就業規則の規定を根拠に「1カ月後の退職は認めない」と引き留められるケースがあります。
ただし、退職後も良好な関係性を保てる円満退職を目指すなら、事前に就業規則を確認し、転職活動に悪影響が出ない範囲で会社と交渉することが望ましいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
正社員の場合、退職の申し出から最短2週間後に退職可能です。
しかし、就業規則より早く退職を目指す場合は、会社側との交渉が不可欠です。
>就業規則より早く辞める最短退職の方法はこちらで解説
法律上の権利を理解しつつ、最適な退職日で会社を辞められるように行動しましょう。


人材が不足している
慢性的な人手不足に悩む職場では、1人の退職が業務に大きな支障をきたす可能性があります。
特に、専門的なスキルを持つ人材や重要なポジションにいる人の退職は、会社にとって打撃となるため、「今辞められると困る」と強く引き止められることがあります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「人材不足だから退職を認めない」「採用できるまで待って欲しい」という主張は、非常によくある引き留め理由です。
会社側の事情は理解しつつも、退職は労働者の権利です。
引き止めに対しては、「退職の意志は固い」と毅然とした態度を示し、感情的にならずに冷静に対応することが重要です。
人材不足が解消されてから退職しようとすると、いつまでたっても辞められず、新しい仕事への挑戦がドンドン遅れてしまうため注意しておきましょう。


引き継げる後任者がいない
自分の担当業務を引き継げる人材がいない場合、「後任が見つかるまで待ってほしい」と言われることがあります。
専門性の高い業務や、一人で担当している業務の場合は、引き継ぎの問題が退職の大きな障壁となることがあります。
後任者がいなくても、事前に業務マニュアルを作成したり、引き継ぎ期間を明確に伝えることで、スムーズな退職を実現することが可能です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
後任者の採用や育成をはじめとした人員計画と実行は、あくまで会社側の責任であり、それを理由に退職希望者を引き止めることはできません。
「後任が見つかるまで」という引き止めを鵜呑みにすると、その間に他の退職者が出てしまい、「いつまでたっても退職できない」ということになりかねないため、注意しておきましょう。




離職率を上げたくない
企業イメージに直結する「離職率」の数字を上げたくないという理由から、退職を認めたがらないケースもあります。
特に、就職四季報に離職率が掲載される有名企業においては、新卒採用の競争力を高めるためにも、離職率を上げたくないという考えが強くなりやすいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
冷たい言い方になってしまいますが、退職を決意した人が会社の離職率を気にする必要はありません。
退職の意志をはっきり伝え、自分の将来のキャリアを最優先に考えましょう。
上司が自分の評価が下がることを懸念している
部下の退職が上司自身の評価に影響するケースも少なくありません。
特に、人手不足の企業や労働集約型のビジネスモデルの業界では、管理職の評価指標に「部下の離職率」が設定されていることもあります。
このような場合、直属の上司を通さず、人事部や、さらに上位の管理職に直接退職の意思を伝えることも検討する必要があるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
上司の都合で退職を引き延ばされるのは理不尽なことです。
しかし、関係性を悪化させないようにするためには、「キャリアアップのため」や「新たな挑戦をしたい」といった前向きな退職理由を強調し、スムーズに退職を進めましょう。
雇用契約の期間中のため
契約社員や派遣社員など雇用期間が定められている場合、原則として「契約期間中は退職できない」という理由で退職を認めないケースがあります。
また、1年を超える雇用契約において1年以上働いた後や、会社の合意が得られた場合はいつでも退職できることも覚えておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
有期契約の場合、基本的には契約期間満了を待つのが無難ですが、事情によっては会社側と交渉して合意退職を目指すことも可能です。
特に、やむを得ない事情がある場合は早めに上司へ相談し、円滑に退職を進める方法を検討しましょう。




退職に必要な期間は雇用形態で異なる
会社を辞める際、退職に必要な期間は雇用形態によって異なります。
特に、正社員をはじめとした「無期雇用」と、契約社員や派遣社員などの「有期雇用」は退職に関する法律が異なるため、適切な手続きを踏むことが大切です。
ここからは、雇用形態によって異なる退職に必要な期間や注意点について、以下の通り解説していきます。
正社員の場合は申し出から2週間で退職可能
正社員をはじめとした雇用期間の定めがない労働者(無期雇用)の場合、法律上「退職の申し出から2週間経過すれば退職できる」と定められています。
しかし、会社の就業規則に定められた退職予告期間を根拠に退職を引き止められることは多く、会社の要望を無視して退職を強行すると、不要なトラブルに発展する可能性もあります。
できるだけトラブルを回避するためには、就業規則に定められた期間を尊重しつつ、転職活動や将来のキャリアに悪影響が出ない退職日を交渉するようにしましょう。
特に、引き継ぎが複雑な業務を担当している場合は、円満退社のためにも余裕を持った期間設定が望ましいといえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
無期雇用契約の場合、法律上は2週間で辞められますが、円満退職を目指すなら、可能な限り1ヶ月前に申し出て業務の引継ぎを適切に行うのが望ましいといえるでしょう。
ただし、就業規則で「3~6ヶ月」と極端に長い退職予告期間を設定している場合がありますが、これに従うと納得のいく転職活動を行うことが難しくなります。
就業規則の退職予告期間は把握しつつも、自身のキャリア設計や目標を優先し、退職日の交渉を行うようにしましょう。


契約社員の場合は一定の条件を満たせばすぐに退職可能
雇用期間が定められている契約社員(有期雇用契約)の場合、原則として契約期間が満了するまでは退職できません。しかし、以下の条件に該当する場合は例外的に退職が認められます。
- 退職のやむをえない理由がある場合(具体例は以下参照)
- 職場のハラスメントやいじめ
- 労働条件の相違
- 健康上の理由で働けなくなった
- 会社が合意している場合
- 1年を超える契約において1年以上経過している場合
特に「やむを得ない理由」がある場合は、会社の合意得られなかったとしても、即時退職できる可能性が高いでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
契約社員として働く場合は、契約期間満了を待たずに退職するハードルが高いことを理解しておくことが重要です。
「退職のやむを得ない理由」が無く、会社の合意も得られない場合は、期間満了まで辞められない場合もあるため注意しておきましょう。
早めに退職を考えている場合は、契約更新のタイミングで話を進めたり、退職交渉をスムーズに進めるための準備をすることをおすすめします。


派遣社員やアルバイトの場合はいつでも辞められるのか?
派遣社員やアルバイトにおいても、有期雇用契約の場合はいつでも退職できるわけではありません。
派遣社員の場合、雇用契約は派遣会社(派遣元)と結んでいるため、派遣先の意向だけで退職を止められることはありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
人材派遣会社にとっては、派遣社員の退職は売上低下に直結するため、しつこく引き止めを受ける場合があります。
どうしても派遣会社の担当者を説得できない場合は、労働基準監督署や退職代行サービスへの相談も検討するようにしましょう。
これに対し、基本的に有期雇用契約となるアルバイトやパートも同様に退職を認められない場合がありますが、担当している仕事の重要度次第では、会社の退職合意を得られるケースが多いでしょう。




退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれない場合の対処法
退職日の1ヶ月前に辞めることを伝えたにもかかわらず、会社側から引き止められたり、退職を認めてもらえないケースは少なくありません。
退職の意思を伝えても在職を強要される場合、どのような対処法があるのでしょうか。具体的な対処法は以下の通りです。
辞めさせてくれない場合の対処法
それぞれ具体的に解説していきます。


上司を介さず人事部門との直接交渉を行う
直属の上司が感情的に退職を認めない場合、人事部門に直接相談するという選択肢があります。
特に、上司個人の評価を守るために引き止めをしているケースでは、上司とだけ交渉を続けると退職がスムーズに進まないことがあります。強硬な引き止めを受ける場合は、人事部門の担当者にも相談するようにしましょう。


退職届を内容証明郵便で送付する
退職届を提出しても受け取ってもらえない場合や、「受け取っていない」と言われる可能性がある場合は、内容証明郵便で送付するという方法があります。
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便サービスです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
内容証明郵便で退職届を送る方法は、法律上、退職の権利がある正社員の場合や、退職のやむを得ない理由がある契約社員などの場合に有効な方法といえるでしょう。
労働基準監督署へ相談する
会社がどうしても退職を認めず、違法な引き止めを行っている場合は、労働基準監督署に相談することがおすすめです。
労働基準監督署からのアドバイスを受けることで、適切な対応方法を知ることができます。場合によっては会社側に指導が入ることもあるため、確実な退職が実現できるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「退職を認めない」「損害賠償を請求する」といった退職拒否を受けて仕事を辞められない場合は、労働基準監督署に相談することで、会社側にプレッシャーをかけることができるため、状況が改善される可能性が高いでしょう。
さらに、具体的な証拠(メールや録音)を持参すると、より効果的な対応をしてもらえる可能性が高まります。


退職代行サービスを使って辞める
直接上司に退職を申し出ることが精神的に辛い場合や、ハラスメントなどで職場環境が著しく悪い場合には、退職代行サービスを使って辞めることも選択肢の一つです。
- 退職の意思表示を代行してくれるため、直接の対面や交渉が不要
- 退職に必要な手続きのアドバイスが受けられる
- メンタル面での負担が軽減される
ただし、弁護士や労働組合の退職代行以外は、退職に伴う各種交渉権がないため、給与や有給休暇の交渉などはできない点に注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職届を受け取ってもらえない場合や、上司からパワハラを受けていて精神的に直接台北を言い出せない場合は、退職代行サービスを利用しましょう。
弁護士や労働組合の退職代行に依頼すれば、退職日の調整や有給休暇の取得交渉まで代行してもらえるため、安心して退職を進めることが可能です。
>おすすめ退職代行の厳選比較はこちら


有期雇用契約の期間中の場合は「やむを得ない退職理由」を伝える
契約社員や派遣社員、アルバイトなどの有期雇用契約で働いている場合、「やむを得ない理由」があれば契約期間中でも退職が認められます。そのため、この「やむを得ない理由」を適切に伝えることが重要です。
- 職場のハラスメントやいじめ
- 契約時と実際の労働条件が大きく異なる
- 家族の介護が必要になった
- 体調不良で仕事を継続することができない
上記のような理由を具体的かつ客観的に説明することで、契約期間中でも退職が認められる可能性が高まります。




1ヶ月前に伝えても退職が認められないパターン別の対処ポイント
退職の意思を1ヶ月前に伝えたにもかかわらず、会社側から引き止められたり、退職を認めてもらえなかったりするケースは少なくありません。
そこで、ここからは以下の引き止めパターン別の対処ポイントを解説していきます。
パターン別の対処ポイント
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職の申し出を1ヶ月前に行っても、上記のように様々な理由で引き止められるケースがあります。
しかし、法律の知識を持ち、冷静に対処すれば、スムーズな退職は十分可能です。
退職は人生において重要な転機です。
自分のキャリアを守るために、適切な対策を講じるようにしましょう。
「繁忙期だから待って」と言われた場合の対応
企業にとって繁忙期は、業務が集中し、人手不足が深刻になるタイミングです。そのため、「忙しい時期に辞められると困る」といった理由で、退職を先延ばしにされることがあります。
この場合、まずは会社の繁忙期がいつまで続くのかを明確にしましょう。「繁忙期が終わるまで」というあいまいな条件ではなく、具体的な日付を設定することが重要です。その上で、自分の希望する退職日と折り合いをつけるか検討します。
もし退職日を妥協できるなら、円満退社のためにも柔軟に対応することも一つの選択肢です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「繁忙期だから」という理由で無期限に退職を引き延ばすことは、労働者には退職の自由を侵害する行為です。
繁忙期を考慮しつつも、自分のキャリアを最優先にすることが重要です。
「引き継ぎが終わってから」と引き延ばされる場合の対策
退職時に「業務の引き継ぎが完了するまで辞められない」と言われることがあります。特に、業務が属人化している職場では、この理由で長期間引き止められることもあります。
業務引き継ぎを理由に退職日を伸ばされそうになった場合は、以下の手順で計画的に引き継ぎを進めましょう。
- 担当業務を洗い出し、引き継ぎに必要な期間を見積もる
- 具体的なスケジュールを立てて会社側に提案する
(退職日までに引き継ぎが完了するスケジュールにする) - 引き継ぎマニュアルや手順書を作成する
このように主体的に引き継ぎ計画を提案することで、「引き継ぎが終わらない」という曖昧な理由での引き延ばしを防ぐことができます。
また、引き継ぎ資料は電子データとして保存し、必要であれば退職後もメールで質問に答えられる旨を伝えるなど、柔軟な対応を示すことも効果的です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
現実的に「会社が認める完璧な引き継ぎ」が退職時に実現できることは少なく、退職日までに終わらせられるように計画することが重要です。


「1か月で辞めるなら損害賠償を請求する」と脅された場合の対応
退職を申し出たときに「突然辞められると損害が発生する」「1ヶ月で辞めるなら損害賠償を請求する」と脅される場合があります。ですが、基本的にこれは職権乱用であり、正当性が認められることは非常に少ないといえるでしょう。
賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
万が一、退職申し出時に損害賠償請求や懲戒解雇などで脅された場合、以下の対応を検討しましょう。
- 冷静に「退職は労働者の権利であり、それだけで損害賠償の対象にはならない」と伝える
- 会話を録音するなど証拠を残しておく
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士の退職代行に依頼する
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
労働者に責任が認められるごく一部のケースを除き、通常の退職で損害賠償請求が認められることはほとんどないため、不当な脅しに惑わされないようにしましょう。




「契約期間中は辞めれない」と告げられた場合
契約社員や派遣社員などの有期雇用契約の場合、「契約期間が満了するまで退職は認められない」と言われ、1カ月前の申し出では退職できないことがあります。
そのため、「契約期間中は辞められない」と言われた場合は以下のポイントをチェックするようにしましょう。
- 「やむを得ない退職理由」に該当するか検討する
(健康上の理由、労働環境の著しい悪化など) - 契約期間が1年を超える場合は、1年経過後の退職の権利を伝える
- それでも認められない場合は、労働基準監督署や退職代行に相談する
雇用契約期間中であったとしても、絶対に退職する方法がないわけではありません。法律上の退職ルールを確認した上で、退職の交渉に臨むようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
特に契約期間中の派遣社員の場合は、派遣会社の担当者から激しい引き止めを受ける可能性があります。
そのため、退職の際は作戦を練ったうえで伝えるように心がけましょう。




退職時に損をしないための確認事項
退職を決意した際、円満に辞めることだけでなく、金銭的・制度的な面でも損をしないように準備をすることが重要です。退職時に確認すべき具体的な事項は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
未消化の有給休暇を計画的に消化する
有給休暇は労働者の権利であり、退職を理由に消化を拒否されることはあってはなりません。
労働基準法第39条5項では「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない」と定められており、退職が決まっている場合でもこの権利は有効です。
有給休暇を確実に消化するためのポイントは以下の通りです。
- 残りの有給休暇日数を確認する
- 退職日までの期間を考慮して計画的に申請する
- 「退職前だから」という理由で拒否された場合は労働基準監督署へ相談する
- 引き継ぎを優先すると有給消化できない場合は、会社側へ有給買取を打診する
退職を円満に進めるためには、業務の引き継ぎに支障が出ないよう配慮しながら計画的に有給休暇を消化することが望ましいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
一部のブラック企業では「退職時の有給消化は認められない」「退職の時は、ふつうは有給使わないものだよ」といった独自の主張を受ける可能性がありますが、これは法的に認められません。
転職活動や、転職先の準備の時間を確保するためにも、有給休暇は確実に消化するようにしましょう。




未払いの残業代や給与を確実に回収する
退職時には、未払いの残業代や給与を確実に回収することも重要です。
特に、サービス残業が常態化している企業では、未払い賃金が発生している可能性がありますが、労働基準法第24条では、賃金は全額を労働者に支払うことが義務付けられています。
未払い賃金を確実に回収するポイントは以下の通りです。
- 残業時間の記録を保管しておく
- 給与明細を確認し不足があれば会社に請求する
- 退職日までの働いた分の給与を確認する
- 支払われない場合は労働基準監督署に相談する
退職を申し出た際、「辞めるなら給与は払わない」などと言われても、それは明らかな法律違反です。給与の未払いが発生しそうな場合は、労働基準監督署や、弁護士の退職代行に相談するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職後に未払い給与や残業代を請求するのは手間がかかるため、退職前に請求し、話し合いで解決できるのがベストです。
直接交渉することが難しい場合は、労働基準監督署に相談することも考えましょう。


退職金や保険の手続きを確認する
退職金の有無や、健康保険・年金などの手続きを確認することも重要です。特に、会社の健康保険から国民健康保険への切り替えや、企業型確定拠出年金(DC)の扱いについては、事前に確認が必要です。
自己都合退職に比べ、会社都合退職で退職した場合の方が失業給付の受給に当たって優遇される点が多くなるため、必ずチェックしておきましょう。
1ケ月でスムーズな退職を実現するためのアプローチ
退職を円満に進めるためには、計画的なアプローチが重要です。1ヶ月という期間でスムーズに退職するためのポイントは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
会社とのやり取りを記録する
退職に関する会社とのやり取りは、すべて記録に残しておくことが重要です。特に口頭でのやり取りはトラブルの原因になりやすいため、メールや書面でのコミュニケーションを心がけましょう。
- 退職の意思を伝えた日時と相手
- 重要な会話の後はメールで「本日お話しした内容の確認です」と要点をまとめる
- 退職に関する書類のコピーを取る
- 退職が認められないなどの場合は会話を録音する
(ただし、相手に録音していることを伝えることが望ましい)
これらの記録は、退職を巡って万が一トラブルになった場合の証拠として役立ちます。特に「言った・言わない」の水掛け論を防ぐためにも重要です。
期限を明確にして退職交渉を進める
退職の交渉では、常に具体的な期限を設定し、それに向けて行動することが大切です。曖昧な表現や態度は、期限を区切ることで、無期限の引き延ばしを防ぎ、退職手続きを確実に進めることができます。
- 「○月○日に退職させていただきます」と具体的な日付を伝える
- 「検討します」「考えておきます」といった曖昧な返答は避ける
- 会社側の提案に対しても、即答せずに「検討して○日までに回答します」と期限を区切る
退職は労働者の権利であることを念頭に置き、自分の意思を明確に伝えることで、1ヶ月という期間でもスムーズな退職を実現することが可能です。
退職願いではなく退職届を提出する
退職の意思を伝える書類には「退職願」と「退職届」の2種類があります。
「退職願」はその名の通り会社に退職を願い出るものなので、受理されなければ効力が発生しません。一方、「退職届」は退職の意思を通告するもので、会社の承認を必要としません。
退職届を受け取り拒否される場合などは、内容証明郵便で送付するなど、確実に届いたことを証明できる方法を選びましょう。


退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれない場合のよくある疑問
「退職を1カ月前に伝えても辞めさせてもらえない!」という状況に直面している人や、退職を伝えるタイミングに悩んでいる人の良くある質問について、以下に解説していきます。
就業規則に「退職は3か月前に申し出が必要」と記載されているのですが?
就業規則に「退職は3か月前に申し出が必要」と記載されていても、民法上は、雇用期間の定めがない労働者の場合、2週間前の申し出で退職が可能です。ただし、極端に長い予告期間でなければ、できるだけ就業規則に従うことがトラブル回避につながります。
合理的な範囲を超える規定(例:6ヶ月前など)であれば、転職活動や次の仕事の入社日を優先し、退職日を伝えるようにしましょう。
1ヶ月前に退職を申し出ても会社側が認めないことは違法ですか?
雇用期間の定めがない労働者が、2週間前に退職の申し出をしているにもかかわらず、会社側が認めないことは違法です。憲法で保障された職業選択の自由には「辞める自由」も含まれており、会社がそれを制限することはできません。
ただし、引き留めのための説得自体は違法ではなく、最終的な選択権は労働者にあります。退職の引き止めを受けた場合は、感情だけで判断せずに、中長期的なキャリア設計に基づいて適切な選択肢をとるようにしましょう。
試用期間中でも申し出から1か月で辞められますか?
試用期間中であっても、雇用契約によっては1カ月で退職可能です。
雇用期間の定めがない正社員などの場合は、試用期間であっても2週間前の申し出で退職が可能です。
これに対し、契約社員などの有期雇用契約の場合、原則として期間満了までの勤務が必要になります。ただし、「やむを得ない事由」がある場合は即時退職も可能です。
1ヶ月前に退職を申し出た場合も有給休暇は使えますか?
1ヶ月前に退職を申し出た場合でも、有給休暇を使用する権利は労働基準法で保障されています。
「退職前だから」という理由だけで有給休暇の使用を拒否することは違法であり、認められません。
「1カ月では引き継ぎが出来ないので損害賠償を請求する」と言われましたが、どうすればいいでしょうか?
「1か月では引き継ぎができないので損害賠償を請求する」という法的根拠がないケースがおおく、単なる脅しの可能性があります。
労働基準法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められており、就業規則や雇用契約書に定めがあったとしても、単に退職したことを理由に損害賠償を請求することはできません。
退職時に損害賠償を仄めかされた場合は、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれない理由と対処法まとめ
退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれない状況は、多くの働く人が直面する悩みです。
ですが、正社員などの無期雇用規約の場合は、2週間前の申し出によって退職できることが民法で定められており、1カ月前に伝えれば問題なく退職可能です。また、契約期間中の有期雇用社員であっても、「やむを得ない退職理由」があれば、いつでも退職することができるため、条件さえそろえば1カ月前の申し出によって退職することができるでしょう。
適法に退職を進めようとしているにも関わらず、会社側が「退職を認めない」等の不当な引き止めを行う場合は、労働基準監督署や退職代行サービスの利用も検討するといいでしょう。
退職は新たなキャリアへの第一歩です。本記事で紹介した対処法を参考に、退職を決意した会社にズルズルと引き止められることを防ぎ、いち早く次の職場で活躍する為の準備を始めましょう!




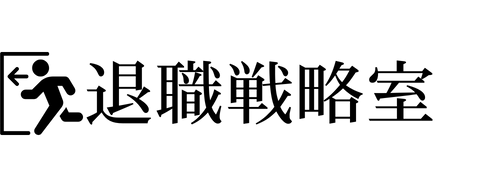
.png)


