【社労士監修】退職時の有給消化はどこまで可能?使い切るコツやトラブルへの具体的な対処法も解説

退職を決意した人にとって、残っている有給休暇をどのように消化するかは悩みのタネのひとつです。
特に、これから新しい仕事に転職する場合、リフレッシュやスキルアップの時間を確保するためにも、有給休暇はできるだけ使い切りたいと考えている人も多いでしょう。
退職を申し出た場合であっても、退職日までに有給休暇を使用する権利は法律で保障されていますが、実際の申請や会社との調整に不安を感じる方もいるようです。
そこで、本記事では、退職時に有給を消化して使い切るための具体的な方法や、トラブルが発生した際の対処法を解説していきます。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/

退職時に有給消化はできるのか
退職を決意した際に気になるのが、残っている有給休暇をどうするかという問題です。せっかく付与されている有給休暇を無駄にしたくないと考える人は多いものの、「退職が決まってからも使えるのか」と不安になっている人も多いでしょう。
ここからは、退職時の有給休暇の取得における法定ルールは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
退職が決まっても有給休暇を使える
有給休暇は、6か月以上継続して勤務し、全労働日数の8割以上出勤した全ての労働者に対して付与されます。
一部のブラック企業や上司によっては、「うちは有給休暇が無い」「退職者は有給使えない」など、法律を超えた独自のルールを設定している場合がありますが、法律上は無効といえるでしょう。
もしも、「有給休暇が残っているのに使わせてくれない」と悩んでいる場合は、最寄りの労働基準監督署や、退職代行サービスへ相談するといいでしょう。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)退職時に有給休暇取得に躊躇する人は少なくありません。
ですが、退職時こそ残っている有給休暇を消化するチャンスと捉えることができます。
転職の準備や心身のリフレッシュ、家族との時間など、次のステップに向けて貴重な時間として活用するようにしましょう。


有給休暇は退職日までに使い切る必要がある
退職届を出した後でも有給休暇を取得することは可能ですが、「退職日」以降に取得することはできません。
例えば、3月31日が退職日であれば、その日までに有給休暇を消化しなければなりません。
未消化の有給休暇があったとしても、会社側に買取りなどの義務はないため、使わなければ無駄になってしまいます。そのため、退職を決めたら、残りの有給日数を確認し、計画的に消化することが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を決めたら、業務の引き継ぎ計画と共に、有給休暇を使い切れるように計画を立てるようにしましょう。
退職時の有給休暇取得を会社は拒否できない
前述したように、有給休暇の取得は労働者の権利であり、「忙しいから」「引継ぎがあるから」という理由で、会社が退職時の有給休暇取得を拒否することはできません。
何故なら、労働基準法において、有給休暇は「労働者の請求する日に与えなければならない」と定められているからです。
参照:e-GOV 法令検索「労働基準法第39条」
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
正当な理由なく有給休暇の取得を会社側が拒否した場合、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります。
参照:e-GOV 法令検索「労働基準法第119条」
そのため、大半の会社において、退職時であっても問題なく有給休暇の消化ができるでしょう。


退職時に最大40日の有給を消化可能
フルタイムで働く労働者の場合、6か月勤務後は10日間の有給休暇が付与されます。その後、1年ごとに有給休暇の付与日数は増えていき、最大20日間付与されます(以下表を参照)。
| 継続勤務年数 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給付与日数/年 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
6年半経過後は、毎年20日間の有給休暇が付与
参照:e-GOV 法令検索「労働基準法第39条」
フルタイム以外の有給付与日数はこちら
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給付与日数/年 | 4日 | 169~216日 | 6カ月 | 1年6カ月 | 2年6カ月 | 3年6カ月 | 4年6カ月 | 5年6カ月 | 6年6カ月 |
| 3日 | 121~168日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
| 2日 | 73~120日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
ただし、実際には業務の引継ぎ状況、退職のタイミングなどによって、すべての有給休暇を消化できるとは限りません。例えば、突然の退職や、引継ぎに時間がかかる場合は、現実的にすべての有給を消化するのが難しいこともあるでしょう。
そのため、有給休暇を無駄にしないようにするためには、できるだけ早めに退職の意向を伝え、引継ぎと有給消化のバランスを取りながら、計画的に有給休暇を消化することがおすすめです。
長期間勤務して有給が多く残っている場合は、特に計画的な準備が必要になるため、注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職前に有給休暇を計画的に取得することが、円満な退職につながります。
特に長期間の有給休暇を取得する場合は、早めに会社と調整し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
なお、前述の通り有給休暇が付与されるのは基本的に「6カ月勤務後(※)」となるため、試用期間中に退職する場合は有給消化はできないため、注意しておきましょう。
※一部の企業ではより早く有給を付与する制度があるので要確認


退職時に有給消化して使い切る7つのコツ
退職が決まったら、残っている有給休暇を最大限活用したいと考えている人が多いでしょう。
しかし、職場の状況や引き継ぎの進捗によっては有給を使用することが心苦しくなってしまうケースもあるでしょう。
そこで、ここからは有給休暇を効果的に使い切るための7つの具体的な方法をご紹介します。
残っている有給休暇日数を正確に確認する
有給休暇を使い切るためには、まずは残っている有給休暇の日数を正確に把握することです。
前述の通り、有給休暇は6か月以上、かつ所定労働日の8割以上出勤しているすべての会社員に付与され、最大で40日分の有給休暇が残っている可能性があるため、正確に把握したうえで取得計画を立てるようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ごく稀に「ウチに有給休暇の制度は無い」と主張するブラック企業もありますが、法律上、一定の条件を満たせばすべての労働者に有給が付与されます。
契約社員やアルバイト・パートの場合でも、出勤日数に応じた有給休暇が付与されるため、必ずチェックしましょう。
退職日から逆算して計画を立てる
有給休暇日数を確認したら、次は退職日から逆算して計画を立てましょう。
これを踏まえ、退職日までに有給休暇を取得するには以下の3つのパターンが考えられます。
- 最終出社日以降にまとめて取得
- 退職日と最終出社日を同日にし、分散して有給取得
- 分散して有休を取得しつつ、残りを最終出社日以降にまとめて取得
たとえば、有給休暇が20日残っている人が3月31日に退職予定の場合、3月上旬に最終出社日を設定し、それ以降にまとめて有給消化期間とすることができます。
もしくは、最終出社日を退職日とし、退職日の前に分散して有給休暇を取得することも可能です。
いずれの場合においても、引継ぎにかかる時間や次の就職先の入社日なども考慮して、自分に最適なスケジュールを組みましょう。早めに計画を立てて会社側に共有することで、より円滑に退職を進めることができるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
有給休暇の計画は、退職後の生活設計にも影響を与えます。
転職活動やスキルアップ、休息の期間を確保するためにも、有給は計画的に消化しましょう。
早めに退職の意向を伝える
有給休暇をスムーズに消化するためには、できるだけ早く退職の意向を伝えることが重要です。
一般的には、退職希望日の1〜2ヶ月前までに上司に相談するのがマナーとされていますが、会社によっては就業規則で「退職3か月前の申し出」を定めている場合もあります。
ただし、退職の意向を伝える際は、退職理由や今後のキャリアプランを整理しておくことも大切です。明確な理由があれば、上司や人事担当者との話し合いもスムーズに進みやすいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を決意した際は早めに申し出ることが望ましいですが、法律上、正社員の場合は退職申し出から2週間で退職可能です。
そのため、転職を急いでいる場合や、有給休暇が残っていない場合は最短退職を検討してもいいでしょう。




引継ぎスケジュールを具体的に示す
退職時の有給休暇の取得に対し、会社側が難色を示す理由の一つが「業務の引継ぎ」です。
このような事態を避けるためには、事前に具体的な引継ぎ計画を作成し、業務に支障が出ないようにすることで、有給取得が円滑になります。なお、引き継ぎ計画には、以下の内容を含めると良いでしょう。
- 引継ぎ期間の全体像
- 業務ごとの引継ぎ担当者
- 重要な業務の締切や年間スケジュール
このように引き継ぎの計画や概要を共有することで、「引継ぎが不十分だから有給は取れない」という事態を防ぐことができます。
また、実際に引継ぎを進める際には、マニュアルを作成したり、後任者と一緒に業務を行ったりするなど、丁寧な対応を心がけましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
引継ぎを適切に行うことは、円満退職につながります。
退職後の人間関係や将来的なリファレンスチェックにも影響するため、計画的に進めるようにしましょう。




有給消化の予定を記録に残る形で申請する
有給休暇の消化予定は、必ず記録に残る形で申請しましょう。
近端管理システムやメールでの申請、書面での提出など、会社の規定に沿った方法で正式に有給取得手続きを行うことが重要です。
申請の際には、最終出社日と退職日を明確に示し、その間の有給消化予定を詳細に記載しましょう。また、有給消化中の緊急連絡先も伝えておくと、万が一の際にもスムーズに対応できます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
とんでもないブラック企業の場合、有給を取得したにも関わらず欠勤扱いにされてしまい、退職後に最後の給与振り込み時に気づくこともあります。
その際は、最寄りの労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談するようにしましょう。
有給を消化しきれない場合は買い取りを打診する
どうしても有給休暇をすべて消化できない場合は、会社に買取りを打診するという選択肢もあります。
就業規則に買取りの規定があるかどうかを確認し、人事部や上司に相談してみましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
買取りを打診する際は、まずは有給消化を第一希望としつつ、業務の都合や引継ぎの状況から難しい場合の代替案として提案するのがスマートな流れといえるでしょう。
労働基準法の基礎知識を押さえる
最後に、有給休暇を無駄なく使い切るためには、労働基準法に基づく基礎知識を押さえておくことも重要です。自分の権利を知っておくことで、不当な対応に対して適切に主張することができます。
有給休暇に関する主な法的ポイントは以下の通りです。
- 有給休暇は労働者の権利であり、原則として取得時期を自由に選べる
- 会社側の「時季変更権」は、業務の正常な運営を妨げる場合に限定される
- 退職が決まっている従業員に対しては、時季変更権の行使は難しい
- 有給休暇は付与日から2年で時効となり消滅する
- 退職時の未消化分は買取りが認められる場合があるが、会社に買取義務はない
- 有給休暇を取得できるのは所定労働日だけであり所定休日(労働義務のない日)は取得できない
(例:土日が所定休日の場合は土日を有給休暇取得日に充てることは出来ない)
これらの知識を持っていれば、会社との交渉も自信を持って行えるでしょう。ただし、権利を主張するだけでなく、円満退職を目指して誠実に対応することも大切です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
法律知識があるだけで、有給取得に関する不当な扱いを受けにくくなります。
ただし、会社が法律を超える独自のルールを持ち出し、有給休暇の取得ができない場合は、労働基準監督署に相談するといいでしょう。
また、退職そのものを認めてくれない場合には、労働組合や弁護士が行っている「交渉権」を持つ退職代行に依頼することで、有給休暇の取得交渉も代行してもらえるため、困った際にはチェックしておきましょう。
>おすすめの退職代行サービス比較はこちら




退職時の有給消化は最終出社日の前後どちらがいい?
退職時の有給休暇を消化する際、多くの人が「いつ有給休暇を取得すべきか」という悩みを抱えます。
大きく分けると、最終出社日の前に消化するパターンと、最終出社日の後に消化するパターンの2つが考えられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
最終出社日より前に有給消化する場合のメリットとデメリット
最終出社日前に有給休暇を消化する場合、退職申し出から退職日までの期間に分散して有休を取得することが一般的です。
この場合のメリット・デメリットはそれぞれ以下の通りです。
最終出社日前までに分散して有給休暇を取得する場合、引き継ぎ完了までのスケジュールに余裕が生まれる点が大きなメリットの一つです。特に、後任者がまだ決まっていない場合において、会社側にとってありがたい有給消化方法といえるでしょう。
ただし、有給休暇が大量に残っている場合においては、最終出社日までに全て消化しきることは現実的ではないため、注意しておきましょう。
最終出社日後に有給消化するメリットとデメリット
退職時の有給消化の最もよくあるパターンとしては、最終出社日以降から退職日までにかけてまとめて取得する方法です。
この場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
最終出社日後の有給消化は、円満な引継ぎを重視する場合や、退職後にまとまった休日が欲しい人に向いているといえるでしょう。
引き継ぎと転職のスケジュールに合わせて有給消化するのがおすすめ
結局のところ、どちらのパターンが良いかは、個人の状況や優先事項によって異なります。以下のポイントを考慮して、自分に合った方法を選びましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
基本的には、自分自身の転職活動や、内定が決まっている場合は入社準備のための学習を優先して考えるようにしましょう。
転職活動の進捗で考える
転職先の有無と入社日転職先が決まっている場合は、新しい職場の入社日から逆算して計画を立てることが重要です。
入社日までに十分な休息期間を確保したい場合は、最終出社日後に有給を消化するのがおすすめです。一方、転職活動中であれば、最終出社日前に有給を消化して転職活動に充てるという選択肢もあります。
引き継ぎ計画に配慮する
引継ぎの状況担当業務の複雑さや後任者の有無によって、引継ぎにかかる時間は大きく異なります。
重要なプロジェクトを抱えている場合や、専門性の高い業務を担当している場合は、引継ぎを優先して最終出社日後にまとめて有給を消化するといいでしょう。
また、引継ぎ完了後に一部の有給を前倒しで取得するという折衷案も検討できます。


心身の状況を考慮する
退職を決意するほど現在の職場に不満や負担を感じている場合は、早めに今の職場から離れるためにも最終出社日前から有給消化を開始することで、心身のリフレッシュを図れるかもしれません。
最終的には、会社との円満な関係を維持しつつ、自分自身にとっても最適な選択をすることが大切です。有給消化の計画を立てる際は、上司や人事部とよく相談し、お互いにとって納得のいくスケジュールを組みましょう。
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
また、健康保険の傷病手当金の受給を考える場合は、在職中に受診して退職日に傷病手当金を受給できる状態で無いと、資格喪失後の継続給付(退職日まで1年間の健康保険加入歴が必要)を受給できないため注意しましょう。
退職時の有給消化でよくあるトラブルと対処法
退職時に有給休暇を消化しようとすると、思わぬトラブルに直面することがあります。
法律上は労働者の権利として保障されているはずの有給休暇ですが、実際の職場では様々な理由で取得が難しくなるケースも少なくありません。
ここでは、退職時の有給消化に関する以下のよくあるトラブルと、その対処法を具体的に解説します。
有給消化を拒否された時の具体的な対応
一部のブラック企業では、「人手不足だから」「退職決まったら有給は認めない」などの理由で有給休暇の取得を拒否されることがあります。
有給休暇の取得は法律(労働基準法)で認められた権利であり、会社独自のルールによって一方的に拒否することはできません。このように有給休暇消化を拒否された場合は、以下の方法で対応しましょう。
- 直属の上司ではなく、人事部門に相談する
- メールや書面で有給休暇申請を行い記録に残す
- 業務の引継ぎ計画を具体的に示して懸念点を解消する
- 労働基準監督署に相談する
有給消化を拒否された場合は、単なる感情的な反応なのか、業務上の具体的な問題があるのかを把握することが重要です。そのうえで、人事部門への相談や引き継ぎ計画の共有などを行い、有給消化に納得してもらうようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「有給消化をやめて欲しい」「退職時に有給使う人いないよ」と遠回しに有給消化を拒否される場合がありますが、基本的に無視して問題ありません。
有給休暇の取得を拒否されるケースは、会社側の管理体制や文化が影響していることが多いです。
特にブラック企業においては、社員の権利を軽視する傾向があるため、転職の際はよりよい企業文化の会社を選ぶようにしましょう。


引き継ぎを理由に有給消化を制限された場合の交渉
退職時には業務の引継ぎが必要ですが、「引継ぎが終わっていないから有給は取れない」という理由で制限されることも少なくありません。この場合は以下の交渉が有効です。
- 引き継ぎの計画を事前に共有する
- 引き継ぎ期間中は週1〜2日の有給取得にとどめる
- 重要な引継ぎが完了した後に、まとめて有給を消化する
- 引継ぎ資料を事前に作成し、質問があればメールで対応する
こうした提案により、会社側も安心して有給消化を認めやすくなります。有給取得に伴う交渉は対立ではなく、双方にとって納得のいく解決策を探る過程だと捉えましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
円満退職を目指すためには、引継ぎを適切に行うことが重要ですが、企業側の理不尽な要求には毅然と対応することも大切です。
有給休暇の取得は転職活動や転職後のキャリアにも影響を与えるため、冷静かつ計画的に対応しましょう。
有給休暇を申請したのに欠勤扱いになっていた場合の対処法
有給休暇を申請したにもかかわらず、欠勤扱いになっていた場合、給与が減額されるなどの不利益を被る可能性があります。このような事態に気づいたら、すぐに以下の対処を行いましょう。
- 給与明細と有給申請内容を再度確認
- 給申請の記録(メールや申請書の控え)を保管
- 上司や人事部に確認
- 労働基準監督署に相談する
そのうえで、会社側へ確認を行い、それでも是正されない場合は労働基準監督署へ相談するようにしましょう。
特に退職時の有給消化の有無は、最終的な受け取り給与に影響するため、早めの対応が重要です。給与明細をしっかりチェックし、不明点があればすぐに確認するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
企業が有給申請を無視して欠勤扱いにするのは、本来、絶対にありえないケースです。
このような対応をされる可能性について事前に気づいた場合は、最初から弁護士の退職代行を通して辞めることも検討しましょう。
>退職代行のおすすめサービス比較はこちら




引き継ぎを優先すると有給が使い切れない場合の選択肢
責任感の強い人ほど、引継ぎを完璧にしようとするあまり、有給消化の時間が十分に確保できないことがあります。
この場合の選択肢は主に以下の通りです。
- 有給休暇の買取を打診する
-
もしも会社の就業規則に退職時の有給買取の規定があれば、未消化分の有給休暇を金銭で補償してもらえる可能性があるため、相談してみるといいでしょう。
- 退職日を遅らせる
-
退職日を延期するどうしても有給を消化したい場合は、退職日自体を後ろにずらすことも検討できます。例えば、当初3月末の退職予定だったものを4月末に変更し、その分の有給消化期間を確保するという方法です。
ただし、次の就職先が決まっている場合は、入社日の調整も必要になるため、注意しておきましょう。
- 消化しきれない有給をあきらめる
-
どうしても有給休暇を消化できな場合は、「あきらめる」という選択肢も出てしまいます。
ですが、全ての有給を消化できなくても、一部でも消化することで損失を最小限に抑えられます。引継ぎが一段落したタイミングで、残りの期間は有給消化に充てるという方法も検討しましょう。
また、半日単位や時間単位での有給取得が可能なであれば、より柔軟な活用も可能です。
どの選択肢を取るにせよ、早めに上司や人事部と相談し、最適な解決策を見つけることが大切です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
有給休暇の未消化は、労働者にとって大きな損失です。転職後の仕事に支障をきたさないよう、計画的に対応しましょう。
場合によっては、次の職場の理解を得て、有給を消化してからの入社を交渉するのも有効です。
退職を引き止められた場合の適切な対応
退職の意向を伝えた際に「もう少し考えてほしい」「待遇を改善するから残って欲しい」など、引き止められるケースもあります。
退職を決意した際の適切な対応例は以下の通りです。
- 感謝の気持ちを示す(「ご配慮いただき感謝します」など)
- 退職の意思が固いことを明確に伝える
- 具体的な退職日と有給消化の希望を改めて伝える
- 引継ぎをしっかり行う意思を示す
退職の意思が固い場合は、「十分に考えた上での決断です」と伝え、あいまいな対応は避けることが大切です。また、引き止めが執拗で強要に近いと感じる場合は、人事部門や上位の管理職に相談することも検討しましょう。
どのようなトラブルに直面しても、感情的にならず、法律上の権利を理解した上で、冷静に対応することが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
引き止められることは、あなたのスキルや価値が評価されている証拠でもあります。
しかし、退職を決意したならば、将来のキャリアを優先し、迷わず前に進むことが重要です。
もしも在職強要されて辞められない場合は、退職代行サービスの利用も検討するといいでしょう。
>おすすめ退職代行の比較はこちら




退職時の有給消化でよくある質問
退職時の有給消化に関するよくある質問と回答は以下の通りです。
有給消化中の給与はどうなりますか?
有給消化中も基本的に通常通り給与が支払われます。
なお、金額としては以下の3つのいずれかの方法で計算のうえ支払われます。
- 通常勤務と同じ賃金を支払う(最も一般的な方法です)
- 直近3ヶ月の平均賃金を計算して支払う
- 標準報酬日額を算出して支払う
有給消化中も社会保険は使えますか?
有給消化中も雇用関係は継続しているため、健康保険や厚生年金などの社会保険は通常通り適用されます。
退職日までは被保険者資格があるので、病院での保険診療や健康保険の給付も受けられます。医療費や出産などで保険を利用する予定がある場合は、この点も考慮して退職日を設定するとよいでしょう。
有給消化中に転職活動をしても問題ないですか?
有給消化中に転職活動をすることは法律上問題ありません。
有給休暇は理由を問わず取得できる権利であり、その使い方は自由です。ただし、有給消化中に他社で働き始めると二重就労になる可能性があるため、現職の就業規則を確認し、転職先の入社日は正式な退職日以降に設定するのが無難です。
また、転職先が同業の場合、競業避止義務等に違反する可能性があるため、注意しておきましょう。
消化できない有給休暇を買い取ってもらうことはできますか?
原則として有給休暇の買取りは禁止されていますが、退職時の未消化分については例外的に買取りが認められています。
ただし、会社に買取りの義務はなく、就業規則に規定がある場合や会社が任意で応じる場合に限られます。
アルバイトですが有給は使えますか?
アルバイトやパートタイマーでも、6ヶ月以上継続して雇用され、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇が付与されます。
付与日数は週の所定労働日数に応じて変わりますが、退職時の有給消化についても正社員と同様の権利があります。
雇用形態による差別は禁止されているため、「アルバイトだから有給は使えない」という理由で拒否されることはありません。
有給休暇は退職日以降でも使えますか?
有給休暇は在職中にしか取得できないため、退職日以降に使うことはできません。
退職日とは雇用契約が終了する日であり、この日を境に労働者としての権利も消滅します。そのため、有給休暇を使いたい場合は、退職日前に消化するか、退職日自体を後ろにずらして有給消化期間を確保する必要があります。
退職日を設定する際は、残有給日数も考慮して計画を立てましょう。
退職時の有給消化まとめ
退職時の有給休暇消化は、労働者の法的権利として認められています。効果的に消化するためには、残日数の正確な把握、計画的な退職日の設定、早めの退職意向伝達、具体的な引継ぎスケジュールの提示が重要です。
また、最終出社日の前後どちらに消化するかは、個人の状況や優先事項によって選択しましょう。
退職時の有給消化を巡ってトラブルが発生した場合は冷静に対応し、必要に応じて労働基準監督署などに相談することも検討する必要があります。
退職を検討している方は、計画的に有給休暇を消化して、次のステップに向けて心身ともにリフレッシュする時間を確保しましょう!
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
本記事では、退職時における有給休暇の取得について、労働基準法をはじめとする法的根拠に基づき解説しています。
有給休暇は労働者の正当な権利であり、退職時であっても適切に消化することが可能です。ただし、現実には、会社側との調整や業務の引継ぎといった課題が生じることもあります。
退職をスムーズに進めるためには、早めの準備と計画的な対応が重要です。特に、有給消化を巡るトラブルを防ぐためには、申請を記録に残すこと、引継ぎの計画を明確にすることが有効です。
また、万が一会社が不当な対応を取る場合には、労働基準監督署や弁護士や特定社会保険労務士、労働組合などの専門家への相談も検討するとよいでしょう。
労働環境の改善が求められる現代において、労働者一人ひとりが自身の権利を理解し、適切に行使することは、円満な退職だけでなく、次のキャリアへの前向きな一歩にもつながります。
本記事が、皆様の退職準備において参考となれば幸いです。
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表
【保有資格】
- 特定社会保険労務士(第1597009号)
- 2級キャリアコンサルティング技能士
- キャリアコンサルタント
- 行政書士
【経歴】
大手人材派遣会社や自動車部品メーカーにおいて人事労務の実務経験を積んだ後、労働局職員としてハローワーク勤務および厚生労働事務官としてキャリア支援や各種労働相談、雇用保険給付業務、助成金関連業務など幅広い分野で活躍。
現在は、社会保険労務士法人 岡佳伸事務所の代表として、企業や個人に対する人事労務コンサルティングを提供し、働く人々のキャリア支援にも尽力。
2025年2月12日監修
続きを読む
【メディア掲載実績】
NHK「あさイチ」(2020年12月21日、2021年3月10日)出演および報道内容の監修
参照:あさイチ「人生100年時代の働き方 仕事によるけが・病気どうすれば?」
他、セミナー講師として多数登壇




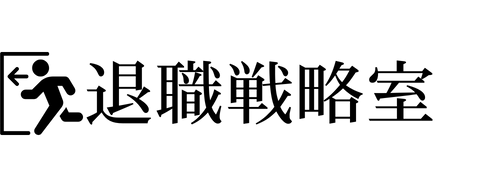
.png)





