会社が退職させてくれない場合の相談窓口は?辞めさせてくれないときの対処法を徹底解説

「会社を辞めたい」と思っても、なかなか退職させてもらえないケースは、実は少なくありません。
退職届の受理を拒否されたり、違約金や損害賠償を請求すると脅されたり、懲戒解雇にすると言われたり…。しかし、こうした会社の対応は違法な可能性が高いものです。
本記事では、退職を認めてもらえない場合の適切な対処法や、おすすめの相談窓口について解説していきます。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


会社が退職を認めないのは違法の可能性が高い
「退職したいのに会社が認めてくれない」「退職届を受け取ってもらえない」など、退職の意思を表明しても会社側に拒否されるケースは少なくありません。
会社が退職を認めないという状況は、実は「在職強要」と呼ばれる違法行為である可能性が高いのです。
退職に関する法律は、「無期雇用」と「有期雇用」で内容が異なります。そこで、ここからは雇用形態ごとに退職のルールや注意点について解説していきます。
正社員は退職を伝えて2週間で辞められる
正社員など期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者(無期雇用労働者)は、民法第627条に基づき、退職の意思を伝えてから2週間で退職することが可能です。
正社員(無期雇用契約の労働者)の場合、退職に関するポイントは以下の通りです。
- 退職の申し入れから最短2週間で退職が成立する
- いつでも退職の申し入れが可能
- 退職に会社の許可は不要
- どのような退職理由でも辞められる
つまり、会社が退職届を受け取らなかったり、退職を認めなかったりしても、退職の意思を表明してから2週間が経過すれば、法的には退職が成立するのです。
なお、会社の就業規則で「退職の1か月前に届け出ること」などと退職予告期間が定められている場合でも、法律上は最短2週間で退職可能です。ただし、円満退職のためには可能な限り就業規則に沿った対応をするのが望ましいでしょう。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)法律上は正社員(無期雇用労働者)は非常に退職しやすい働き方です。
会社ごとの独自ルールで「退職を認めない」と主張するケースもありますが、基本的に法律に則った退職が可能になります。




雇用期間中の契約社員は原則退職できない
契約社員や派遣社員などの期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)の場合は、契約期間の途中で一方的に退職することはできません。原則として契約期間が満了するまで勤務する必要があります。
ただし、以下の場合においては、契約期間中であっても退職することが可能です。
- やむを得ない事由がある場合
-
民法第628条では、有期雇用契約においても、「やむを得ない事由」がある場合はすぐに退職することができると定められています。
「やむを得ない事由」の例としては、職場のハラスメントを受けている場合や、病気や怪我で仕事を続けられない場合、家族の介護などが該当します。
- 会社の合意がある場合
-
会社側が退職に合意している場合は、契約期間が残っていても退職可能です。
- 1年を超える雇用契約において1年以上勤務した場合
-
有期雇用の労働者であっても、1年を超える雇用契約において1年以上働いている場合は、申し出ることでいつでも退職することが可能です。
契約社員であっても、健康や生活への深刻な支障がある場合には、法的にも途中退職の正当性が認められることが多々あります。無理に働き続けるのではなく、早めに専門家に相談して対策を講じましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
契約社員の場合、会社の合意は比較的容易に取れることが多いですが、派遣社員の場合は派遣元が退職を認めないケースがあります。
派遣会社にとって、派遣社員の退職は「売上の低下」に直結するため、会社によっては激しい引き止めを受ける可能性があるでしょう。
自力で退職することが難しい場合は、退職代行や弁護士などの専門家への相談を検討するようにしましょう。
>派遣社員も退職代行を使って辞められる?注意点とおすすめな人を解説




退職をさせてくれない際の5つの対処法
会社に退職の意思を伝えたにもかかわらず、さまざまな理由で退職させてもらえないケースは少なくありません。このような状況に直面したとき、どのように対処すべきか、具体的な方法を5つのケース別に解説します。
それぞれ詳しく解説していきます。
退職届の受理を拒否された場合
退職を申し出た際に、「退職届を受け取ってもらえない」「退職届を破かれた」という話を聞くことがありますが、この行為は法的に意味がありません。
前述したように、正社員(無期雇用)の場合は退職の申し出から2週間で退職が可能であり、退職届を提出してから最短2週間が成立します。
ですが、「退職の意思表示をした」という客観的証拠を残すためにも、退職届を受け取ってもらえない場合は以下の対応をするといいでしょう。
- 退職届を内容証明郵便で送付する
- 「退職願」ではなく「退職届」を出す
- 直接退職届を提出するだけではなく、会社のメールでも退職を希望している記録を残します
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職届の受理拒否は法的に無意味です。感情的に動かず、証拠を残しながら粛々と手続きを進めることが、確実かつ安全な方法です。
ただし、有期雇用(契約社員や派遣社員)の場合、やむを得ない退職理由がない場合は、会社の合意が必要になるケースが多く、交渉は慎重に行う必要があるでしょう。


引継ぎを理由に引き留められる場合
「引継ぎが終わっていない」という理由で退職を引き留められることもよくあります。
しかし、希望する退職日までの期間に出来る範囲の引き継ぎを実施すれば、それ以上会社の都合で退職を妨げることは、原則できません。
引継ぎを理由に引き留められる場合の対処法は下記の通りです。
- 可能な範囲で引き継ぎを実施
-
まずは退職日を設定し、そのうえで可能な範囲で引継ぎを行いましょう。
- 明確な期限を設ける
-
「○月○日までは引継ぎに協力しますが、それ以降は有給休暇を消化の上で退職させていただきます。」等のように、期限を設定したうえで引き継ぎを行いましょう。
また、「後任が決まるまで退職できない」という独自ルールで在職強要をする会社もありますが、後任の確保は会社側の責任であり、退職を引き止める根拠とはならないため、振り回されないように注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職するうえで、自身の業務の引き継ぎは必要ですが、後任者がいない場合は「複数の同僚へ分散して引き継ぎ」「引き継ぎ書類を作成」等を行い、退職日を引き延ばされないようにしましょう。




違約金を請求すると脅された場合
退職を申し出たところ「急に退職するなら違約金を払え」と言われるケースがあります。
しかし、労働基準法第16条では、労働契約の不履行について違約金を定めることや損害賠償額を予定する契約を禁止しています。
就業規則に違約金の定めがあっても、毅然とした態度で拒否し、必要であれば労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を申し出た際に「違約金を支払え」といわれると、頭が真っ白になって、退職をあきらめる場合もあるようです。
ですが、このような場合は一度冷静になり、必要に応じて専門家に相談するようにしましょう。




損害賠償を請求すると言われた場合
退職によって会社に損害が出るとして、損害賠償を求められることがあります。
ただし、以下の場合においては損害賠償請求の正当性が認められる可能性があるため、注意しておきましょう。
- 退職の意思表示をせずにバックレたことで損害が出た
- 有期雇用契約期間中に退職が成立していない状況で一方的に辞めた
- 退職後に従業員や顧客の引き抜きを行い明確な損害が発生した
また、前述したように、「損害賠償を予定した契約」は労働基準法によって禁止されているため、就業規則や雇用契約を根拠に損害賠償請求が認められることは基本的にありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
多くの場合、「辞めたら損害賠償を請求する」といった会社側の発言は、退職を思いとどまらせるための脅しにすぎません。
もし本当に損害賠償をちらつかせてくるようなブラック企業を辞めたい場合は、弁護士や退職代行サービス、労働基準監督署といった専門機関への相談も検討しましょう。
懲戒解雇を仄めかされた場合
「退職するなら懲戒解雇にする」などと脅されるケースもあります。懲戒解雇になると、退職金が支給されない、離職票に「重責解雇」と記載されるなどの不利益が生じる可能性があります。
しかし、退職の申し出自体は労働者の正当な権利であり、それを理由に懲戒解雇とすることは不当解雇にあたります。対処法としては下記があげられます。
- 就業規則の確認
-
どのような場合に懲戒解雇となるのか、就業規則を確認。
- 証拠の収集
-
不当な懲戒解雇の脅しについて、メールや録音などの証拠を残す。
- 専門家への相談
-
不当な懲戒解雇の脅しを受けた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談する。
懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分です。これは、重大な背信行為や犯罪行為、または何度注意しても無断欠勤や遅刻を繰り返すような場合に限って認められるものです。
そのため、単に退職の意思を伝えただけで懲戒解雇をちらつかせてくるのは、明らかに不当な対応だといえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職意思の表明を理由とした懲戒処分は不当解雇になります。
脅し文句にひるまず、証拠を残したうえで専門家に相談するといいでしょう。
退職させてくれない時にすぐに相談できる5つの窓口
会社から退職を認めてもらえない場合、一人で悩まず専門の相談窓口に相談することがへの近道です。
状況に応じて適切な相談窓口を選び、早めに行動することが大切です。ここでは、すぐに相談できる以下の5つの窓口とその特徴を解説します。
それぞれ詳しく解説していきます。
労働局もしくは労働基準監督署の総合労働相談コーナー
厚生労働省が全国の都道府県労働局や労働基準監督署に設置している「総合労働相談コーナー」は、労働問題に関するあらゆる相談を無料で受け付けています。退職に関する問題も相談可能です。
- 無料で相談できる
- 労働関係の専門知識を持った相談員が対応
- 必要に応じて会社への指導も可能
- 中立的な立場からアドバイスが得られる
総合労働相談コーナーでは対面だけではなく電話での相談も可能で、最寄りの総合労働相談コーナーは、厚生労働省HP(以下参照)で調べることができます。
無料で利用することができるため、退職の権利について法的な根拠に基づいたアドバイスが欲しい場合や、会社の対応が法律違反ではないかと思われる場合は、まず総合労働相談コーナーに相談するのが良いでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社との直接交渉に疲れてしまった方や、会社の在職強要が違法か判断できない方は、まずここで客観的なアドバイスを受けることをおすすめします。


退職代行サービス
退職代行は、利用者に代わって会社に「退職の意思」を伝え、やり取りを代行してくれるサービスです。
このサービスを利用すれば、会社と直接やり取りをせずに退職できるのが大きな特徴です。精神的に追い詰められている人や、すでに会社との関係が悪化していて連絡を取りづらい人にとっては、特に心強い選択肢といえるでしょう。
- 会社側と直接対面する必要がない
- 心理的負担が軽減される
- 迅速に退職を進められる
- 有給休暇取得の交渉も可能な場合がある
ただし、退職に関する「交渉」が必要な場合は、民間の退職代行サービスは対応できません。
退職に伴って、有給休暇の取得や未払い給与の支払い交渉も代行して欲しい場合は、労働組合、もしくは弁護士の退職代行サービスに依頼する必要があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行サービスは、「とにかく一刻も早く辞めたい」「もう会社と関わりたくない」という方にはおすすめな選択肢のひとつです。
ただし、業者によって対応可能範囲や質に差があるため、退職後にトラブルを抱えないためにも、費用だけでなく「弁護士が対応するかどうか」や「退職代行の実績」をしっかり確認して依頼先を選ぶようにしましょう。
>退職代行サービスの選び方はこちらで解説


弁護士
退職を巡って法的なトラブルが生じている場合や、会社から不当な要求をされている場合は、労働問題に強い弁護士に相談するのが最も効果的です。
- 法的な代理人として会社と直接交渉できる
- 違法行為に対して法的措置を取れる
- 退職金や未払い賃金などの請求も可能
- 会社側が弁護士の介入を知ると態度を軟化させることが多い
特に、会社から損害賠償や違約金を請求されている場合や、不当な懲戒解雇の脅しを受けているようなケースでは、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
「退職代行」を弁護士が運営しているケースもあり、そうしたサービスを利用すれば、退職の手続きを進めながら法的トラブルの対応も同時に任せることができます。


転職エージェント
退職そのものに直接関与はしませんが、「退職したいが、次の仕事が決まっていない」「将来が不安で動けない」という場合には、転職エージェントのサポートが非常に心強い味方になります。
- 無料で利用できる
- 退職時のアドバイスももらえる
- 次の就職先を同時に探せる
- 転職市場の最新情報を得られる
特に、「今の会社を辞めたいけれど、次の仕事が決まっていないのが不安…」という方には、転職エージェントの活用がおすすめです。面接対策や履歴書・職務経歴書の添削など、転職活動をスムーズに進めるためのサポートが受けられます。
ただし、転職する意思がなければ利用できない点や、退職代行そのものには基本的に対応していない点には注意が必要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
転職先が決まっているという安心感があるだけで、退職に踏み出しやすくなります。
さらに、会社との退職交渉においても、気持ちに余裕が生まれ、強気で臨みやすくなるでしょう。
キャリア相談サービス
退職の悩みだけでなく、今後のキャリアや心理的なケアも含めて相談したい場合は、有料のキャリア相談サービスの利用もおすすめです。
国家資格キャリアコンサルタントなどによるキャリア相談サービスは、「退職すべきかどうか迷っている」「今の仕事がつらいが、次の一歩が踏み出せない」といった悩みに寄り添うサービスです。
- 客観的な視点からキャリアを見直せる
- 心理的なサポートも得られる
- 中長期的なキャリア設計のアドバイスが得られる
- 自己分析の深堀が可能
特に、「退職後どうすればいいのか分からない」「自分に合った仕事が分からない」といった悩みがある場合に有効です。
公的機関・民間サービスともに選択肢があり、近年はオンラインで全国どこからでも相談できるサービスも増えているため、気軽に利用することができます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
引き止められてしまって、この先どう動けばいいのか分からない…」という方には、キャリア相談サービスの活用がおすすめです。
弊社が運営する「キャリアバディ」では、キャリアコンサルタントなどの専門家が、キャリア設計から仕事の悩みまで幅広くサポートしています。
今の仕事にモヤモヤしている方や、将来のキャリアに不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
円満な退職実現までの具体的なステップ
退職を会社に認めてもらえないという問題に直面している場合でも、できれば円満に退職したいと考えるのは自然なことでしょう。
会社とのトラブルを避け、良好な関係を保ったまま退職するためには、段階的かつ計画的に進めることが大切です。以下では、円満な退職を実現するための5つの具体的なステップを紹介します。
最適なタイミングで退職の意思を伝える
退職の意思を伝えるタイミングは、円満退職のカギとなります。
正社員の法律上は退職希望日の2週間前までに伝えればよいですが、社会通念上は1〜2ヶ月前に伝えることが望ましいとされています。
なお、退職理由を伝える際は、会社や上司への不満ではなく、「自己成長のため」「新しい環境にチャレンジしたい」など前向きな理由を伝えると摩擦が少なくなります。引き止められる余地を残さない明確な意思表示が大切です。
退職届を提出する
退職の意思を口頭で伝えた後は、書面で正式に退職届を提出します。退職届は簡潔に、かつ必要な情報を漏れなく記載することが重要です。
退職届は「退職願」ではなく「退職届」という形式で提出するのがポイントです。「願」は許可を求めるニュアンスがありますが、「届」は決意を伝える通知です。
後任者へ業務を引き継ぐ
円満退職のためには、責任をもって業務の引継ぎを行うことが重要です。これにより、退職後も業務が滞りなく進み、会社や同僚への負担を最小限に抑えることができます。
- 業務マニュアルを作成する
- 重要な取引先や顧客との関係を整理する
- クラウドサービスやシステムのアカウント情報をまとめる
- 定期的に発生する業務のスケジュールと処理方法
引継ぎが完全に終わらないことを理由に無期限に退職を引き延ばされることは避けるべきですが、可能な限り誠実に対応することが、円満退職への近道です。
退職日までに余裕をもって、複数の社員に業務を分散させるか、引き継ぎ書を作成するなどして、スムーズな引き継ぎを行いましょう。
有給休暇を消化する
退職前に残っている有給休暇を消化することは、労働者の正当な権利です。退職の際には全て消化したうえで辞めるようにしましょう。
- 退職日が決まったら、すぐに残りの有給日数を確認する
- 業務の引継ぎ計画を立てる際に、有給消化スケジュールも考慮に入れる
- 有給消化計画を早めに上司に伝え、理解を得る
会社によっては有給休暇の買取制度がある場合もありますが、原則として有給休暇の権利を行使できるようにしましょう。
会社が有給休暇の取得を認めない場合は、労働基準監督署に相談することも選択肢のひとつとなります。
会社貸与物を忘れずに返却する
最後に、退職日までに、会社から支給されたPC・スマートフォン・制服・社員証・鍵・書類などはすべて返却しましょう。
返却漏れがトラブルの原因になることもあるため、計画的に返却しましょう。


退職させてくれない時の専門家への相談時期と選択のポイント
退職を会社に認めてもらえない場合、自力での解決が難しくなるケースも少なくありません。そんな時、専門家のサポートを受けることで、スムーズな解決につながることがあります。
ここでは、専門家への相談のタイミングと適切な専門家の選び方について解説します。
各専門家への相談が効果的なタイミング
専門家に相談するタイミングは、問題の深刻さや緊急性によって異なります。一般的には以下のようなタイミングが効果的です。
- 退職の意思を伝えた後、パワハラやモラハラが激化した場合
- 退職届を提出しても受理されず、無視され続けている場合
- 「辞めるなら違約金を払え」「損害賠償請求する」などと脅された場合
- 「懲戒解雇にする」などの不当な脅しを受けた場合
- メンタルヘルスに深刻な影響が出始めている場合
- 引継ぎを理由に引き留められているが、まだ話し合いの余地がある場合
- 退職の意思を初めて伝えたところで、即答を避けられた場合
- 退職時期の調整について交渉中の場合
専門家への相談は、「最後の手段」と考えるのではなく、問題が複雑化・長期化する前の「予防策」と捉えるのが良いでしょう。特に、健康状態の悪化や深刻な法的問題に発展しそうな場合は、早めの相談が重要です。
各専門家の選択は、直面している問題の性質によって異なります。例えば、法的問題には弁護士、キャリアの悩みには転職エージェントというように、目的に合わせた専門家を選ぶことが大切です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職に伴うトラブルは、相談が早ければ早いほど、解決の選択肢が多くなります。
「退職させてもらえない」という問題が発生した際に、信頼できる専門家に適切なタイミングで相談することで、精神的なゆとりを持つことができるでしょう。
法的対応が必要な場合の弁護士へ相談
会社から違約金や損害賠償を請求されたり、「懲戒解雇にするぞ」といった脅しを受けた場合は、個人での対応は非常に危険です。
労働問題に強い弁護士であれば、企業側の不当行為に対して厳正に対応できるだけでなく、退職後の労働審判や訴訟対応も視野に入れて動けます。初回相談無料の事務所も多いため、躊躇せずに動き出すことが重要です。
弁護士費用は一般的に着手金と成功報酬の形で発生しますが、労働問題については比較的リーズナブルな料金設定の事務所も増えています。複数の弁護士に相談して比較検討することも一つの方法です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を伝えたことで、会社側と法的なトラブルを抱えてしまった場合は、弁護士の退職代行に相談することも検討するといいでしょう。




自力での交渉が難しい場合の退職代行へ相談
会社との関係が悪化しすぎて、もう顔を合わせたくない、話したくないと感じるケースでは、退職代行サービスが有効です。
- パワハラ・モラハラなどで精神的に限界に達している
- 上司との関係が険悪で直接話すことが難しい
- 早急に会社との関係を断ちたい
- 退職を伝えた後の引き留めや説得が苦痛である
- 体調不良で出社できない状態である
また、最近ではLINEやオンラインで即日対応してくれる退職代行業者も多く、スピーディな対応が可能です。
状況に応じて適切な専門家を選び、早めに相談することで、退職問題の解決がスムーズに進む可能性が高まります。一人で悩まず、必要に応じて専門家の力を借りることを検討してください。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職代行に依頼することで、職場とのやり取りをすべて任せられるため、心身のリスクが高まっている時は遠慮なく相談しましょう。
ただし、業者選びには注意が必要で、口コミ・運営実績・弁護士対応の有無などをしっかりチェックしましょう。
>おすすめ退職代行の一覧比較はこちら




退職させてくれない場合の相談窓口と対処法のまとめ
会社が退職を認めないという状況に直面したとき、法律上の権利を理解し適切な対応をとることが重要です。
例えば、正社員は民法第627条により、退職の意思表示から2週間経過すれば会社の承諾なく退職できます。これは労働者の基本的権利であり、会社がこれを認めないのは「在職強要」という違法行為の可能性があります。
また、有期雇用契約(契約社員や派遣社員など)で働いている場合であっても、「やむを得ない事由」があれば、すぐに退職することができます。
法律を超えて退職を妨げられている場合は、内容証明郵便での退職届提出や専門家への相談を検討するといいでしょう。
>退職させてくれない時にすぐに相談できる5つの窓口は本記事のこちら
退職問題は一人で抱え込まず、早めに専門家のサポートを受けることで解決の糸口が見つかります。自身の健康と将来のキャリアを最優先に考え、適切な相談窓口を活用しましょう。


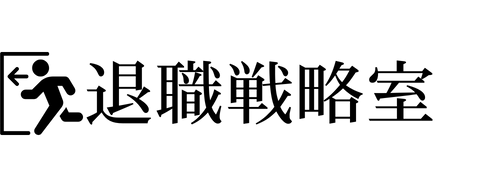
.png)





