【体験談あり】退職できない悩みと7つの対処方法を解説!それでも辞められない時の最終手段3選も紹介

退職を申し出たのに、会社から「後任が見つかるまで待って欲しい」「いま辞めたら損害賠償を請求する」と言われて、スムーズに退職できないケースがあります。
このような在職強要は違法行為である可能性が高く、職場環境によっては心身に著しく負担がかかる場合があるため、適切に対応していく必要があります。
本記事では、在職強要の具体例や体験談、退職に関する法律上のルールや実践的な対処法まで解説していきます。辞めたいのに退職できなくて悩んでいる人は、是非最後までご確認ください。
プロフィール画像.jpg)
特定社会保険労務士
(社会保険労務士法人岡佳伸事務所 代表)
監修者 岡 佳伸
【保有資格】
- 特定社会保険労務士(第1597009号)
- 2級キャリアコンサルティング技能士
- キャリアコンサルタント
- 行政書士
【経歴】
大手人材派遣会社や自動車部品メーカーにおいて人事労務の実務経験を積んだ後、労働局職員としてハローワーク勤務および厚生労働事務官としてキャリア支援や各種労働相談、雇用保険給付業務、助成金関連業務など幅広い分野で活躍。
続きを見る
現在は、社会保険労務士法人 岡佳伸事務所の代表として、企業や個人に対する人事労務コンサルティングを提供し、働く人々のキャリア支援にも尽力。
【メディア出演実績】
NHK「あさイチ」(2020年12月21日、2021年3月10日)出演および報道内容の監修
参照:あさイチ「人生100年時代の働き方 仕事によるけが・病気どうすれば?」
他、セミナー講師として多数登壇
2025年2月12日監修
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


退職できない!在職強要の具体例
会社を辞めたいと考え退職を申し出たにも関わらず、会社がそれを認めず退職できないケースがあります。
これは「在職強要」と呼ばれ、会社が労働者の権利を著しく侵害するものであり、違法行為に該当する可能性があります。
在職強要の具体例としては以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png) 退職戦略室 編集長
退職戦略室 編集長少子高齢化に伴って人材不足が続く日本においては、退職者の引き留めが行われることが多くあります。
退職引き留めの全てが問題というわけではなく、適切な方法と、本人の意思によって在職を決めるのであれば問題ありません。
ですが、労働者の意思を無視した在職を強要は、法的にも倫理的にも問題があるといえるでしょう。
退職届を受理してもらえない
退職届の不受理は最も一般的な在職強要の形態です。
退職届を受理せず辞めることを認めないのは、労働者の退職の自由を侵害する違法行為であり、会社にそのような権限はありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
民法において、正社員の場合は退職の申し出から2週間、契約社員の場合は原則として契約期間中は退職できないものの「やむをえない理由」があればいつでも退職が可能です。
参照:e-Gov法令検索「民法第627条・628条」
ですが、退職拒否をするブラック企業はこの法律を無視して在職強要を行う場合があります。
会社が法律を無視した在職強要をする場合は、労働基準監督署や退職代行サービスへの相談を前向きに考えるようにしましょう。


後任が見つかるまで待つように言われる
人手不足が深刻な職場においては、「後任が見つかるまで待ってほしい」と言われ、退職できない場合がよく見られます。
労働力不足によって求人倍率が高い状況が続く日本では、求人広告を出しても応募者が確保できる保証はなく、後任者が見つかるのがいつになるのか分からない場合が多いでしょう。
会社の都合で退職の権利を制限することは認められないため、期限の存在しない「後任が見つかるまで」という要求を聞く必要はありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職希望者に「後任が見つかるまで」と引き留めつつ、人材の募集や社内異動の調整を一切していない悪質なケースもあります。
このような場合、部下の退職が自身のマイナス評価につなげることを恐れ、「自分が異動になるまで待って欲しい」が本音のケースもあるため、注意が必要です。
退職するかどうかは自分のキャリアおよび人生に深く関わる選択のため、会社の判断ではなく自分の判断で行動するようにしましょう。


退職時期を引き延ばされる
退職を申し出た際に、会社側から「半年後でないと認められない」「繁忙期は認められない」など、退職時期について不当な制限を受け、すぐに退職できないケースがあります。
就業規則や雇用契約に「退職は半年前に申し出が必要」等を定めている会社がありますが、法律を超えた設定については法的拘束力はありません。
そのため、会社側が退職時期の引き延ばしを要求している場合であっても、本記事で紹介する「確実に退職を実現するための最終手段」をとることで、問題なく辞めることができます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職時期を引き延ばされることで、転職の時期を逃す可能性があるため、注意が必要です。
また、ハラスメントがある職場の場合は、仕事を続けることがそのものが精神的に苦痛を感じるでしょう。
当然のことですが、会社は個人のキャリアに一切責任を持っていません。
自身の人生とキャリアを守り育てるためには、自分で考えて行動することが必要です。
状況次第では、退職代行サービスの利用も検討するといいでしょう。


損害賠償請求や懲戒解雇で脅される
悪質なブラック企業の場合、退職を申し出たことで「損害賠償請求」や「懲戒解雇」をすることを仄めかし、労働者の在職を強要するケースが見受けられます。
脅しともとれる内容で在職を強要されるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 損害賠償請求を仄めかされる
- 懲戒解雇にすると脅す
- 退職金は一切支払わないと宣言
これらの脅しは、そのほとんどが法的根拠のないものです。
退職を巡ってこのようなトラブルに巻き込まれ、退職できずに困っている場合は、すぐに弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスや、各労働基準監督署や労働局に設けられた総合労働相談コーナーへ相談するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ブラック企業によっては、会社側が職権を濫用し、実際に損害賠償請求や懲戒解雇を行うケースがあります。
退職の申し出に伴って会社側がこのような対応をする可能性がある場合は、最初から弁護士の退職代行に依頼し、法的に適切な対応をしてもらうことがおすすめです。
>弁護士の退職代行はこちらで解説


法律で定められた退職に関するルール
退職は労働者の基本的な権利のひとつであり、雇用形態に応じて退職のルールが法律で定められており、これを把握することで毅然とした態度で退職引き留めに向き合うことが可能になります。
法律で定められている退職に関する主なルールは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
正社員は2週間前の申し出で退職できる権利がある
民法第627条第1項に定められている通り、期間の定めのない雇用契約(正社員)の場合、2週間前に退職の申し出をすれば退職できる権利が保障されています。
そのため、労働者本人の希望があれば、申し出から最速2週間後に退職が可能で、原則、これを止めることは出来ません。
また、正社員の退職の場合は理由は問われず、人間関係の悩みや業務上の問題など、どのような理由でも退職することができます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
円満退職のためには、ある程度会社の要望を聞きつつ、転職の妨げにならないように退職日を設定する必要があります。
ですが、退職申し出の後に3か月~6か月のように極端に長い在職を要求される場合は、転職活動に影響が出る可能性があるため、断ることを前向きに検討しなければなりません。
退職という人生の転機においては、自身の中長期的なキャリアを優先して考え、自分を犠牲にするような判断を取らないようにしましょう。




契約社員の場合の退職ルールと例外
契約社員やパート社員等の期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)の場合、原則として契約期間の満了まで勤務する必要があります。そのため、「雇用期間中は退職できない」という考えは、基本的に間違っていません。
ただし、以下の場合は契約期間中であっても退職することが可能です。
- 退職のやむを得ない理由がある場合
- 契約開始から1年以上経過している場合
(雇用契約期間が1年以上の場合) - 会社の合意がある場合
特に、退職のやむをえない理由がある場合は、すぐに退職をすることが可能です。やむをえない退職理由とは、具体的には「職場のハラスメント」「仕事が困難な家庭事情」等が一例として挙げられます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社によっては、退職のやむをえない理由を伝えたとしても、「契約期間中は退職できない」と言い張るケースがあります。
この場合、担当者の法律理解が不足しているか、もしくは退職できることを知っていて在職強要をしていることが考えられます。
特にハラスメントや労働関係法令の違反は立派な退職理由になり得ます。
もしも一人で退職を進めることが難しい場合は、労働組合や弁護士などの「退職に関する交渉」が可能な退職代行サービスに依頼するといいでしょう。




就業規則による退職予告期間が長い場合の法的な扱い
多くの会社の就業規則には、「1ヶ月前」や長い会社だと「半年前」といった退職予告期間が定められています。そのため、「退職を申し出ても、すぐには退職できない」と悩んでいる人は多いようです。
ですが、就業規則に極端に長い退職予告期間が設けられている企業の場合、退職の際に揉めることもあるでしょう。
自分一人で退職を進めることが荷が重いと感じたら、労働基準監督署や労働局に設けられた総合労働相談コーナー、もしくは退職代行サービスへの相談を検討した方がいいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
不当に長い退職予告期間は労働者の転職活動を阻害し、健全なキャリア形成を妨げる恐れがあります。
退職をすることを決めた場合は、自分自身の人生やキャリア設計を優先し、法的に認められる退職期間で辞めることを目指すといいでしょう。
会社から退職できないと言われた場合の対処法7選
会社から様々な理由で退職を認めないと言われた場合でも、適切な対処方法を知っていれば、合法的に退職を実現することができます。
それぞれのケースに応じた効果的な対応策を見ていきましょう。
と言われた場合の対処法7選
給与の未払いをほのめかされた場合
退職の意思を伝えることで、会社から「今やめるなら給与は支払えない」と給与の未払いを宣言される場合があります。
退職時に、もしも会社が賃金の未払いという違法行為を行う場合は、以下の方法で対応しましょう。
- 給与明細や勤怠記録などの労働の証拠を確実に保管する
- 給与未払いの発言を記録に残す
- 必要に応じて労働基準監督署に相談する
どのような状況であっても、原則、給与の未払いは許されないことを念頭に、上記の対応を検討するようにしましょう。
退職を申し出ることで給与の未払いを宣言する時点で非常に悪質な職場といえるため、労働基準監督署への相談や退職代行サービスの利用も前向きに検討するといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ブラック企業のなかには、既に勤務した日時に対して、「成果を上げておらず、働いたと認められない」という非合理な理由で賃金の未払いを行おうとする場合があります。
当然のことですが、これは認められません。
職権を濫用して退職の引き留め、および労働者の賃金未払いを仄めかされる場合は、労働関係のトラブルに強い弁護士の退職代行サービスや、労働基準監督署へ相談をするといいでしょう。


損害賠償を請求すると脅された場合
退職届を出した際に、様々な理由をつけて「損害賠償を請求する」と脅され、結果的に退職できず悩んでいるケースが見られます。
そのため、たとえ就業規則や労働契約に損害賠償の定めがあったとしても、退職を理由とする損害賠償請求は基本的に認められません。
ただし、退職者が在職中に職権を濫用した悪質な行為、および会社へ実質的な損害を与える行為をしている場合は、稀に損害賠償が認められるケースもあるため、注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
上記で紹介した以外にも、人手不足を理由に損害賠償請求をされるケースがあります。
ですが、正社員の場合は法律で定められた「申し出から2週間の期間」を空けて退職する場合は、その間に経営者に採用を行う必要があり、損害賠償の正当な理由になり得ません。
もしも自身の退職のケースにおいて「損害賠償請求されるかも?」と不安になっている人は、弁護士の退職代行に相談して現実的なリスクを確認してみるといいでしょう。


懲戒解雇をちらつかせられた場合
退職の引き留め手段の一つとして、「今辞めるなら懲戒解雇をする」と脅される場合があります。
懲戒解雇は、労働者に悪質な職場規律違反や背信行為がある場合にのみ認められる非常に重い処分であり、適正な手続きを経る必要があります。
労働者に懲戒解雇が認められるような行為が認められるケースでなければ、万が一懲戒解雇をされても法的に無効になります。
ですが、懲戒解雇の有効性を争うためには労働審判や訴訟が必要になる可能性が高く、弁護士費用が必要になるだけではなく退職後のキャリア形成に費やすべき時間を失うことになります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職の申し出時に会社側から懲戒解雇を仄めかされた場合は、まずは労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーに相談するようにしましょう。
もしくは、弁護士の退職代行サービス等に相談し、法的な知識をもとに対応することがおすすめです。
費用は必要になるものの、弁護士の退職代行であれば懲戒解雇を避けつつ、退職に伴う有給休暇の取得や退職日の調整も代行してもらえるので、ブラック企業を確実に退職する際におすすめの選択肢のひとつです。


退職金不支給を示唆された場合
退職金規定のある会社では、規定に基づく退職金の支給は会社の義務です。そのため、退職を理由に退職金を不支給とすることは違法行為です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社によっては、退職理由が自己都合退職か否かによって、退職金の支給有無や支給率が異なる場合があります。
自分から退職を申し出る場合は自己都合退職になると誤解している人もいますが、パワハラやセクハラ等の会社側の要因によって退職する場合は「会社都合退職」と認められるケースもあるため、就業規則をよく確認し、適切な対応をとるようにしましょう。


有給休暇の取得を制限された場合
退職を申し出た際に、引き継ぎの必要性や人手不足を理由に、有給休暇の取得を会社側が認めないことがあります。
会社が有給取得を認めない場合は、労働基準監督署や退職代行サービスに相談し、退職までに期間中に有休を使い切ることで、次の転職に活かせるようにするといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職時に限らず「うちは有給休暇の制度はない」と主張する会社もありますが、これは法律上認められません。
6か月以上継続して勤務し、労働日の8割以上出勤している労働者は、雇用形態や所定労働日数を問わず有給休暇の対象です。
フルタイム労働者の場合は6か月以上勤務後に10日分、その1年後には11日分の有給休暇が付与されます。
有給をこれまで使えなかった場合は、退職時に使い切って次の転職先に備えるようにするといいでしょう。




離職票の発行を拒否された場合
「退職は認めない」「どうしても辞めるなら離職票は出さない」と主張し、退職の引き留めを行うブラック企業もあります。
発行を拒否された場合は、ハローワークに相談することで解決できます。ハローワークから会社に働きかけてもらうことが可能で、それでも発行されない場合は、ハローワークから離職票の発行を受けることができます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
離職票は雇用保険の失業手当(雇用保険の基本手当)を受けるために必要な重要書類です。
退職の引き留めのために離職票の発行をしないことを仄めかすのは言語道断ではありますが、万が一会社側が発行しなくてもハローワークで対応可能なため、安心して退職しましょう。
希望している退職日と異なる日程を提案された場合
退職の申し出をした際、最もよくある引き留め交渉として「退職日を延期の交渉」が挙げられます。
本記事内でもお伝えしたように、法律上、正社員の場合は退職申し出から2週間で退職することが可能です。
ただし、それ以上の退職日の調整については、自分自身のキャリア設計を第一に検討した方がいいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職日の交渉はよくある引き留めの一種です。
転職活動の妨げにならない範囲で応じても問題ないですが、長引くと転職活動の予定が立てづらく、職場環境が悪い場合は心身にも負担がかかるでしょう。
どこまで退職日の交渉に応じるべきか悩んだ際には、自分のキャリアや転職活動に悪影響が出ない範囲を目安に考えるようにしましょう。
在職強要の実態!退職できなかった体験談
ここからは、退職を申し出ても「引き止められて辞められなかった」「在職を強要された」という人の体験談をご紹介していきます。
「もっと早く決断すればよかった」人手不足を理由に退職引き止め
私は長年、病院の看護師として働いていました。
担当はハードな外来業務で、業務負担が重く、何度も退職を考えました。しかし、「職員が足りない」「あなたにしかできない仕事」と引き止められ、辞めることができませんでした。
私の「頼まれると断れない」という性格も影響し、強く言えずに退職を先延ばしにしてしまいましたが、職場からの圧力も大きかったのです。
続きを読む
「もう少し待って」と言われ続け、気づけば何年も同じ状況が続いていました。
そのうちに精神的にも追い詰められ、出口の見えない絶望感に襲われました。
そんな中、妊娠を機に「産休とともに退職したい」と伝えました。しかし職場は「急に言われても困る」と冷たく対応。
3年以上も前から退職の意思を伝えていたのに無視し続けたのは職場側なのに……。
この瞬間、私は職場が自分をまったく考えていなかったことを痛感しました。
最終的に産休を迎えるタイミングで退職しましたが、もっと早く強い態度を取るべきだったと後悔しています。
体験談寄稿者のプロフィール
- 年齢:33歳
- 性別:女性
- 職業:看護師
ハラスメントが原因で退職を決意するが怒鳴られて委縮
上司のパワハラやセクハラに耐えられず、心身ともに限界を感じて退職を決意しました。
しかし、退職届を提出すると「無責任だ」「後任も決まっていない」と上司から強く叱責され、二人きりの空間で長時間責め立てられました。
怒鳴られることもあり、この状況を終わらせるために「辞めるのはやめます」と言わざるを得ませんでした。
続きを読む
その後も業務上のやり取りで辛く当たられ、精神的に追い詰められる日々が続きました。
退職できない悩みを周囲に相談すると、退職代行や弁護士への相談を勧められ、最終的に退職代行を利用することを決意。
弁護士を通じて手続きを進めた結果、上司と顔を合わせることなく退職することができました。
体験談寄稿者のプロフィール
- 年齢:31歳
- 性別:女性
- 職業:日本語教師
退職を拒否され10年後にようやく退職が実現
高校卒業後、新卒で電気会社に入社しました。
第二種電気工事士の資格は取得していたものの、技術は未熟。それでも、高校で学んだ知識を活かして頑張ろうと考えていました。
しかし、現実は厳しく、怒鳴られることや工具で殴られることもあり、何もさせてもらえない日もありました。
そんな日々が続く中、「この生活がこれからも続くのだろうか」と、不安を抱くようになりました。
続きを読む
入社から7カ月が経った11月、退職を決意し、退職届を準備しました。
そして社長に申し出たところ、「君が辞めるなら君の学校の後輩は採用しない」と告げられ、退職届は受け取ってもらえませんでした。
その後、社内では退職の話が広まり、先輩からも厳しい言葉をかけられ、辞めることが難しい状況になりました。
こうして、気づけば10年が経過していました。
転機が訪れたのは、社長の急逝でした。後任の新社長のもとで改めて転職活動を開始し、求人を探して応募。無事に内定を獲得しました。
そして、新社長に退職を申し出ると、スムーズに話が進み、10年勤めた会社を退職することができました。
体験談寄稿者のプロフィール
- 年齢:30歳
- 性別:男性
- 職業:電気工事士
家族の病気で退職を決意したが「後任が見つかるまで待って欲しい」
大手飲料メーカーで役員秘書をしていた私は、3歳の子どもが重い病気になったことをきっかけに退職を決意。
しかし、「業務が回らない」「後任が決まるまで待ってほしい」と引き止められ、辞められない日々が続きました。
秘書業務の特殊性から引き継ぎが難しく、業務量も増加。
一方で、病状は悪化し、病室で過ごす時間が増えていきました。
続きを読む
転機は、子どもの容態急変で3日間病院を離れられなかったとき。
私がいなくても会社は回っていたのです。
そこで、退職日を明記した辞表を提出し、「子どもの命か仕事か」という選択を伝えました。
さらに、先輩が「労基や弁護士への相談も考えているらしい」と話を広めてくれたことも後押しに。
結果、希望通りの日程で円満退職できました。
一貫した意志と周囲の協力が、退職を実現する鍵でした。
体験談寄稿者のプロフィール
- 年齢:40代
- 性別:女性
- 職業:役員秘書
退職を伝えても「考え直してほしい」と何度も話し合い
育児休暇後、夫の転勤に伴い退職を決意しました。
しかし、会社に退職を伝えると「休暇を取ったばかりで辞められると困る」と強く引き止められました。
上司からは「無責任だ」「業務に支障が出る」と何度も説得されました。
さらに、退職をすることが会社にとってどれほどの困難を引き起こすかを繰り返し説明され、最終的には退職届すら受け取ってもらえませんでした。
続きを読む
一時は会社の都合を考えて悩みましたが、家庭を最優先すべきだと決意。
それでも退職は簡単には認められず、転職先が決まるまで何度も話し合いが続きました。
その際、上司から「次の仕事を決めるのは無理だろう」とプレッシャーをかけられることも。
最終的に、転職先が決まったことを伝え、家庭の事情を改めて説明。
何度も説得されましたが、強い意志を持ち続けたことで理解を得ることができ、ようやく退職が実現しました。
円満退職はできましたが、精神的に非常に辛い経験でした。
体験談寄稿者のプロフィール
- 年齢:38歳
- 性別:女性
- 職業:栄養士
上司のパワハラで辞めることを決意するも退職拒否
当時、私は介護事業所のサービス提供責任者として働いていましたが、上司によるパワハラに悩まされていました。
サービス残業の強要や大声での叱責が1年以上続き、精神的に限界を感じて退職を決意。
退職届を提出しましたが、「人員が足りなくなるからダメ」と拒否され、何度相談しても認めてもらえませんでした。
続きを読む
一緒に働く仲間に申し訳ない気持ちはありましたが、自分を守るために退職を強行することに。
ある日、上司の机に退職届と「精神的に限界のため、明日から出社しません。退職します。」と書いた手紙を残し、そのまま会社を去りました。
その後、会社から電話や訪問がありましたが、一切応じず退職の意思を貫いた結果、最終的に連絡も途絶え、無事に退職が成立しました。
退職できない状況でも、意志を貫くことが大切だと実感した経験でした。
「育児休暇を取ったばかりで辞められるのは困る」と退職拒否
育児休暇取得後、夫の転勤に伴い退職を希望しましたが、「育児休暇を取ったばかりだから、急に辞めるのは非常に困る」と会社に引き止められました。
「業務に支障が出る」と繰り返し説得され、退職届を受け取ってさえもらえませんでした。
上司からは「無責任ではないか」と非難され、何度も再考を求められました。
会社に迷惑をかける罪悪感に悩みましたが、家庭の事情を優先し退職を決意。
続きを読む
何度も退職の話し合い場が設けられ、その際に上司から「次の仕事を決めるのは無理だろう」とプレッシャーをかけられましたが、転職先が決まり再度退職を申し出た結果、ようやく辞めることができました。
最終的には円満退職を実現できましたが、上司の理解を得る過程は非常に辛いものでした。
体験談寄稿者のプロフィール
- 年齢:38歳
- 性別:女性
- 職業:栄養士




退職できないデメリット
退職が実現できない状況が続くことは、個人のキャリアや健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。具体的には以下のようなデメリットがあるため、退職の引き留めに対しては適切に対応していく必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
転職のタイミングを逃す
会社の在職強要によって退職できない場合のデメリットのひとつとして、転職のタイミングを逃すことが挙げられます。
退職を決めた際は、会社の要望に合わせすぎると、自分自身のキャリア設計ができなくなってしまう危険性があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
転職のタイミングを逃さないようにするためには、先に転職先を決めてから退職してもいいでしょう。
その際、入社可能日が不明確なままでは採用を出しづらいという背景もあるため、「内定をもらったら1か月後には入社可能」のように退職予定日を決めて転職活動をする必要があります。
ただし、これは残業が少なく、有給休暇を使って面接などを受けることができる職場に限ります。
在職中に転職活動をすることが難しい場合は、まずは退職をして、失業給付を受けつつ転職活動をすることも検討しましょう。
心身にストレスがかかる
労働者の希望を無視し、不当な在職強要によって退職できない状況は、大きな精神的ストレスとなります。
その結果、集中力の低下や業務効率の悪化、心身の不調を招きかねません。
体調不良は、退職後の転職にも影響を与える可能性があるため、仕事を続けるストレスが大きいと感じている場合、速やかに退職する必要があるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
職場のパワハラやセクハラが原因で心身に不調をきたしている場合、退職の際に会社に対して損害賠償を請求することも可能です。
その際は、法的に対応可能な弁護士の退職代行サービスへの依頼して、確実な退職と損害賠償請求を両立させることも検討しましょう。
労働環境が悪化する
退職の意思を表明した後、職場の環境が著しく悪化することがあります。
退職の申し出を拒否して在職を強要しつつも、上司からの過度な監視や嫌がらせをされ、同僚からの冷たい態度とられる等、精神的な負担が増大する可能性があります。
このような状況が長期化すると、メンタルヘルスに深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、出来る限り早急に退職する必要があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
信じられないことに、一部のブラック企業では退職の引き留めをしたにも関わらず、仕事を続けることを選択すると周囲から嫌がらせを受けることがあります。
このような環境で「仕事を続けることが難しい」と感じたら、退職代行サービスを使って迅速かつ確実に退職を目指すのも選択肢の一つといえるでしょう。


確実に退職を実現するための最終手段3選
会社からの不当な引き止めに遭遇し、正攻法では円滑な退職を実現することが難しい場合の最終手段として、以下の方法を使うことでより確実に退職することが可能です。
上記の方法について、それぞれ詳しく解説していきます。
退職届を内容証明郵便で送付する
退職を申し出ても拒否されてしまう場合は、「退職届を内容証明郵便で送る」という方法があります。
通常の郵便ではなく内容証明を利用することで、「退職届を受け取っていない」と会社側が主張することができなくなるため、確実に退職できる方法のひとつといえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
内容証明郵便で退職届を送付するのは、確実に退職できる方法である一方で、会社との対立構造を強める恐れがあります。
そのため、いきなり内容証明郵便を送るのではなく、退職届の受け取り拒否等のやむをえない事情がある場合に、選択肢のひとつとして考えましょう。


労働基準監督署や労働局の総合労働相談コーナーに相談する
会社側の在職強要によって、退職できずに困っている場合は、各労働基準監督署や労働局に設けられた総合労働相談コーナーに相談することがオススメです。
労働基準監督署とは、厚生労働省が設置する出先機関のひとつで、労働関係法令を違反する企業を取り締まるための組織です。
労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する際は、これまでの経緯や会社とのやり取りを時系列で整理し、具体的な事実関係を説明できるように準備しておくことが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
在職の強要は基本的に職権を濫用した違法行為のため、総合労働相談コーナーに相談することで「退職できない」という悩みは解決できることが多いでしょう。




退職代行サービスを利用する
退職代行サービスは、その名の通り退職に関する会社との交渉や必要な手続きを代行してくれるサービスです。特に以下のような場合に効果的な選択肢となります。
- 直接の対面でのコミュニケーションを避けたい場合
- 法的な専門知識が必要な複雑な状況の場合
- 心身の負担を最小限に抑えて退職したい場合
特に、弁護士が行う退職代行サービスを選ぶことで、より確実な法的保護を受けながら退職手続きを進めることができます。また、有給休暇が残っていれば、職場に一度も行かずに実質的な即日退職を実現することもできます。
迅速な退職や有給休暇の確実な消化を目指したい場合は、退職代行サービスの利用を前向きに検討するといいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ただし、退職に関する交渉は弁護士、もしくは団体交渉権を持つ労働組合の退職代行にしかできず、民間の代行業者は基本的に「意思の伝達」しかできないため、注意しておきましょう
また、損害賠償請求や懲戒解雇などに対して裁判などの法的な対応ができるのは弁護士のみのため、退職時のリスクに応じて代行業者を選ぶようにしましょう。




退職できない悩みと対処方法まとめ
退職は労働者の基本的な権利として法律で保護されており、会社による不当な引き止めや在職強要は違法となる可能性が高いものです。
会社から給与未払いの示唆や損害賠償の脅し、懲戒解雇の示唆などを受けた場合でも、これらのほとんどは法的根拠のない違法な行為です。このような状況に直面した場合は、一人で抱え込まずに、総合労働相談コーナーや労働基準監督署への相談、退職代行サービスの利用など、適切な方法を選択して対応することが重要です。
退職できずに仕事を続けることで心身の負担が大きい場合や、会社との交渉が困難な場合は、弁護士による退職代行サービスの利用を検討することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、スムーズな退職を実現することができます。
退職の決断をしたならば、自分のキャリアや人生を第一に優先して考え、適切な手段を選択して確実に会社を辞めるようにしましょう。
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
プロフィール画像.jpg)
本記事は、退職を巡るトラブルへの対処法を分かりやすく解説しており、特に、退職の権利や法律に基づいた対応策が具体的に解説しているので、会社から引き止められた場合でも冷静に対処できるでしょう。
退職代行サービスの活用も紹介されていますが、労働基準監督署や労働局に設けられている総合労働相談コーナー等での相談も有効な手段です。
総合労働相談の窓口で相談対応を行っている総合労働相談員は社会保険労務士や企業の人事担当経験者などの方で経験を元に親身に相談にのってくれます。
また、女性の方向けに同性の相談員も配属されています。
自分のキャリアと健康を大切にし、無理のない方法で円満な退職を目指しましょう。






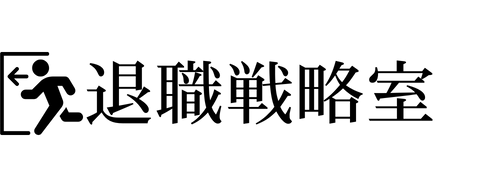
.png)
