引継ぎをする後任がいない場合でも退職して問題ない!辞めさせてもらえない場合の対処法も解説

「退職したいけれど、引き継げる後任がいない…」
「引き留められてしまって辞められない」
退職を決意したものの、会社への責任感から退職を躊躇したり、後任が見つかるまでと引き止められたりして、なかなか辞められない人が多いようです。
実は、後任が不在であっても法律上は退職して問題がなく、適切な引き継ぎ方法さえ知っていれば、円満に退職することが可能です。
この記事では、後任者がいなくても退職できる理由や注意点、具体的な対処法について解説していきます。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


引き継ぎができる後任がおらず退職に悩む理由
退職を決意したものの、「引き継ぎをする後任がいない」という状況に直面し、悩んでいる方は少なくありません。
特に、管理職などの責任あるポジションや専門性の高い業務を担っている場合、引き継ぎが十分にできないことによる不安が大きくなるでしょう。
後任がいない状況の退職に悩む主な理由は以下の通りです。
退職に悩む理由
それぞれ対処法と併せて解説していきます。
-150x150.png) 退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)
退職戦略室 編集部(キャリアコンサルタント)特に、真面目で責任感の強い方ほど、後任不在の状態で会社を去ることに不安や罪悪感を抱きがちです。
ですが、退職する会社の体制に気を取られ過ぎると、自分のキャリアアップのチャンスを逃してしまうこともあるため、注意しておきましょう。
後任がいない状態で退職することに罪悪感を覚えている
多くの方が後任不在での退職を躊躇する最大の理由は、会社に対する罪悪感です。
特に以下のような状況において、自分が退職することで迷惑がかかることへ罪悪感を感じやすいでしょう。
- 自分しか対応できない業務がある
- 上司や同僚から強く引き止められている
- これまで職場に貢献してきた実感がある
しかし、会社の業務は本来、一人の社員に依存するべきではありません。個人に業務が集中している状況こそが問題であり、それを改善するためにも、組織としては業務の標準化やマニュアル化を進めることが重要です。
そのため、後任がいない状況であっても、退職に対して過度な罪悪感を感じる必要はありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
後任の有無を問わず、退職による罪悪感を感じることは自然なことですが、組織運営は個人ではなく会社全体で行うものです。
個人が責任を背負いすぎるのではなく、会社の仕組みとして改善できる点に目を向け、退職に向けた引き継ぎ書類や体制を作ることが大切になるでしょう。


同僚への負担増加を心配している
後任がいない状態で退職すると、必然的に残された同僚が自分の仕事を引き継ぐことになります。
- 自分の業務を他のメンバーが分担することになる
- 既に多忙な同僚にさらに業務が割り振られる
- 過重労働でチームの士気が下がることが懸念される
ただし、会社側には適切な人員配置を行う責任があります。本来、「後任がいない」という人員配置不備の負担を個人が背負うべきではなく、会社が対策を講じるべき問題です。
退職を決意したのであれば、引き継ぎの工夫や業務整理に取り組みつつ、必要以上に自分を責める必要はありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
同僚への負担を気にかけるのは悪いことではありません。
ですが、自身が退職することを考えると、根本的なサポートはできません。
退職を決意した場合は、「引き継ぎ書類の作成」や「複数人へ分割した引き継ぎ」を行うことで、自分も周囲も納得のいく形を目指しましょう。
取引先への影響を懸念している
営業職をはじめとした対外的な窓口業務を担当している場合、後任者不在の状況で退職することで、取引先との関係性への悪影響を与える可能性があることも懸念点のひとつです。
こうした心配がある場合は、退職前に取引先へ適切に引き継ぎを行い、会社側と連携して対応策を考えることが大切です。具体的には以下の通りです。
- 取引先に事前に挨拶を行う
- 社内で後任が決まらない場合でも、チームでサポートできる体制を整える
- 主要な業務の進捗や取引先の要望を記録して引き継ぐ
取引先への影響を最小限にするためには、事前の引き継ぎや連携が不可欠です。退職は個人の決断ですが、円滑に進めるための準備をしっかりと行い、取引先との信頼関係を最後まで大切にしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
自身の後任者がいない場合であっても、チームで状況を共有し、複数人に分散して取引先の引き継ぎを行うようするといいでしょう。


引き継ぐ後任がいなくても退職して問題ない理由
前述したように、後任がいないのに退職することに対し、不安や罪悪感を抱えている方は少なくありません。ですが、法的には後任がいなくても退職することは何ら問題ありません。
引き継ぐ後任がいなくても退職して問題ない理由は以下の通りです。
退職して問題ない理由
それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
終身雇用の時代が終わり、個人のキャリアの責任を会社ではなく自分自身が負う時代において、退職・転職は個人の自由です。
退職時に後任がいないことを気にかけることはあっても、自分自身のやりたいことやキャリア設計に基づいた選択をするように心がけましょう。
後任者の確保は経営者・人事の責務
まず明確にしておきたいのは、適切な人員配置を行い、円滑な業務継続体制を構築するのは、経営者や人事部門の責任だということです。そのため、イチ従業員が後任の確保について責任を負うべきではありません。
企業運営において、人材の採用・配置・育成は経営の根幹に関わる重要な業務です。特に以下のような点は、会社が主体的に取り組むべき課題です。
- 特定の社員に業務が集中しない組織体制の構築
- 業務の「見える化」と標準化の推進
- 社員の突然の退職に備えたバックアップ体制
「一人の社員が辞めただけで業務が回らなくなる」という状況自体が、実は会社側のリスク管理ができていないことの証左です。
そのような状況を作り出したのは個々の従業員ではなく、組織体制を構築すべき経営層の責任であることを理解しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
なお、退職を伝えた後に、後任のアサインや採用を行うことは会社側で行い、その人へ引き継ぎを行うことが一般的ですが、退職日に間に合わない場合は現在の従業員に分散して引き継ぐ形で問題ありません。
「後任者が見つかるまで待って欲しい」という引き止めを受ける場合がりますが、安易に引き受けないように注意しておきましょう。
退職の自由は法律で保障されている
日本の法律では、労働者の「退職の自由」が法律で保障されており、後任者がいない状況でも退職して問題ありません。
特に重要なのは、正社員の場合は退職届を提出してから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても法的に退職が成立するという点です。そのため、会社が「退職を受理しない」「後任が見つかるまで待ってほしい」と主張しても、法的効力には影響しません。
もちろん、円満な退職のために可能な限り協力することは大切ですが、あくまでも善意に基づく協力であり、義務ではありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
契約期間中の有期雇用社員は、実は退職に法的制限があり、「やむを得ない理由」や「会社の合意」が必要になります。
体調不良や家族の介護などの「やむを得ない退職理由」ではない場合は、会社と合意を得られるように交渉する必要があります。
すぐに退職したい事情がある場合は、退職代行サービスの利用も検討するといいでしょう。
>おすすめ退職代行サービスの比較はこちら




後任探しを理由にした引き止めは不当である
「後任が見つかるまで辞めないでほしい」という引き止めは、実は会社側の都合を一方的に押し付けるものであり、不当な要求といえます。このような引き止めには以下のような問題点があります。
- 「後任が見つかるまで」という期限が明確ではない
- 後任採用を進めている最中に他の人が辞めてしまう可能性がある
- 退職希望者の転職や人生設計が犠牲になる
また、退職を申し出た後に、突然の昇給や処遇改善を提案されることもありますが、これも実現するか不透明な上に、一時的な引き止め策である可能性が高いといえるでしょう。
短期的な条件改善に惑わされず、自分のキャリアプランに沿った決断をすることが重要です。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
一部のブラック企業では、「後任者を自分で探してこないと辞められない」とリファラルを強要される場合もあります。
当然のことながら、この要求に法的根拠は一切なく、また、心情としても、そのような職場に人材を紹介することはできないでしょう。


後任不在でも引き継ぎをして円満に退職する5つのステップ
ここまで、後任がいなくても退職する権利があることを解説してきましたが、実際には会社や同僚への配慮として、できる限り円満な形で退職したいものです。
そこで、後任不在の状況でもスムーズに引き継ぎを行い、トラブルなく退職するための5つのステップを以下に解説します。
退職日から逆算して最低1ヶ月以上の引き継ぎ期間を設定する
後任がいない状況では、引き継ぎに十分な時間を確保することが重要です。理想としては、退職の意思を伝えてから実際に退職するまでに、最低でも1ヶ月以上の期間を設けましょう。
ただし、転職に悪影響が出ないようにするためには、退職の申し出の際に以下の点に注意することが大切です。
- 具体的な退職日を明示する
- 引き継ぎ期間の具体的な予定を提案する
- 退職日を記載した退職届を提出する
特に業務が複雑であったり、担当範囲が広かったりする場合は、より長い引き継ぎ期間を設定することも検討しましょう。ただし、無期限に延長することは避け、必ず具体的な退職日を設定することが重要です。
この期間設定は、会社側に引き継ぎ計画を立てる時間を与えると同時に、自身が心理的にも準備を整える期間にもなります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
だらだらと退職日を引き延ばされることが無いように、引き継ぎと有給の消化計画に応じた退職日を最初に提示するようにしましょう。
日々の業務内容を詳細なマニュアルにまとめる
後任不在の状況では、誰が引き継ぐことになるにせよ、業務の詳細を体系的にまとめたマニュアルが非常に役立ちます。日常的に行っている作業の手順や注意点、トラブル対応方法などを文書化しましょう。
- 業務フローを図や表を使って視覚的に説明する
- 専門用語やシステム独特の言い回しには説明を付ける
- 定期的な業務と不定期な業務を区別して整理する
- スクリーンショットなどを活用し、システム操作手順を詳細に記録する
特に自分しかわからない業務のコツや暗黙知を言語化することに注力しましょう。「当たり前」と思っていることこそ、他の人にとっては新しい情報である可能性が高いため、細かく作成することがおすすめです。
必要書類とデータの保管場所をリスト化する
業務に必要な書類やデータファイルの保管場所を明確にリスト化することで、後任者や引き継ぎを受ける同僚が必要な情報にスムーズにアクセスできるようになります。
リスト化すべき情報には以下のようなものがあります。
- 紙の書類やファイルの保管場所と分類方法
- デジタルファイルの保存場所とフォルダ構造
- 社内システムやクラウドサービスのアクセス方法とパスワード
- 定期的に参照する外部サイトや情報源のリスト
特に重要度の高いファイルや、アクセス頻度の高いデータについては、優先的にリスト化し、わかりやすく整理しておきましょう。
必要に応じてインデックスや付箋を活用し、物理的な書類も探しやすく整理することが重要です。
各業務を複数の同僚に分散して引き継ぐ
自身の業務をそのまま引き継げる後任者がいない場合、担当業務を複数の同僚に分散して引き継ぐことになります。
一人に全ての業務を押し付けるのではなく、業務の性質や難易度に応じて適切な人に割り振りましょう。
- 業務をできるだけ小さなタスクに分解する
- 各同僚のスキルセットや現在の業務量を考慮して割り当てる
- 担当者以外でも情報共有できる体制を作る
分散して引き継ぐことで、一人あたりの負担を軽減できるだけでなく、属人化を防ぎ、組織としてのノウハウ共有にもつながります。また、引き継ぐ側も段階的に進められるため、より丁寧な引き継ぎが可能になります。
進行中の案件状況を時系列で整理する
最後に、現在進行中のプロジェクトや案件について、時系列で整理しておくことが重要です。
特に後任がいない状況では、複数の人が分担して対応することになるため、全体像を把握しやすいように情報を整理する必要があります。
- 案件ごとにスケジュールと進捗状況を明確に記録する
- 今後予定されているタスクやマイルストーンを具体的に示す
- クライアントや取引先の連絡先情報を整理する
- 案件に関する過去のやり取りや重要な決定事項をまとめる
特に重要なのは、「いつ、何が、誰によって行われるべきか」を明確にしておくことです。退職後に「あの案件はどうなっているの?」と慌てることがないよう、計画的に整理しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
これら5つのステップを丁寧に実行することで、たとえ後任が不在であっても、会社の業務に大きな支障をきたすことなく退職することができます。
また、丁寧な引き継ぎは自身の仕事やスキルの棚卸にもつながるため、今後のキャリアにおいても有用な時間になるでしょう。
引継ぎの後任不在で退職する場合の法的知識
退職を考える際に、「後任がいないのに辞めると法的に問題があるのではないか」と心配する方も多いでしょう。ここでは、後任不在で退職する場合の知っておくべき以下の法的知識について解説します。
知っておくべき法的知識
それぞれ詳しく解説していきます。
後任がいない状況で退職しても法律上は問題ない
結論からお伝えすると、会社が後任者を確保できていない状況であっても、法律上は問題なく退職することができます。
後任を確保することに関する法律上の定めはないため、会社から「後任が見つかるまで待って欲しい」という主張はあくまで要望のため、従わなくても問題ありません。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
前述のように、採用や異動にとり後任者の確保は会社側が対応すべきことであり、退職者がそれを待つ必要はありません。
ただし、担当業務の引き継ぎは適切に行う必要があるため、引き継ぎ書類の作成や、複数人への引き継ぎで対応するようにしましょう。
正社員の場合は退職通知から2週間後に辞められる
正社員として雇用されている場合、退職の意思表示をしてから2週間経過すれば、会社の承諾がなくとも法的に退職が成立します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
そのため、正社員(無期雇用契約社員)が最短の退職を目指す場合は以下の流れで辞めることが可能です。
- 退職の意思表示(口頭でも可能だが、書面が望ましい)
- 2週間の経過
- 法的に雇用契約の終了が成立
※正社員の場合
退職の申し入れの際、会社側が「退職届を受理しない」と主張しても、退職の意思表示から2週間経過すれば雇用契約の終了が成立します。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
就業規則に「退職の1ヶ月前に申し出ること」などの規定がある場合、一般的には、会社への配慮として就業規則の規定も尊重することが望ましいですが、2週間の法定期間を超えて強制的に就業を続けさせることは法的に難しいとされています。
>最短で退職するには?法定の2週間ルールや就業規則より早く辞める方法も解説




引き継ぎを一切しなければ損害賠償を請求される可能性がある
退職する権利は保障されていますが、退職に際して「引き継ぎを一切行わない」など、明らかに会社に損害を与える行為は避けるべきです。
引き継ぎに関する事項が法律に定められているわけではないものの、労働契約に基づく命令によって引き継ぎを行うのは、民法の基本原則である「信義則上の義務(以下参照)」といえるでしょう。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
ただし、通常の引き継ぎを行った上で退職する場合に、「後任がいないことによる業務の混乱」を理由に損害賠償請求されることは、基本的に考えづらいでしょう。
法的知識を身につけておくことで、不当な引き止めや脅しに対しても冷静に対応できるようになります。退職に関する法的権利を理解したうえで、円満な退職を目指しましょう。


退職の引継ぎの後任がいない際の注意点
後任不在の状況で退職する際には、以下の点に注意することが重要です。
それぞれ詳しく解説していきます。
退職日を無闇に譲歩しない
退職を申し出た際、後任がいない状況においては「もう少しだけ待ってほしい」「あと1ヶ月だけ」など、退職日の延期を求められることが少なくありません。
会社側の事情を汲むことも大切ですが、自分のキャリアや次の転職先の方が優先事項が高いことを自覚し、くれぐれも「後任が見つかるまで」のような交渉に応じないように注意しておきましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
特に、既に転職先の入社日が決まっている場合は、退職日が延びることが迷惑をかける可能性があります。
円満退職を目指しつつも、自身のキャリア設計や新たな仕事への挑戦を最優先に考えましょう。
引き継ぎ完了の基準を明確にする
後任が決まらない場合、引き継ぎ作業が長引くことがあります。
ですが、その際においても「まだ引き継ぎが終わっていない」という理由で退職を引き延ばされないよう、引き継ぎ完了の基準を明確にしておくことが重要です。
そのため、以下のポイントを意識して引き継ぎをするようにしましょう。
- 主要な業務のマニュアルを作成する
- 担当業務ごとに引き継ぎの進捗を記録する
- 上司やチームと引き継ぎの完了条件を事前に話し合う
後任がいない場合であっても、引き継ぐべき項目や分散して引き継ぐ担当者をリスト化して進めることがオススメです。各項目の完了目標日を設定するなど、具体的な基準を設け、会社側と合意の上で引き継ぎをするようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
基本的に、退職に対して「完璧な引き継ぎ」はありません。
退職日までに現実的に完了させられる計画を立て、重要事項が漏れないように注意して引き継ぐようにしましょう。
カウンターオファーを安易に受けない
退職を申し出ると、会社側が給与アップや待遇改善を提示し、引き止めようとすることがあります。これを「カウンターオファー」と呼びますが、安易に受け入れるのはリスクが伴います。
しかし、カウンターオファーを受け入れて残留を決めた社員の約4割が半年以内に退職するという調査結果が出ています。
そのため、オファーを受けた場合は、退職を決意した理由を振り返り、本当に今の会社に残ることがベストなのかを慎重に判断する必要があります。一時的な条件改善に惑わされず、自分のキャリア目標や人生計画に照らして冷静に判断しましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
カウンターオファーに応じると、一時的に条件は改善されても、長期的には同じ問題に直面する可能性が高いです。冷静に状況を見極め、本当に自分にとってベストな選択をしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
また、実際に退職せずに現職に残った場合であっても、提示された待遇改善や昇格が実現しない場合もあります。
そのため、もしもカウンターオファーについて真剣に検討する場合は、その確実性についても必ず確認する必要があるでしょう。


引き継ぎの後任不在で退職できない場合の対処法
退職を決意したものの、後任が決まらず「退職できない」と会社から引き止められるケースは少なくありません。しかし、退職は労働者の権利であり、適切な手順を踏めば確実に退職できます。
ここでは、後任不在でも退職を進めるための具体的な対処法を解説します
複数の社員へ分散して引き継ぐ計画を立てる
自身の担当業務を全て引き継げる後任が確保できない場合、引き継ぎの負担を一人に集中させず、複数の社員で分担する方法が有効です。
「後任がいないから退職させられない」と引き留められた場合は、既存の複数の社員に業務を分散して引き継ぐ具体的な計画を立て、上司に提案するようにしましょう。
会社にとっても、業務の属人化を防ぐことは長期的な目線で見るとメリットがある提案のため、受け入れやすいといえるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
引き継ぎは個人の責任ではなく、会社全体で取り組むべきものです。
計画的に分散することで、業務の属人化を防ぎ、円滑な退職につなげましょう。
労働局の総合労働相談コーナーに相談する
退職を申し出た際、後任がいないことを理由に退職を拒否されたり、高圧的な態度で引き止めを受ける場合があります。
この場合、複数の社員へ分散して引き継ぐ提案をしても聞く耳を持たず、ひどい場合は退職届を破り捨てられてしまうケースもあるようです。
労働局の相談窓口では、具体的な法的根拠をもとに対応策をアドバイスしてくれるため、会社との交渉に不安がある場合は活用しましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
後任者の有無にかかわらず、基本的に会社が一方的に退職を拒否することはできません。
もしも退職を認めてもらえない場合は、公的機関に相談するようにしましょう。
>退職できないときの対処法と相談先はこちら




退職代行サービスの利用を検討する
何度交渉しても会社が退職を認めない場合、最終手段として、退職代行サービスの利用を検討することも一つの選択肢です。
退職代行を使って辞めることで、以下のようなメリットがあります。
- 直接退職を伝える必要が無い
- 引き継ぎを書面で済ませられる
- 一度も会社に行かない即日退職が可能なケースもある
特に強引な引き止めが続いている場合や、退職を申し出たことでパワハラや嫌がらせを受けている場合には、精神的な負担を軽減するために有効な解決策となるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
代行サービスを使うことで、退職日までの出勤日相当の有給休暇が残っていれば、実質的な即日退職も可能です。
ただし、退職に伴う「交渉」が必要になる場合は、団体交渉権を持つ労働組合、もしくは弁護士の退職代行以外は対応できないため、注意しておきましょう。
>おすすめの退職代行サービス比較はこちら




引き継げる後任がいない場合の退職に関するよくある質問
後任者がいなくても退職していいのか?
後任の確保は会社の責任であり、個人が負うべき負担ではありません。
円満退職のためには引き継ぎにはしっかり行うことが望ましいですが、後任がいないことを理由に退職の権利が制限されることはありません。
後任を採用するまで待って欲しいと言われたのですが?
「後任を採用するまで待ってほしい」という会社側の要請には法的拘束力はなく、応じる義務はありません。
対応としては、「最大でも○月○日までは協力できますが、それ以降は退職させていただきます」と具体的な期限を提示するのが有効です。
後任者がいない場合どのように引き継ぎをすればいいですか?
後任不在の場合は、詳細な業務マニュアルの作成と複数の同僚への分散引き継ぎが効果的です。
担当業務を分解し、複数の同僚に分散して引き継ぐことで、一人あたりの負担を軽減できます。
引き継ぐべき後任者がいない状態で退職すると損害賠償請求されますか?
適切な引き継ぎを行った上で退職する場合、損害賠償請求されるリスクは非常に低いです。
ただし、引き継ぎを全く行わずに突然退職し、結果的に明確な損害が発生した場合は損害賠償を請求されるリスクがあるでしょう。
退職代行を使えば引き継ぎをせずに辞めれますか?
退職代行サービスは退職の意思表示や手続きをサポートするものであり、引き継ぎ義務を免除するものではありません。
理想としては、退職代行サービスを利用する前に、基本的な引き継ぎ資料を作成しておくことが望ましいですが、難しい場合は、退職代行から退職の申し入れを行った後に引き継ぎ書類を作成することも可能です。
引き継ぐ後任がいなくても退職して問題ない理由まとめ
本記事では、後任がいない状況での退職に悩む方々に向けて、退職しても問題ない理由や法的根拠、退職できない場合の対処法などを解説してきました。
後任不在の状況で退職することに不安や罪悪感を感じる方は多いですが、後任者の確保や組織体制の再構築は会社が対応するべきことであり、退職者が主体的に考えることではありません。
適切な引き継ぎを行った上での退職は、決して無責任な行為ではありません。自分自身のキャリア設計と人生を最優先し、新しい仕事へ挑戦するようにしましょう!






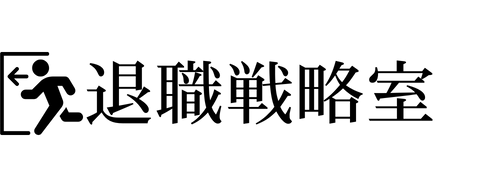
.png)





