【弁護士監修】退職届を受け取ってもらえない!受理されない場合の対処法と円満退職のコツを解説

退職届を提出したものの、「人手不足だから」「後任が見つかるまで」といった理由で受理を拒否されるケースは少なくありません。
しかし、正社員の場合は退職の申し出から最短2週間で退職が成立すると法律に定められており、退職届の受け取りを拒否することはできません。
参照:e-Gov法令検索「民法第627条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ」
本記事では、退職届が受け取ってもらえない理由や具体的な対処法、円満退職のコツまで徹底解説していきます。
退職に悩んでいる人におすすめ!
退職後のキャリアに悩んでいる方は、オンラインキャリア相談サービス「キャリアバディ」をご活用ください。
「有料のキャリア相談」だからこそ、転職エージェントとは異なる中立的な視点で、キャリアの専門家があなたに寄り添ったサポートを行います。
\まずは相談相手を探す!/


会社側に退職届を受け取ってもらえない理由
退職届を提出したのに、上司や会社側に受け取ってもらえず、自身のキャリア設計や新しい挑戦の障害になることは少なくありません。
ではなぜ、会社側は退職届の受けとりを拒否してまで、引き止めを行うのでしょうか?会社に退職届を受け取ってもらえない理由は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
人材不足が深刻なため
退職届を受け取ってもらえない場合、深刻な人材不足が原因になっているケースが多々あります。
少子高齢化に伴って労働人口が減少している近年、多くの企業で人材不足に悩まされています。特に中小企業や専門職の分野では新たな人材を確保することが難しく、なかでも、専門的なスキルや豊富な経験を持つ社員の退職は大きな痛手となります。
-150x150.png) 退職戦略室 編集長
退職戦略室 編集長人材不足を理由に退職を引き止められる場合、「後任を採用できるまで待って欲しい」という引き止めを受けることが多いでしょう。
ですが、後任採用がいつになるか分からないことに加え、待っている間に別の人が退職するとさらに退職しづらくなってしまいます。
円満に退職するためには、早めに上司と相談し、人手が不足していても引き継ぐための建設的な計画を練るようにしましょう。


繁忙期で退職されると業務が回らないから
繁忙期に退職を申し出ると「今は忙しい時期だから」と拒否されることがあります。
プロジェクトの節目や決算期、店舗の繁忙期など重要な時期には、業務継続を優先するあまり、個人の意思よりも組織の都合を優先させようとする傾向があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ただし、「繁忙期だから退職を後にして欲しい」という会社側の要望を鵜呑みにすると、退職時期がズルズルと後ろ倒しになり、キャリアの転機を逃しかねません。
転職のチャンスを逃さないようにするためには、繁忙期であってもしっかり退職の交渉をするようにしましょう。
成長を期待されているから
上司や経営者から「この社員はまだ成長できる」と期待されている場合、退職届を受け取ってもらえない場合があります。
この場合、「上司や経営者の期待に応えたい」と考えること自体は誤りではありません。ですが、中長期的な視点で自分のキャリアを見つめ、現職での成長が望めない場合は、退職の意思を明確に伝えた方がいいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
この場合、希望のポジションや給与などを条件に残留を促す「カウンターオファー」の提案を受ける場合があります。
しかし、退職申し出時の条件改善の提案は、結果的に実現しない場合もあるので注意が必要です。
もしもカウンターオファーを検討する場合は、実現可能性についても詳しく確認するようにしましょう。
離職率を上げたくないため
企業にとって離職率は重要な指標です。
離職率が高いと「働きにくい職場」という評判が広まり、採用にも悪影響を及ぼします。また、上場企業の場合は株主や投資家に対する企業評価にも関わるため、会社側は離職率を低く抑えようと退職を思いとどまらせようとする場合があります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
上場企業の場合は離職率が四季報に掲載され、労働集約型のビジネスモデルの場合、採用数や離職率がIRに掲載される場合もあります。
そのため、マネジメントに携わる上司としては出来る限り退職を防ぎたいと考えるのは自然なことです。
ですが、終身雇用制度が実質的に終わった現代において、自身の人生やキャリアの責任は自分しか持つことができないため、中長期的なキャリア設計の上で、冷静に退職を決断するようにしましょう。
上司の人事評価に関わるから
多くの企業では、部下の離職率が上司の評価に影響します。
前述のように、離職率は直属の上司のKPIに組み込まれている場合があり、退職の引き止めを行うことも管理職の仕事のひとつです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
ただし、「退職届を受け取らない」という方法により引き止めは適切な手段ではなく、あくまで対話を通して引き止めの交渉をするべきといえます。
強硬な引き止めを受けた場合は、毅然とした態度で退職の意思を伝え、どうしても退職届を受け取ってもらえない場合は、記録が残る「内容証明郵便」で送付することを検討しましょう。
会社側が退職を拒否することはできるのか?
退職届を提出したのに受け取ってもらえない場合、「このまま会社を辞められないのでは」と不安になるでしょう。
では、「退職届を受け取らない」という会社の対応について、法的な正当性はあるのでしょうか?退職に関するルールは、実は雇用形態によって異なるため注意が必要です。
無期雇用の正社員や、有期雇用の契約社員や派遣社員の退職に関する法定ルールは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
正社員の場合は退職の拒否はできない
正社員(無期雇用契約)の場合、法的に会社側が退職を拒否することはできません。
日本国憲法第22条第1項において職業選択の自由が認められており、また、民法第627条第1項では「無期雇用の場合は退職の申し入れから2週間で退職可能」であることが定められています
また、退職の意思は必ず退職届によらなければならないというものでもないため、本人が何かしらの方法で会社側に退職の意思を通知すればそのまま辞めることができます。
ただし実務上は、就業規則で「退職希望日の1ヶ月前までに退職届を提出すること」などと定められているケースが多いため、特に会社が不当な対応をしていないのであれば、こうした社内ルールにも配慮することが望ましいでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
会社が退職届を受理しないなど不当な対応をするようであれば、「内容証明郵便の郵送」、「メールやLINEでの通知」など形に残る方法で退職意思を通知、「退職代行サービスの利用」を検討するといいでしょう。
契約社員でも一定の条件を満たせば退職可能
契約社員やアルバイト・パートなど期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)や派遣社員の場合は、原則として雇用元との契約期間が満了するまでは働く義務があります。
しかし、以下の条件を満たせば、雇用契約の期間中でも退職可能です。
- やむを得ない理由がある場合
- 契約から1年以上経過している場合
- 会社側の合意が取れた場合
それぞれ詳しく解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
有期雇用の契約社員やパートとして働いている場合、実は期間中の退職においては正社員より退職に関するハードルが高いといえるでしょう。
会社から合意が取れれば問題ありませんが、退職を拒否された場合は、戦略的に交渉をする必要があります。




やむを得ない理由がある場合
民法第628条では、「雇用期間中であっても、やむを得ない理由があればすぐに退職可能」と定められています。
「やむを得ない退職理由」には以下のようなケースが該当します。
- 本人の病気やケガにより勤務継続が困難な場合
- 家族の介護が必要になり勤務継続が困難な場合
- ハラスメント(パワハラ・セクハラなど)が改善されず就労困難となる場合
- 労働条件が契約時と大きく異なる場合
(もしくは違法に引き下げられた場合)
このような退職理由がある場合は、雇用期間中であっても直ちに退職することが可能と考えられます。
そのため、上記に当てはまる場合は、会社側に対してその理由を具体的に説明して退職する旨を通知すると良いでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
なお、職場のハラスメントや労働条件の一方的引下げが退職理由の場合、自分から退職する場合であっても「会社都合退職」にできる可能性があります。
自己都合退職と比べ、会社都合退職の方が失業給付の受給条件が良くなるため、必ず確認しておきましょう。
契約から1年以上経過している場合
労働基準法第137条では、契約期間が1年を超える有期労働契約において、1年を経過した後は、労働者はいつでも退職できると規定しています。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
1年以上の雇用契約を結ぶケースは稀ですが、これに該当している人は1年以上働けばいつでも退職することが可能になります。


会社側の合意が取れた場合
雇用契約の期間中でも、会社側と合意すれば退職することができます(合意解約)。
また、会社側は有期雇用の労働者を強く遺留するということは多くないため、基本的には退職を申し入れればスムーズに合意によって退職できることが可能性が高いでしょう。
ただし、会社が期間途中の解約を頑なに承服しない場合は、戦略的に対応する必要があるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
雇用契約期間中の退職において、「退職のやむを得ない理由」に該当しない人の場合、合意退職を目指すことが一般的です。
そのため、会社側が退職に納得するように、退職時期や引き継ぎ計画など、適切な条件を提示すべき場合もあるでしょう。




退職届が受け取ってもらえないまま辞めると起きうるトラブルと対処法
万が一、退職届が受け取ってもらえないまま退職日を迎えると、様々なトラブルが発生する可能性があります。退職届が不受理のまま退職する場合に起きうるトラブルは以下の通りです。
それぞれ、対処法とともに具体的に解説していきます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
不要なトラブルを避けるためにも、基本的には合意を得られるように努めることが望ましいですが、どうしても退職届を受け取ってもらえない場合は「退職代行サービス」や「総合労働相談コーナー」への相談を検討するといいでしょう。


退職前の有給休暇の取得を認めてもらえない
退職前に残っている有給休暇を消化しようとしたところ、人手不足や引継ぎの必要性を理由に拒否されることがあります。
対処法としては、有給休暇の申請を書面やWEBシステムなど記録が残る形で行うことが重要になります。それでも、会社側が不当に拒否する場合は、労働基準監督署に相談するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職時でなければ、有給休暇の取得が事業運営の妨げになる場合は「時季変更権」を行使することが可能です。
ですが、退職する場合は退職日以降に有給を取らせることができないため、有給休暇の取得を拒否することはできません。
どうしても会社側が納得しない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや退職代行サービスへ相談するようにしましょう。




給与を支払ってくれない
退職届を受け取ってもらえないまま退職すると、未払いの給与や残業代の支払いを拒否されることがあります。
しかし、労働基準法第24条により、働いた分の給与は必ず支払われる権利があります。
参照:e-Gov法令検索「労働基準法 第24条」
給与の不払いなどを受けた場合は、働いた日時や業務内容の記録を残し、労働基準監督署に相談しましょう。それでも解決しない場合は、弁護士に相談の上、不払い賃金の請求を行うようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
賃金の未払いは許されることではありませんが、転職先が決まっている場合は、裁判などに時間を使うことができずに断念してしまうケースもあるようです。
退職に伴って、給与の未払いなどのトラブルが発生しそうな場合は、退職届の受け取りを拒否された時点で「弁護士の退職代行」に相談し、退職時点から会社との交渉を依頼することも検討しましょう。


離職票や源泉徴収票をもらえない
退職届を受け取ってもらえないまま退職日を迎えることで、転職先の入社に必要な源泉徴収票や、失業手当の受給に必要な離職票などの書類を会社が発行してくれないケースもあります。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職が成立している以上、対応の公的機関に相談することで退職書類を受け取ることは可能ですが、上記の対応には時間も労力も必要になります。
そのため、可能な限り退職に対する会社の合意を得ることが望ましいでしょう。
損害賠償請求を仄めかされる
退職を伝えた際に「いま辞めるなら損害賠償を請求する」などと脅され、退職届を受け取ってもらえない場合があります。
しかし、通常の退職であれば労働者に損害賠償責任が発生することはほとんどなく、会社側もそれを理解していることが多いでしょう。そのため、損害賠償を持ち出すのは「退職させないための脅し」であることが多く、過剰に心配する必要はありません。
もしどうしても不安という場合は、労働基準監督署や、法的対応が可能な弁護士の退職代行に相談することがおすすめです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
弁護士の退職代行に依頼することで、高い交渉力で有給休暇の取得や退職日に関する「交渉」ができるだけではなく、会社側が損害賠償を持ち出した際にも適切な対応が可能になります。
そのため、不要なトラブルを避けるためには、退職届の受け取りを拒否された時点で、弁護士の退職代行に相談することを検討するといいでしょう。


懲戒解雇にすると脅される
退職届を受け取ってもらえない状況のまま辞めることで、「懲戒解雇にする」と脅されることもあります。
しかし、懲戒解雇の有効性が認められるハードルは極めて高く、単に退職を申し出たことを理由にすることで適法な懲戒解雇をすることは現実的ではありません。
退職届と退職願の違いを理解して適切に選択する
退職の意思を会社に伝える際の書類には、「退職届」と「退職願」の2種類がありますが、退職の意思を表示するという点で法的な違いはほとんどありません。
ただし、会社の慣習や就業規則などによって使い分けが求められることもあるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、退職届と退職願の違いについて、理解しておくべき以下のポイントを解説していきます。
それぞれ詳しく解説していきます。
退職届と退職願に法的効力の違いはない
退職届と退職願はいずれも「退職の意思表示」を行うものであり、法的効力に違いはありません。
ただし、企業によってはまず「退職願」を提出し、会社側の了承を得たうえで、退職日が決まった段階で「退職届」の提出を求めるケースもあります。
このような企業では、「退職願」はあくまで退職の希望を伝えるものであり、会社の承認が前提となります。したがって、円満に退職したい場合や話し合いの余地を残したい場合には、まず退職願を提出する方が望ましいでしょう。
このように、退職届と退職願の法的な差はないものの、会社ごとの慣習やルールに応じて使い分けることで、スムーズに退職手続きを進めることができます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
基本的には退職願から提出し、会社側の了承を得たうえで退職届を出すことが望ましいといえるでしょう。
ですが、会社側に退職を認めてもらえない無期雇用者の場合でも、退職届を提出することで最短2週間後に辞めることが可能になります。



一部のWEB記事では、「退職願はあくまでお願いであり、退職の通知とは異なる」と説明されていることもあります。しかし、重要なのは「退職したいという意思を明確に示すこと」です。
退職届も退職願も、いずれも労働者が退職の意思を示すための書面である点に変わりはなく、法的な効力に違いはありません。



ただし、会社によっては「退職願は合意退職の申し出にすぎず、退職の意思表示とはいえない」と主張してくる場合もあります。
そのような事態を避けるためにも、退職の意思が固まっている場合は「退職届」として提出したほうが無難といえるでしょう。
また、退職届や退職願は、一度会社に受理されると「退職の合意が成立した」と判断され、原則として撤回できなくなる可能性があります。そのため、これらの書類を提出する際は、内容やタイミングについて慎重に判断するようにしましょう。
状況に応じた使い分けのポイント
退職届と退職願は、退職希望者を取り巻く状況に応じて使い分けることが重要です。以下に、状況別の使い分けポイントを解説します。
円満退職を希望する一般的なケースでは、まず退職願を提出するのが慣例とされています。退職願を提出して会社側の理解を得た上で、最終的に退職届を提出するという流れが一般的です。
この方法であれば、会社側との良好な関係を維持しながら退職手続きを進めることができます。
一方、以下のようなケースでは、最初から退職届を提出することを検討すべきでしょう。
- 退職願を出しても受け取ってもらえない場合
- パワハラやセクハラなどの問題があり、早急に退職したい場合
- 繰り返し退職の意思を伝えているのに、引き止めにあっている場合
- 会社との交渉が難航し、これ以上の話し合いが困難と判断した場合
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
円満退職を目指す場合は「退職願」から提出し、退職願を受け取ってもらえないなど激しい引き止めに合っている場合は「退職届」を提出するようにしましょう。
撤回可能性の違いと提出時の注意点
退職届と退職願には、撤回可能性においても大きな違いがあります。これは提出前に十分理解しておくべき重要なポイントです。
退職願・退職届はいずれも法的な意思表示であり、一度提出すると原則として一方的に撤回することはできません。民法第540条によれば、解約の意思表示は相手方に到達した時点で効力が生じ、その後の撤回は相手方の同意がない限り認められません。
つまり、退職願や退職届を出した後に「やっぱり辞めるのをやめたい」と思っても、会社側が撤回に同意してくれない限り、予定通り退職することになります。
ただし、「退職願」が会社側の承認を前提としている場合は、社内で承認される前であれば比較的容易に撤回することができます。「家族と相談した結果、もう少し働き続けることにしました」などと伝えれば、多くの場合、会社側も柔軟に対応してくれるでしょう。
退職届を受け取ってもらえない場合の対処法
退職届を提出しても受け取ってもらえない状況は、精神的に大きな負担となります。
しかし、正社員は法律上は自由な退職が認められており、有期雇用社員の場合でも、「やむを得ない理由」があればすぐに退職可能です。そのため、適切な対処法を知っていれば確実に退職できます。
退職届が受け取ってもらえない場合の対処法は以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
上司の上司や人事部門に相談する
直属の上司が退職届の受け取りを拒否している場合は、まず上司の上司や人事・労務部門に相談しましょう。
相談する際は、感情的にならず冷静に状況を説明し、退職理由を前向きに伝え、法律上の権利についても必要に応じて言及しましょう。人事・労務部門は従業員と会社の間に立つ存在で、社内規定や法律に詳しいため、適切な対応を期待できることが多いです。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
特に、上司が自身の評価が下がることを気にして退職届の受け取らない場合は、上層部に掛け合うことで解決する場合が多いでしょう。


内容証明郵便で退職届を送付する
上司に直接受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便(※)を利用して退職届を送付する方法が効果的です。
内容証明郵便で退職届を送付する際は、退職日や退職理由、氏名、捺印を明記し、「退職の意思表示」であることを明確に記載します。
内容証明郵便は特定の文書を送付した事実が公的に証明できるため、「受け取っていない」という言い逃れを防ぎ、確実に退職することが可能です。



なお、内容証明郵便はあくまで文書を送付したことを証明する手段のひとつに過ぎません。
そのため、退職の意思を会社に伝える方法としては、メールやLINEなど、記録が残るものであれば同じ効果があります。
もし内容証明郵便を送るのが手間だと感じる場合でも、メールやLINEで退職の意思をはっきり伝えておけば、それだけで十分といえるでしょう。
労働基準監督署に相談に行く
退職届の受理拒否が続く場合は、労働基準監督署への相談も有効です。
相談の際は、雇用契約書や就業規則のコピー、これまでのやり取りの記録などを持参し、状況を時系列で整理して説明できるよう準備しましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
労働基準監督署では状況に応じて会社側への指導や助言を行ってくれることがあります。
無料で相談することができるため、退職の受け取り拒否に悩んだら、まずは相談してみるといいでしょう。


弁護士に相談して法的対応を取る
退職届を受け取ってもらえないだけではなく、損害賠償請求や懲戒解雇などで脅されている場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
弁護士に相談するメリットとしては、法的知識に基づいた専門的なアドバイスが得られることや、弁護士名義の内容証明郵便で会社側にプレッシャーをかけられることなどが挙げられます。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職を申し出ることで、損害賠償や懲戒解雇をチラつかせられては、安心して転職活動を進めることもできません。
安心・安全な退職をしたい場合は、弁護士の退職代行へ相談しましょう。
>おすすめの弁護士の退職代行はこちら




退職代行サービスの活用を検討する
会社側が退職を認めてくれない場合は、退職代行サービスを利用することがおすすめです。
退職代行を使えば、退職の意思表示や会社との交渉を代行してくれるため、直接会社と対峙する精神的負担を軽減しつつ、確実な退職を目指すことができます。
| 弁護士の退職代行 | 労働組合の退職代行 | 民間の退職代行 | |
|---|---|---|---|
| 退職意思の伝達 | 対応可能 | 対応可能 | 対応可能 |
| 退職に伴う交渉 | 対応可能 | 対応可能 | 対応不可 |
| 損害賠償請求などの 法的対応 | 対応可能 | 対応不可 | 対応不可 |
| 利用料金の相場 | 5~10万円 | 2~4万円 | 2万円前後 |
相談する退職代行サービスを選ぶ際は、料金の相場だけではなく対応可能範囲や実績・口コミ、24時間対応の有無など、様々な要素を比較検討するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
いずれの退職代行サービスにおいても、LINEやメールで無料相談できる体制があるため、悩んでいる人はまずは相談してみるといいでしょう。
>おすすめ退職代行の比較解説はこちら




円満退職するためのコツ
退職届が受け取ってもらえないという問題に直面しないようにするために、最初から円満に退職するための準備をしておくことが重要です。円満退職するためのコツは以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
就業規則に記載された退職までの期間を確認する
退職を考え始めたら、まず就業規則を確認しましょう。多くの企業では就業規則に退職の手続きや予告期間について記載されています。
一般的には退職希望日の1ヶ月前または2ヶ月前までに申し出ることが求められていることが多く、円満退職を目指すならこのルールに従うのが得策です。
就業規則は社内のイントラネットや共有フォルダなどで閲覧できます。退職予告期間を守ることは、会社側が後任の採用や引継ぎの準備をする時間を確保するために重要になるため、転職に影響しに範囲で協力するようにしましょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
稀に3か月を超える退職予告期間を設定している企業がありますが、これをそのまま守ると転職活動に悪影響が出かねないため、注意しておきましょう。
1〜3ヶ月前に退職の意思を伝える
退職の意思を伝えるタイミングは非常に重要です。可能であれば、就業規則で定められた期間よりも少し余裕を持って伝えることで、会社側も準備の時間が確保でき、引き止めにあっても余裕を持って対応できます。
退職の意思を伝える際は、まず直属の上司に伝え、その後必要に応じて人事部門にも伝えましょう。
繁忙期や重要プロジェクトの締め切り直前は避け、プライバシーが確保できる場所で1対1で話すことをお勧めします。感謝の気持ちを示しつつ、決意は固いことを伝えると良いでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
退職時期に配慮することで、無理な引き止めを避けることが可能になります。


前向きな退職理由を準備する
退職の意思を伝える際に伝える退職理由は、円満退職のためにとても重要です。
実際には人間関係や待遇面での不満があったとしても、できるだけ前向きな理由を準備しておくことが望ましいでしょう。
- キャリアアップのため
- スキルアップのため
- 新しい挑戦のため
前向きな理由を伝えることで、会社側も退職に対して「仕方ない」と受け入れやすくなります。
ただし、退職理由が職場におけるハラスメントやいじめ、労働関係法令の重大な違反によるものの場合は、会社都合退職で辞めるためにも正しく伝える必要があるでしょう。
-150x150.png)
-150x150.png)
-150x150.png)
もしも直属の上司のハラスメントを理由に退職する場合、直接伝えることは非常に難しいでしょう。
その場合は、上司の上司へ伝えるか、もしくは人事・労務部門の担当者へ退職を伝えるようにしましょう。


引継ぎは丁寧に行う
円満退職の最大のポイントは、丁寧な引継ぎを行うことです。退職後に、自分の担当業務を後任者や同僚が滞りなく引き継げるよう、十分な準備と時間をかけることが重要です。
- 引き継ぎ書を作成する
- 退職日までに完了できるよう、計画的に引継ぎを進める
- 後任者からの質問に答える時間を十分に確保する
- 取引先や社内の関連部署に退職と後任者の紹介を行う
特に長期間担当していた業務や専門性の高い業務は、暗黙知や経験則など文書化しにくい知識も多いものです。可能な限りそうした情報も伝えることで、会社への貢献度を示すとともに、後任者の負担を軽減することができます。
丁寧な引継ぎは、「最後まで責任を持って仕事をした」という印象を残すだけでなく、残された同僚への配慮にもなります。これにより、退職後も良好な関係を維持しやすくなるでしょう。




退職届を受け取ってもらえない場合の対処法に関するよくある質問
退職届の提出や受理に関して、多くの方が同じような疑問や不安を抱えています。
ここでは、退職届が受け取ってもらえない場合に関する、よくある質問と回答を解説していきます。
退職届を置いて会社に行かなくてもいいですか?
退職届を提出した後でも、退職日までは労働契約が続いているため、無断で会社を休むと就業規則に違反し、トラブルの原因になるおそれがあります。
ただし、有給休暇が残っている場合は、それを申請することで「出勤せずに退職日を迎える」ことも可能です。
スムーズに退職するためには適切な手続きを踏み、必要な引継ぎを行った上で退職日を迎えることが望ましいでしょう。
退職届の受理を拒否されても退職できますか?
はい、法律上は退職届の受理を拒否されても退職できます。
民法第627条により、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間経過すれば雇用契約は終了します。
また、契約社員や派遣社員などの有期雇用契約社員の場合は、やむを得ない退職理由があればすぐに辞めることが可能です。
どうしても会社側が退職届を受け取ってくれない場合は、内容証明郵便やメールなど、記録が残る方法で退職の意思を伝えるようにしましょう。
そうすることで、「退職の意思を会社にしっかり伝えた」という証拠が残り、あとからトラブルになった際にも、自分の意思表示が正しく行われていたことを証明できます。
退職届はいつ提出すべきですか?
正社員などの無期雇用契約の場合、退職届は退職日の2週間前に提出すれば、法律上は問題ありません。
ですが、ビジネスマナーとしては退職届の提出は会社の就業規則に定められた予告期間に従うのが基本で、一般的には退職希望日の1ヶ月前、業種によっては2〜3ヶ月前が多いでしょう。
退職の意思表示をメールで行ってもよいですか?
どうしても退職届を受け取ってもらえない場合は、メールで退職の意思表示をすることは法的に有効です。その際は、宛先に直属の上司だけでなく人事部門も含め、開封確認機能を使用するとよいでしょう。
会社によっては正式な書面での提出を求める場合もありますが、法律的には退職届によるものもメールによるものも変わりはありません。
もちろん、会社との関係を良好に維持したいのであれば、就業規則に従って書面で提出するのが望ましいでしょう。
ですが、特にこだわらない場合は、メールやLINEなど記録が残る方法で退職の意思を伝えるだけでも問題ないという考え方もあります。
退職をしたいのですが、後任が見つかるまで残って欲しいと言われました。
後任が見つかるまで残るよう求められるケースは多いですが、法律上、正社員の場合は退職届を出した2週間後に、後任の有無にかかわらず退職できます。
円満退職を望むなら「最大でも○月○日まで」など明確な期限を設けた協力の意思を示すことで、双方が納得できる妥協案を見つけるようにしましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合の対処法まとめ
退職届が受け取ってもらえないという状況は、精神的な負担となります。しかし、本記事でご紹介してきたように、退職は法律で保障された労働者の権利であり、適切な方法で対応すれば確実に退職することができます。
会社から退職を拒否され引き止めを受けた場合には、トラブルを避けるためにも、適切な対処法を心がけるようにしましょう。



昨今は退職代行サービスが盛んに利用されているという報道も見ますが、それだけ退職に悩んでいる労働者も多いということでしょう。
しかし、法律的には退職の効力を生じさせることはそれほど難しいことではありません。正社員であれば労働者が会社に対して退職の意思を通知するのみです。
この退職の意思表示について、法律では「こうしなければいけない」という決まりはありません。会社指定の様式に従って退職届や退職願を出すのはもちろん、退職の意思を記載した文書を郵送する方法や、退職の意思を明示したメールを送ることも有効です。
ただ、無用のトラブルを回避するためには退職意思を通知したことを事後的に証明できるようにすべきであるため、電話で口頭で伝えたという方法は避けた方がいいでしょう
※録音しても良いですが、その手間を考えればメールで十分と考えられます。


プラム綜合法律事務所
監修者 梅澤康二
【保有資格】
- 弁護士
【経歴】
第二東京弁護士会所属。
東京大学法学部卒業後、日本四大法律事務所の一つであるアンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。6年間の実務経験を経て、2014年に独立し、プラム綜合法律事務所を設立。
企業法務全般から労務トラブル、訴訟対応、交通事故、相続、刑事事件まで幅広い分野に対応。
著書・執筆実績も多数あり、労務管理やハラスメント対応の専門家として多方面で活躍中。
【主な著書】
『ハラスメントの正しい知識と対応 職場で取り組む予防・対策』(ビジネス教育出版社)
『それ、パワハラですよ』(ダイヤモンド社)
2025年5月4日監修


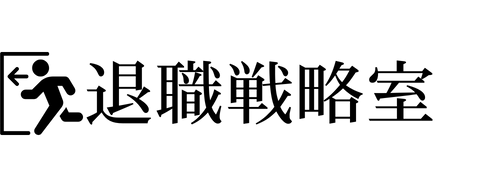
.png)




